第十三段
「亜細亜動乱編」
【 一 】
スペイン・イエズス会宣教師・バリニャーノは天正少年使飾とともに来日した。
天正十七年(1590年)一行は長崎港に到着。当時の宣教師は母国へ東洋諸国の情報を提供するといった役割も担っていた。
来日した一年後、バリニャーノは直接の上司であるスペイン領のフィリピン総督に対して報告書を提出しなければならなかった。そのため部下の宣教師・エスペランザと内容の検討をした。
「来てみて分かったが、日本は不毛で貧しいな」とバリニャーノが云った。
「ですが武力は侮れないと思います」とエスペランザはあごひげを撫でながら云った。
「なぜ、あのように熱心に軍事訓練をするのだろうか?」
「そうですね、秀吉が大乱を収め、とりもなおさず、いくさもなくなったのでしょうが」
「しかし、まぁ、この日本を征服しても益はないと思うが」
「屈強なこの国の兵を利用すると手を汚さずに明国を……」
「君は賢過ぎるのが……あだになるぞ」
「はい、恐れ入ります」
「まぁ、今後とも日本を重要視する必要がある、が趣旨になろう」
その後、バリニャーノは報告書をしたため始めた。さまざまな日本の情勢を書き連ねた末尾に、
「私が、ここで閣下に断言できることは、迅速に遠征するならばシナを簡単に征服できるということでございます。そして、このことを一層簡単に運ぶためには、シナの近くの日本が、すすんでこれに加わることでございます。秀吉を仲間に入れ込み、その強大な武力を利用すれば、シナ征服はより簡単にできましょう」と結んでいる。
【 二 】
十五世紀から十七世紀にかけてヨーロッパ各国はこぞって海外に領土を求めた。所謂「大航海時代」である。海外の新領土を「植民地」と呼んだ。それはインド・アジア・アメリカ・の各大陸で行われ、日本だけを除いて、ほぼ地球陸地の全域まで及んだ。
先陣争いはスペインとポルトガルであった。スペインはコロブスの新大陸発見後、中米メキシコ、有米のペルーを中心とした大領土を獲得した。さらに太平洋を横断してフィリピン諸島の領有にも成功した。
両国の植民地拡大の競争は激化し、憂慮したローマ教皇アレクサンドル6世が裁定した。大西洋上に西経四十六度の子午線を引き、東をポルトガル、西をスペインの領土とした。世に言うトリデシリャス条約である。世界はスペインとポルトガルに二分されたかに思われた。
スペインの植民地政策は入植することよりもキリスト教の布教と、黄金や財宝をかすめとることにあった。
コンキスタドーレス(征服者)はマヤ、アステカ、インカなどの文明を徹底的に破壊し、金、銀を奪い、莫大な富をスペインにもたらした。先住民虐殺の数は100万人とも云われている。例えばインカ帝国の人口は最大で1,600万人存在していたが、スペイン侵攻以来108万人まで減少した。
そんなスペインが虎視眈々と中国や日本に狙いを付けていたのが正に秀吉の時代である。
秀吉は果たしてどう動いたのか?
【 三 】
天正十八年(1591年)八月、関白秀吉は衆楽第に程近い利休屋敷内の茶室にいた。端然と茶を点てる利休、夜の帳はすでに落ち、先ほどまで煩かった日暮蝉の群声も途絶えて、静寂のみが二人を包んでいた。
「利休よ」と秀吉が口を開いた。
「はい」
「右近はそちの弟子であったな」
「はい、さようでございます」
「あれを、ルソンに流そうと思う」
利休の点前する動きがしばし乱れたかに見えた。
「訳を聞かぬのか?」
「関白様のご差配でございますから」
「お前にしては殊勝なことを云う」
「恐縮でございます」
高山右近は、天文二十一年(1552年)摂津の国で生まれた。十二歳で洗礼。洗礼名はドン・ジュスト。父がキリスト教に感銘を受け、家族全員で洗礼を受けた。
長じて右近は明智光秀との山崎の合戦に、いち早く秀吉の陣に駆けつけ功を挙げた。以来、秀吉の信頼は厚く、天正十三年(1585年)には播磨国明石郡に六万石を賜った。傍ら右近は茶道を極め、号を「南坊」と称し、千利休の覚えもめでたく七高弟、所謂「利休七哲」の一人としても知られる。
「これを見よ」と秀吉は一通の封書を利休の膝元まですべらせた。
利休はしばしお点前の動きを止め、封書に見入った。この書状は、秀吉が宣教師・バリニャーノの秘書を金品で篭絡し、入手した機密文書であった。スパイとして働いたその秘書は日本の文字にも精通していた。
読むうち利休は「なんと!」と驚博した。
「恐ろしいのう、エスパニアという国は」
「まことにでございます」
「明、朝鮮、そしてわが国まで盗ろうとしておる」
「恐ろしいことで」
「先手を打つのじゃ」
「南坊のことでございますな」
「きっとエスパニアも驚くに違いない」
「関白殿下はエスパニアの魂胆、全てお見通しと」
実は利休の妻と娘もキリシタンのミサに出向いていた。利休自身も何度か見学したこともある。司祭の教えを聞くうち「全ては神の御許では平等」の教義に感銘をうけ、「狭き門」からヒントを得て、「にじり口」を考案した。
しかし、利休はもう動揺などしていない。弟子の一人や二人失くしても痛くも痔くもなかった。為政者に取り入り、己の「俺び茶」が天下一になればいいのである。今後一切、妻や娘が教会に行くことを禁じよう。身の回りからキリスト教を消し去ろう、と。
かくして高山右近はルソンに流された。その後、かの地で非業の死を遂げる。
秀吉はエスパニアの意欲を砕くと、われらこそが「明国」を併合しエスパニアと対抗せねばならぬ、という考えが胸中に沸きあがってきた。所謂「唐入り」である。
家康や利家らも迫りつつあるエスパニアの脅威に憂慮していたので、秀吉の「唐入り」に対して反対意見がでなかった。
秀吉の行動は迅速であった。対馬の宋氏を通じ、「日本が明に攻め入るときは協力するように」という趣旨の文書を朝鮮政府に送りつけた。もともと朝鮮国は、中国・明を宗主国としてきた永い歴史がある。謂わば日本は弟分と思っているところに、手下扱いをされてプライドを傷つけられた。だが日本の武力を内心かなり恐れていたのだ。当然、明国に救いを求めた。
秀吉は大いに怒り、1591年、九州の名護屋(佐賀県)に城を築き朝鮮侵攻の準備をはじめた。
その場内の茶室で利休と二人だけの時間をもった。
「のう利休」
「はっ」
「この日本では、わしはいつまでも二番手なのじゃ」
「天下人ではございませんか?」
「世の中のものはそう云うが、違うのじゃ、上にもう一人いる」
「その方は、帝のことでございますか?」
「そうじや、この国ではどうしても帝の上には出られぬ」
「……」利休は言葉が出なかった。
「信長公は豪胆な方だった」
「まさか、帝を殺めようと……」
「そうじゃ、されば朝廷寄りの光秀に殺された」
「そうでございました」
「わしは、違う。明国の国王になる」
「ははっ!」
と、事のあまりの大きさに利休はただただ平伏するのみであった。
「のう利休よ」と先ほどまでの気迫は失せ、優しげに声をかけた。
「はい」
「わしにはもう一人、どうしても超えられぬ人間がおる」
「どなたで、ございましょう?」
「利休よ、お前じゃ」とニヤリと微笑んだ。
「殿下、ご冗談を」と平伏する利休の背筋に冷たいものが走った。
その年、千利休は秀吉より死を賜った。京都一条戻橋で首を吊るされたのだ。
秀吉の朝鮮侵攻は1592年、96年の二度に渡った。
秀吉は挫折し、慶長三年(1598年)この世を去る。享年六十二歳。
「つゆとおち つゆにきえにし わがみかな なにわのことは ゆめのまたゆめ」
【 四 】
それから約300年後の明治三十七年(1904年)二月八日、満州旅順港に配備されていたロシア旅順艦隊に対する日本海軍駆逐艦の奇襲攻撃で、日露戦争の火蓋が切られた。
ロシア帝国の満州及び朝鮮における権益の維持・拡大を、日本として防ぎ、同時に自国の安全保障を確保するためである。
信平の長男・辰十郎は、対ロシア日本陸軍の第三軍・乃木希典大将の幕下にいた。
乃木は先の西南戦争の折、政府軍として従軍しており、袂は分けたが心の奥底では深く西郷に心酔していた。乃木は《青龍の掛軸》と信平の関わりを知っていたのだ。
日露開戦の前年、乃木は副官を島原に派遣し、信平の従軍を請うた。高齢を理由に一旦は断ったが、再度請われたため、信平は長男・辰十郎を派遣することにしたのだ。
旅立ちの前夜、信平ほ辰十郎を自室に呼んだ。
「辰十郎、これを」と《青龍の掛軸》が収められた木箱を辰十郎の前に押し出した。
「はい、必ずや乃木閣下のそばにお届けします」
「なにか、二十五年前の私と似ている。あの時は西郷先生であったが」
「やっとお役にたてる日がきました」
「もう、充分修行も積んだ。心配しておらぬ」
「はい、ありがとうございます」
「家のことは心配無用、存分に働いてこい」
「はい!」
【 五 】
六月六日、乃木大将以下日本陸軍第三軍は大連に上陸、旅順を目指した。
辰十郎は野営の折、乃木大将の本部テントにしばしば呼ばれた。
その夜も乃木は《青龍の掛軸》を机に拡げて見つめながら云った。
「西郷さんも日々、これを観ていたと聞いたが……」
「はい、三万将兵の命を考えながら見ていらした、と父から聞きました」
「西郷さんの融和外交を採用していたなら、今回の……」
「戦争はなかった と云うことでしょうか」と、辰十郎は乃木に問うた。
乃木は《青龍》をなおも見つめている。
「そう思う。しかし大君の大命が下った今は、一軍人として任務を果たすのみ」
と真っ白いあごひげを撫でながら云った。
緒戦の勝利に勢いを得た海軍はそのまま上陸し、上陸兵による占領を強く満州司令部に要求。司令部はそれを受け入れ、陸軍の乃木にしばし停滞の指示を出した。加えて、既に引退の身であった乃木の大将復帰を歓迎しない雰囲気が、旅順港攻略担当の海軍当局には存在していた。
実は開戦前、海軍の一部には軍艦発注に関しての汚職が存在していて、陸軍までにも及んでいるとの疑惑があった。ここに明治天皇の怒りがあり、朝鮮上陸第三軍の長の人選に影響した。天皇は陸軍統帥部が出した人事案を三度にわたり拒否した。
苦慮した統帥部は会議を開き、席上、若手作戦課長の「お上の意中は乃木閣下にあり」の意見で決した。のちに明治天皇は「戦争は国民に塗炭の苦しみを強いる。乃木のような清廉潔白の人間でないと勤まるものではない」と語った。
この進軍の停滞が、後に「ぐずの乃木」と世間から揶揄される原因となった。乃木は海軍の横槍の件は一切弁明しなかった。事実、海軍の思惑ははずれ、ロシア軍は旅順港背後の高地に既に兵を配置していた。 あわてた海軍は前言を翻し、陸軍に侵攻を促した。が、遅れの付けは大きく、乃木軍ほ戦死者5,000名、戦傷者10,000名以上の犠牲を出した。
上陸後半年、十二月四日に乃木軍が203高地を占領し勝敗の帰趨が決した。
「多くの犠牲を出してしまった……」と乃木は呟いた。
「海軍が意地を張らなければもっと早くに」と辰十郎は悔しげに云った。
「しかたなかろう、海軍も旅順港封鎖の成功で勢い込むものがあったろうから」
「すみません、閣下」
「なにを、あやまる」
「《青龍の掛軸》がありながら……」
「いや違う! 西郷さんが側にいる、と思えただけで、どれほど心強かったか」
「そう云っていただけるだけで、うれしく思います」
「次は、いよいよ、海軍の決戦となる」
「天王山の戦いと聞いております」
「そこで、東郷閣下が貴方を望んでいる」
「えっ、」
「閣下は既にご自身で《青龍》を見られたそうだ」
「はい、以前、確かに島原にお見になりました」
「やはりな。辰十郎さん、貴方には生きてもらわんと」
「閣下! また閣下とお会いしたく思います」
そう云って乃木を見つめると、乃木は少し悲しげな表情で微笑んだ。
【 六 】
明治四十五年九月二十三日、明治天皇のご大葬の当日。
乃木はその朝、大礼服に身を改め、静子夫人とともに記念写真を撮影したのち、最後の参内に向かった。帰宅し昼食を摂り午後遅く、静子ともども居間に篭もった。
階下にいる義姉サ夕子はいぶかしんでいた。将軍がご大葬に列する気配のないのは不思議であった。
日も落ちて午後八時前、明治大帝が乗る霊柩が宮城を出る号砲が鳴り響いた。ほどなくサ夕子は、二階にあやしい物音を聞いた。すぐ様子を見に女中をやったが、座敦の戸は内側から錠が下ろされていた。内側からうめき声らしいものが聞こえたと云う。
実は女中はもうーつの言葉をはっきりと聞いでいた。それは乃木の声ではつきりと「龍が……」という言葉であった。あまりにも奇異な言葉なので誰にも言わなかったが、後年この女中が残した日記に明記してあった。京都大学国史学科教授・野中澄友博士が発見し、「乃木大将殉死始末」という論文に発表した。だが国史学会はこれを無視した。
乃木はまず妻・静子の心臓を短刀で刺し貫き絶命を見届け、自身古式に従って自刃した。
座して上着を脱ぎ、軍服のボタンを外し、腹を広げた。
軍刀を抜き、刃の一部を紙で包み、逆に掴み、左腹に突きたて、臍のやや上方を経て右へ引き回し、一旦刃を抜き、第一創と交差するように十字切り下げ、さらにそれを右上方へ撥ね上げた。作法でいう「十文字腹」である。
次いでズボンのボタンを丁寧にかけたのち、刃を上に、軍刀の柄を膝の間に立てると、死に向かって身を投げかけた。刃は乃木の頸部を貫き、頚動脈を裁断した。畳に鮮血が広がる中で、乃木は直ちに絶命した。
乃木は気が遠のく中、ご大葬の号砲に混じって「うお~っ」という龍の悲しむ雄叫びを聞いていた。
「これで、明治大帝と西郷さんに……会える」と、笑みが少しだけこぼれた。
【 七 】
明ける明治三十八年(1905年)、日露開戦以前、陸軍・明石元次郎大佐をリーダーとしたロシア労働運動の誘発工作の効果が出た。
ウラジオストック日本料理屋を舞台とした諜報活動の主人公は、信平の《青龍》を精神的支柱とした稲佐お栄こと道永エイであった。
お栄は後のロシア革命の立役者ウラジミール・レーニンの兄、ウリアノフに日本からの活動資金提供の橋渡しをしていた。ウリアノフは動乱罪で絞首刑になるが、弟のウラジミール・レーニンがその意思を継いだ。同年(1905年)一月九日、ロシア帝国の首都サンクトペテルブルグで労働者の大規模ストライキが起きた。参加者は実に十一万人に及んだ。「血の日曜日事件」である。
ロシア帝国は今まさに日本との戦いの最中、大打撃を喫する。
【 八 】
明治三十八年四月、猪原辰十郎は島原に帰っていた。
同月中旬のある夜。猪原家の座敦に男女五人が集まり、協議していた。あたりには重苦しい雰囲気が漂っていた。猪原信平を中心に辰十郎、日本連合艦隊参謀・秋山真之大佐、赤碕伝三郎、稲佐お栄の五名である。
赤碕とお栄はどちらも天草出身で明石大佐の機関に属していた。
赤碕はマダガスカル島シノべでウラジオストック港に向かうロシアパルチック艦隊を発見し陸軍本部にいち早く打電した男である。
三月十六日にシノべの寄港地を出たバルチック艦隊はいよいよ日本に接近する。その時期は五月下旬の予測。
秋山大佐が口を開いた。
「ウラジオへの航路は、対馬海峡経由、津軽海峡経由、宗谷海峡経由の三箇所が考えられます」
「どこを経由するのかの情報は、どう探りましても取れませんでした」とお栄がうなだれた。
「わたくしもであります」と赤碕も云った。
「三箇所全てに分散させれば、全てが撃破されます。どうしても戦力を一点に集中する必要があります。しかも、もう五月までには時間がありせん」という秋山。座は一層沈鬱になった。
「東郷司令長官より、猪原信平殿に相談せよ、と私に内々の命令が下りました」
「父にですか……大佐、それは荷が重過ぎます。日本の命運を決する判断ですよ」と、辰十郎は秋山に云いつのった。
「東郷元帥は、頑固な方です。信平殿の意見を聞けの一点ばりです」と秋山は引き下がらない。
さらに沈黙の時間が流れた。
「わかりました。秋山さん、やってみましょう」と初めて信平が口を開いた。
【 九 】
次の日から信平は辰十郎を伴い、弘法大師が百万遍の経を唱えた普賢岳の洞窟に向かった。それは信平がかつて「普賢岳」の鎮撫祈願をした場所で、峻険な崖の中ほどに穿ってあった。
洞窟に着くと、二人は略式の護摩を焚き、経を唱え始めた。二人の経は見事に唱和していた。
「オン サンマカ サトバン(普賢菩薩)、オン バザラ ダトバン(大日如来)、ノウマク サンマンダ バザラ ダンカン(不動明王)……」
暗い洞窟の中で朗々と響き渡った。
二人の一身不乱の読経は永遠に続くかのようであった。勿論、信平は時間の経過など念頭になかった。
乃木が戦い、今東郷が戦う、いずれも西郷縁の士である。『私を捨てた武人の戦い』に、信平も辰十郎も参加している覚悟であった。
【 十 】
どれほどの時が流れただろうか? 信平の声にやや衰えが出始めてきた。まだ霊験は現れてこなかった。
またしばし時が流れた。辰十郎は唱和しながら護摩を焚き次いでいく。
父の衰弱が気がかりになった。
「今回だけは、負けたのか……」と思い定めた刹那、「ドカーン!」と轟音と同時に洞窟が激しく揺れた。
「辰十郎、表を見よ!」と信平が叫んだ。
辰十郎は洞窟の入り口まで駆け寄り、空を見上げた。見ると、普賢山頂に大量の黒雲が集まり、わだかまって起ちあがった。みるみるうちにあるものに形造られていった。
「龍だっ!」と辰十郎が独語した。
「気をしっかりもて!」と信平が叱咤した。
「はい」
信平の読経に再び力が湧いてきた。
「父上、龍が動き始めました!」
更に読経の声が張ってきた。
「山頂から、去って行きます!」
「方角は!?」
「朝鮮の方です」
「対馬じゃ!」
普賢岳全体を覆いつくすような豪雨が降り注いでいた。


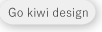 クリック!
クリック!



 トップ
トップ