春雨

出典:tenki.jp
暖気が近づき、雨がちの日々となりますね。
花を落とすの雨は是 花を催すの雨
(花を散らす雨は、花を咲かす雨)
出典:春簾雨窓 頼鴨厓
昔、吟じてた詩の一節です。懐かしい。
旭亭に春
島原 旭亭に春がやって来ました。
庭仕事

白い梅の花が咲き誇って迎えてくれました。春告草の別名を持つ梅。見る者の心を洗い流してくれるような白さ。

それとキンカンの実。こちらはマーマレードジャムにします。
今年は全国的に降雨量が少なかったので、早速水撒き。
そして樹々の消毒。かつてカイガラムシにやられましたので、この時期の消毒が大切です。
さらに寒肥。
さらにさらに雑草取り。
春以降の艶やかな庭園を迎えるための下準備がたくさん。ココロねっこ的発想。
島原野菜

そうこうしていると島原の親戚の方に野菜をまたいただきました。こんれが本当においしいんです。合掌。
いただいた庭先でジルがレタスをムシャムシャ。彼もレタスやキャベツが大好物。


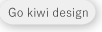 クリック!
クリック! 生きてることを楽しもう。座右の銘は荘子の「逍遙遊」。長崎県。
生きてることを楽しもう。座右の銘は荘子の「逍遙遊」。長崎県。

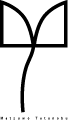
 トップ
トップ オススメ
オススメ 記事一覧
記事一覧 掲示板
掲示板 長崎マニアックガイド
長崎マニアックガイド 長崎の酒場
長崎の酒場 長崎を歩く
長崎を歩く 長崎キャンプ場
長崎キャンプ場 長崎インターネットラジオ
長崎インターネットラジオ 私の手作りキャンプ場
私の手作りキャンプ場 私の家づくり
私の家づくり デザイン
デザイン 絵
絵 音楽
音楽 小説
小説 メール
メール リンク
リンク