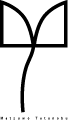1999年10月
1999_10_29
シルクロードの復活

キルギスでの人質が話題となりました。けれどその肝心な説明がマスメディアによってされません,いつものとおり(苦笑)。
今回の事件は,一言で言えばシルクロードの復活が起こってきていると言うことなのです。この地域の理解が進めば,世界史のイメージが変わってしまうでしょう
旧ソ連のウズベキスタン,カザフスタン,トルクメニスタン,キルギス(タン),タジキスタンの事を“ファイブ・スタン(stateの意味)”といいます。頭だけをとると加藤タキ。覚えるには便利です。
遊牧民の草原ハイウェー
シルクロードは大帝国の繁栄した地域でした。中国,南北インド,ペルシャ,ローマ。裏を返せば欧米が優位に立ったのは,たかだか200年前に過ぎません。
中央アジアは重要なハブ拠点だったのです。そして,いわば草原のハイウェーでもあり,スポーツカーのごとき駿馬を乗り回す遊牧国家が存在していました。たとえば,モンゴルは数十年でユーラシア大陸の大半を領土としましたし,もともと昔中国の西北部にいたトルコ人は今ヨーロッパに隣接しています。実際彼ら遊牧民族は強かったのですね。実は19世紀のアジアの大帝国として挙げられる清朝,ムガル帝国,オスマントルコ帝国のいずれもが,遊牧国家に起源をもつ国であることを認識していただけばいいと思います(「ムガル」という名は「モンゴル」のインド式発音)。だから写真のような顔なんです,簡単に言いいますと。
1991年のソ連崩壊で再注目
で,再びこの中央アジアをみんなが注目しはじめています。なぜか?中央アジアは旧ソ連に組み込まれていたため,この地は世界から忘れ去られていました。封印されてたんですね。それが1991年,ソ連邦の崩壊後に歴史の舞台に再登場したのです。今後,中国がさらに開放政策に向かうならば,いよいよシルクロードが再現されてきます。オープンにされると元々が戦略的な要衝です。みんなが注目し,ここに利権と権力抗争が生じているのです。欧米諸国はNew Western(新天地)とさえ呼び始めているほどです。
CF.遊牧民族のお勉強
スキタイ,匈奴,突厥,フンなどはいずれも民族名ではなく,遊牧国家と考えたがよい(「遊牧民から見た世界史」杉山正明,日本経済新聞社)。たとえばモンゴル帝国の構成員のうち,支配者であるモンゴル人はほんの一部。その中には漢民族もいれば,スラヴ系の民族もいる。このようにハイブリッド的性格を「遊牧国家」は持っていた。高校世界史の教科書のように「勃興したフン族が移動してきたため,ゲルマン人の大移動がおこり……」などというと,「フン」民族が急に現われたり強くなったりしたという印象を受けるが,実はそうではなく,さまざまな民族を含んだ遊牧国家がやってきてる。だから急に強くなったり,瓦壊してどこかへ消えてしまったりするのも充分納得のいくことである。


 ホームページは欲しいけれど、高いのは勘弁してほしい。
ホームページは欲しいけれど、高いのは勘弁してほしい。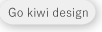 クリック!
クリック! トップ
トップ オススメ
オススメ 記事一覧
記事一覧 掲示板
掲示板 長崎マニアックガイド
長崎マニアックガイド 長崎の酒場
長崎の酒場 長崎を歩く
長崎を歩く 長崎キャンプ場
長崎キャンプ場 長崎インターネットラジオ
長崎インターネットラジオ 私の手作りキャンプ場
私の手作りキャンプ場 私の家づくり
私の家づくり デザイン
デザイン 絵
絵 音楽
音楽 小説
小説 メール
メール  リンク
リンク