Zone

1 カウンター
失神から目覚めるような朝を,また迎えた。胃が重く焼ける。口腔には唾液がたっぷりと溜つている。
傍らで,柔らかな寝息を立てている妖精を起こさぬように,そっとベットを抜け出し,バスユニットに立つ。顎の力をゆるめると,粘性の高い唾液が長く尾を引いて流れ出した。クリーム色の洗面台と僕の唇を結ぶ睡液はめまいがするほど透きとおり,ライトを受けてキラキラとぬめった。そして,その美しさ故に,冷えきった恐怖感が僕を襲うのだった。
熱めのシャワーを浴びる。急に胃が収縮し,僕は吐きあげる。アルコールの匂いとともに,少しばかり血の混じった酸性の液体が垂れる。
振りかえると,ゾーンに来てからまだ主食らしきものをとったことがない。皆アルコールにからめながらの摂取だ。昨夜の盛り上がりも凄かった。誰かが途中でトルエンを撤いたのかもしれない。フジノが名言を吐いた。マーゼンの野郎らは身体鍛えろって言ってるけどさ,こうやって不節制やっていることと,鍛えることにどんな違いがあるって言うの? どっちにしたって負荷をかけているわけだろう? 同じじゃないか。
全身にシャンプーをかけると,身体は生ゴミの詰ったポリバケツのように思えた。
赤い着色のきいた苺に,コンデンスミルクをたっぷりとかける。一粒つまみ口に運ぶ。甘ったるいとろみの中,プチプチと音が立つ。昨夜吸い過ぎた二コチンの味がする。
彼女は,しわの寄ったシーツに唇をすぼめよせて眠り続ける。朝の唇だけはルージュを引かないで欲しい。僕はブランデーを含み,そっと彼女に口づけをする。妖精は夢に沈みながら,少しだけ伸びをした。
カーテンを開けると,相変わらず乳濁色の世界が広がっていた。霧はベランダにまとわり手摺さえもぼやけさせている。
ゾーン。深い霧に覆われた不思議の領域。晴れることのない霧に包まれて,どこまでも樹海が広がり,沼が点在する。その只中に忽然とアーケードがある。まさに忽然とだ。入域ゲートをくぐり,ゾーンを一昼夜歩き,やっとのことで来訪者はアーケードの姿を目にする。ここはそのアーケードの南塔十六階,妖精の部屋だ。
眼下にうっすらと広がるアーケード。今日のように霧の薄い日には,部屋のベランダ越しにアーケードの屋根裏が見える。アーケード第三層の通りだ。目を凝らすと,アーケードを基盤にして立ち上がった東西北それぞれの塔と,それらに取り囲まれるように伸びた聖塔ロゴスの細長く巨大なシルエットが望める。僕がいるこの南塔も含め五つの塔には,ぎっしりと様々な店舗や施設が詰っている。けれどその煩雑さのため,把握しているのはほんの限られた場所だ。
指についたべとつきを嘗めながら,首をまわす。ゾーンに来て,もうニヶ月が過ぎ,彼女との暮らしも,一ヶ月半が過ぎた。
鮮かに,彼女と出会った夜が思い出される。
◇
カウンターの隅には,熱帯魚の水槽が置かれていた。スポットを浴びて,エアーがゆらめく。その間を,セロファンのような胸ビレを震わせて泳ぐ脊椎の透けた魚が数種類。気抱の音はどこかしら実験室の静けさを思わせる。僕はその前の席に座り,瑠璃色のきらめきを持った小魚の動きを目で追いながら三杯目のバーボンをなめていた。五匹の群がガラスに写った僕のぼんやりした顔の中で苦しそうに口をパクパクさせたかと思うと,一斉に反転してサーモスタットの陰へと向かう。
「退屈だわ」
水槽の中,僕の横で女の唇がポツリとそう言った。
「退屈だわ,いつ来てもこの店」
グラスの氷が,カタリと肩を落とす。同時に,僕の小ネジも少し左へ回転する。
「もう長いの?」
僕の言葉に,なにが? という目で女は振りむく。どことなくオフチャンネルのブラウン管を連想させる瞳だ。
「なにが?」
「この店の常連さんだろ,君?」
ミルはきまぐれにドアを鳴らしたにしては落ちつける店だった。バーやスナックの類いではない。昼間は喫茶で通し,夜はモグリで酒を出す。そういった店だ。オリーブ色の縁取りを持つカウンターが,赤い嫌瓦に囲まれた店内を二分している。あちら側がマスターの,こちら側が僕たち客の領分というわけだ。高めの黄色いスツールが五つ並び,脇にはスタンドピアノと,小さなテーブルが二つ。六人も客が入れは満員御礼の札も出始めそうな店だ。僕は一番端にかけ,今まで熱帯魚の疎外感について考察を巡らせていた。
女の子をそんなふうに言っちゃだめよ,と微笑みながら彼女は答える。
彼女は僕を,別の種族のように眺めた。
「そう言うようにしてる,女の子にはね」
「じゃあ,女の人には?」
「お一人でしょ? そう言うね」
「お一人じゃなかったら?」
「さよならって言う」
女はパールのイヤリングをいじりながら,声を出さずに笑った。それが,最初にみた彼女の笑みだった。胸元で細いチェーンが虹のように揺れ,彼女は電話に立った。
メタルのボタンを押す指が,しなるほどに長い。年齢は二十代半ば。濃いグレーの光沢を持ったスーツに,シルクのブラウス。幾重にも巻いたパールとチェーンのネックレス。受話器に向かってうなずくたびに,ボブが揃ってなびく。声さえなければ,カクテルグラスの縁に輪をなす塩のように小粋な女だ。
その夜,僕等はアーケードの中でつまらぬジョークを飛ばしあい,両手の指以上の角を細かく曲り,古びた店により,ハンバーガーをほうばり,アルコールをお互いにもう一杯ずつ煽り,あなたって見た目よりずっと不器用ねと彼女が言い,ワインをもう一杯煽りたいなと僕が漏らし,彼女のワンルーム・マンションに転がり込み,灯を消して,じゃあお休みと言い,それでお休みにならず,明け方に寝息を立てることになった。
女に名前を聞くと,飛べない妖精よ,と笞えた。
つい昨夜のことのようだ。けれど,もう一ヶ月半が過ぎている。
◇
「おはよう,ねえ何時? 沢田くん」妖精がベッドの中がら,目だけを覗かせ宣う。
「二時さ」
「素敵な日になるかな?」
「どうして?」
「誕生日なの」
湯気に咳をしながら,彼女はコーヒーを飲んでいる。
キラキラと輝くCDは,イーノの『鏡面界』だ。プレイヤーは,途中つまずきながらCDを引き入れる。近頃少し調子がおかしい。
「君が生まれた日も,やっはり霧だった?」
僕が言う。
「深い霧の中に生まれたわ」
「実にロマンティック」
「そう?」彼女には,小首を傾げる癖がある。
「プレゼントは何がいい?」
「本当に!」
「支度をしなよ。出掛けよう」
メタル・フレームのボストン眼鏡に,男物の四つボタン・ジヤケット。これが妖精の出立ち。僕は,ニットのチャイナ・ジヤケット。今日のエレベーターが下降する。
一階アーケードまでの間に,十八回エレベーターは止まり,四十二人が乗り込み,三十六人が降りた。晩冬の夕方。薄闇が世界を支配し始める時刻。
到着を知らせるチャイムが鳴る。
ドアが開くと同時に,圧倒的な音の洪水が押し寄せる。アーケードは人と霧でごった返している。まるでゾーン域の音という音を,すべてこの通りに詰めこんだようだ。華やいだ会話,酔いどれの罵声,恋人達の囁き,口論,歓声,爆笑,その上に降り懸かる何万人分かの足音。それらが無秩序なまま渾然となって,ショーウィンドゥに,タイルに,反響し共鳴しうねり合う。長く連なるアーケードの通りは,左へのゆるいカーブを描きながら,霧の中に消えている。道には横一列につきチェス盤大の大理石タイル五十枚ほどが敷かれている。かなりな道幅だが,両サイドに所狭しとへばりついたディスプレイが,げびた笑いを繰り返し,実際よりずっと狭く感じる。そして人,人,人。人の頭が,うごめく複雑なゴブラン織のようだ。ナイフで一気に切りさかれた孵卵朋の蜂の巣は多分こんな様子だろう。異なる顔は異なる記号だ。それ以上でもなく,それ以下でもない。
横を行く緑色に髪を染めた男の肩には,力メレオンが止まっている。カメレオンは抱えきれない心記事でもあるかのように,眼球をでたらめにまわすほかはピクリともしない。高笑いを上げる女達が降って湧いたかのように現れ,乾杯を叫ぶと,ぶつけられたグラスは,甘い芳香を撒き散らしながら,粉々に砕けた。極彩色のネオン光線を黒いオーバーコートの背に受けながら,男が街角で吐いている。男の喉は三度ゲロを戻しては,苦しそうにヒューと音を立てて息を吸う。その横をデニムのジャケットをはおった女が,チェーンを鳴らし過ぎ去っていく。馬鹿言うんじゃねえよ!とパープルのアイシャドゥをひいた男がそれを追う。
狂おしいほどに猥雑なアーケード。人々は,本来のアーケードと五つの塔を合せたこの街全体もまた,アーケードと呼称する。そしてアーケードの外には,濠々としたゾーンが広がる。
僕等は雑踏の中を泳ぎ,時々僕が彼女を大声で呼び,彼女が人波の向うで手を振り,何を買いたいのと僕が尋ね,顰蹙と彼女が答え,ブティックで小一時間迷ったあげく彼女はラインストーンがびっしりと埋め込まれたベルトを選んだ。めでたし。さあ,ミルに行こう,夜が始まった。
◇
マイルスの『クッキン』が鳴っている。
妖精は,ミルによく溶けこむ。ジクソーパズルのピースのようだ。
「なに飲む? おごるよ。誕生日なんだって?」
グラスを持って絵描きのフジノが,僕等の席へやって来る。この店の常連で,画家でゲイだ。
向うのテーブルでは,老人とスーツの男が,タロットを広けている。タロットカードを睨み,眉間に皺を寄せたスーツの男。老人は唇を撫でながら,だから影は光を忌むんじゃよと呟いた。その情熱とやらも,結局は黒い波に飲まれる。あんたの意見も通らんて。スーツの男はゆっくりと首を振った。
「なんにする?」と,フジノ。
「チェリ―バルブ」と,妖精。
「それで乾杯といこう。沢田くん,それにマスターもね」
ウオッカをベースに,レモンジュースとオレンジキュラソー,グレナダンがシェイクされる。フリーザーからグラスが四つ取り出される。霜が一面に付着しているよく冷えたグラスだ。マスターは神妙にカクテルを注ぐ。「では」と言って茶漉し状の網を持つと,水槽から器用に2センチほどの熱帯魚をすくいグラスヘ落した。魚は激しく尾ビレを震わせ,カクテルの細かい雫をカウンターに散乱させる。「こいつの頬はいつだって情事を楽しんだ後みたいに染まっているなあ」フジノが呟いた。「チェリーバルブは近頃よく出るよ」そう言ってマスターは四つ目のグラスに飾る。
「では」
フジノが嬉しそうに髭を動かす。僕達はグラスを手にとってかがげる。
「では,我らが飛べない妖精の,誕生を祝して!」
グラスは歯と歯がぶつかる音を立てる。僕達は一気に飲み干す。喉の中を魚が泳ぎ下っていくのが分る。胃に近くなってその感覚はぼやけ,そして消えた。
急にフジノが咳込んで,口の中のものをぶちまける。
「あ~あ,だらしないんだから」
向こうの席でイスの音がした。見ると,スーツの男が立ち上がっていた。
「忘れているのです。入域ゲートをくぐったとき,誰にとってもここはフロンティアの地。そして流され,腐敗し,享楽を耽り」
「何度シャッフルしても現れる黒い影をどうする?」
老人は手に持ったタロットをテーブルに置いて続ける。
「確かにお前は,ようやっとる。けれど集団の意思というもんは,成員の意思を離れて蔦をからめ始める」
スーツの男の唇が動こうとした。
「大きな声を出すのはやめて」妖精が言う。
男がこちらを見る。
「先カンブリア期の思想のようでさえある」 フジノが呟く。
「でしたら,考古学者になったがいい」
「今でも,アーケードじゃ,みんなうまくいってるわ」妖精が言葉をぶつける。
「日々が重くないですか?」
彼女は,眉をちょっと上げて「なにそれ,分らないわ,ねえ」と僕に聴く。
スーツの男は溜息をついてコートをはおった。一つ一つボタンを確認するように止め,丁重にたたまれた財布から取り出したキャッシュで二人分の支払いを済ませると、重いドアを開いた。外の喧騒が下卑た邪気のように押し寄せる。
「お騒がせしました」
広い肩がドアに消え,そして,カウベルの音が店内に残る。
「さむいわ」
「いい人だと思うよ」
「あらマスター,いつからマーゼンになったの」
「僕はいつだってニュートラルさ。イワサキさんはいい人さ」
やれやれと老人はタロットを切る。
「ほら、また」そういってカードを見ながら、スコッチをあおる。
「ご心配ですね」とマスター。
「厄介なことに巻き込まれなきゃいいが。息子は死んだ女房に似て」老人はそう漏らして店を去った。
ふう,と息をつくと,マスターはピンクの遺骸をつまんでフジノの頗に持っていく。ほら,魚は綺麗に飲まなくちゃ。フジノは笑いながら舌を出してそれを受けた。
「ねえ,『マプート』かけて。ディビット=サンボーンのやつよ」煙草をくわえながら,妖精がリクエストする。
「ゾーンにはどれくらい?」僕は,フジノに尋ねた。
「忘れたね。僕達はここの市民なのさ」
「君は?」妖精に尋ねる。
「なにが?」
「ここはどのくらい?」
「忘れたわ。忘れることで厚顔になったわ」
「ヨウちゃんはまだ大丈夫。レヴューもまわらず,ここにへばりついてる」
「お金ないだけよ」
「作ってくりゃいい,ゾーンで」
「禁じ手よ,それ」
「みんなやってることさ」
不思議の領域,ゾーン。アーケードを離れ,霧深いゾーンの只中,来訪者は「形成」に挑む。自分のバイブレーションと同調する地を捜し出すことが大切だ。うまくいけは,地中より願望するものを沸き上がらせることが出来る。貴金属・カメラ・ファミコン・冒物・セーター・ビデオ・旋盤・バイク・ウィスキー・スカンジナビア=デザインのソファー・赤い毛玉・ウォーホールのシルクスクリーン・海綿・シルバーブルーのマフラー・色黒の兄・ブロンドの情婦……。そうしたありとあらゆるものの形成に来訪者はチャレンジし,そして見事手中におさめ,あるいは無念の涙を飲んできた。この「形成」現象こそ,ゾーンのゾーンたるところだ。来訪者もまたそれが目的でゲートをくぐる。
また来訪者にとって,ゾーンは危険極まりない地でもある。人の心が虚脱状態にあるとき,ゾーンの地は人の心をからめ取るのだ。アイデンテティの喪失。これを人々は,ゾーンの「侵略」と呼ぶ。
しかしこうしたゾーン域にも,「侵略」が見られぬ場が,一箇所だけあった。アーケードだ。こうしてアーケードは,人々の宿りと安らぎの場となっていた。
そしてまた,各人の形成力には個人差があり,ゲートで貰った証明書によると僕のレベルはC5。すごい数値じゃない、と妖精は言った。僕の滞在パスポートが切れるのは,一ヶ月後。冬の終りだ。
◇
僕と妖精がほろ酔い加減でミルを後にしたのは,午前零時を回った頃。けれどもメインアーケードは,ラップダンスのように込みあっていた。
オートピアノがご機嫌なラグタイムをやっている。ピアノの上にはホログラムが置かれ,虹色の像を浮き出していた。ラグタイムに会わせて陽気にタップを踏む小豚の映像だ。ワーオという声が聞こえた。スケボーに乗った髭だらけの大男が霧の中から現れ,山積みされていた音楽ソフトの中に,ディズニー=アニメのようにぶつかって行った。店員が真赤な顔をして現れ,妖精は大声を出して笑う。「あいつが悪いんだ」と大男は,路上で高いびきをかいているジャンパーの老人を指さして怒鳴った。「あのじいさんは動かんが,あんたはここまでやって来た」と店員が怒鳴り返す。なるほど,そりゃそうだ。
アーケード,二十四時。眠り入ることを知らない。
へけべれの酔払いが突然,妖精に抱きついく。彼女は奇声をあげる。僕が笑う。振りはらわれて男は倒れ,レモン色に光るトルソのディスプレィを粉々に壊した。
ダッシュして,エレべーターに見事な滑り込みセーフをきめる。西塔の三十二階までそのまま昇り,やたら小さなパブやバーが並ぶ狭い通路を抜け,また別のエレベーターに滑り込み二十四階で降りると,そこは倉庫街で人影は疎らだった。暗闇の中にまるで映画のセットのように立つアイスクリームショップをみつけて立ち寄り,お互いにバニラを一つずつ食べた。時にはハードボイルドもいいわね。アイスはソフトにかぎる。店を出てキスをすると,彼女の唇は冷たくてバニラの味がした。
「高い空を見たいわ」
「え?」
「外の世界よ。なにか外のこと覚えてない?」
「ビル。銀色の被膜を外側にコーティングしたガラスだらけのビル。近くの歩道橋の真中あたりに行って跳めると,そいつの前に広がる町並を,後向きにして鋭いカッターで切り取って立っているようなやつさ。僕はそこにCDを持って通うんだ」
「CD?」
「うん,ビートルズの『マジカル・ミステリー・ツアー』なんかね。気晴らしになるのさ。そいつをかけて僕は何かやっていたよ。忘れちゃったけどね」
「ゾーンに入るとき?」
「僕の好きなものはベジャールの振り付けで,嫌いなものは曇日のデートさ。僕はいろんなものを覚えてるよ。だけど,肝心なところが思い出せないんだ」
「みんなそうよ。それがゾーンなの」
再びメインアーケードに降りて,イベント広場に抜ける。光の祭典の中,上気した聴衆に紛れる。突然歓声と拍手が沸き上がる。ステージに車椅子の老人が現れたのだ。
「誰だい?」
「市長よ。正式にはアーケード自治長とでも言うんでしょうけど,みんなそう呼んでるわ」「人気があるんだ」
「まあね。昔このアーケードではケーブルテレビのスターだったのよ。前の市長が暗殺されて,彼が後釜ってわけ」
「いいマスクをしている」
「ここの男達の半数がゲイだわ。彼はマスコットみたいなものよ」
バニーたちに囲まれ市長は,手を振っている。
「彼の家族は?」
「なに言ってるの。家庭ですって? 誰が好き好んで足かせを履くっていうの? ミルのマスターもその変り者の一人だった訳だけど,結局別れたわ」
僕が首を振り,妖精がその真似をして首を振った。
その時,爆音が背中を襲った! 首のないバニーが転がる。ステージ上に立ち昇る煙。叫びが上がる。テロだ! 黒煙の中,市長の回りを取り囲むSPが見える。一瞬の出来事だった。
「近頃よくあることさ。バカが増えてきている」
近くで誰かが呟いていた。
 ホームページは欲しいけれど、高いのは勘弁してほしい。
ホームページは欲しいけれど、高いのは勘弁してほしい。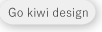 クリック!
クリック! トップ
トップ オススメ
オススメ 記事一覧
記事一覧 掲示板
掲示板 長崎マニアックガイド
長崎マニアックガイド 長崎の酒場
長崎の酒場 長崎を歩く
長崎を歩く 長崎キャンプ場
長崎キャンプ場 長崎インターネットラジオ
長崎インターネットラジオ 私の手作りキャンプ場
私の手作りキャンプ場 私の家づくり
私の家づくり デザイン
デザイン 絵
絵 音楽
音楽 小説
小説 メール
メール  リンク
リンク


