Zone

2 飛べない妖精
来訪者の僕は,彼女のマンションで暮らしている。けれど僕は,彼女が何者なのかを知らない。惹かれたのは,出会った時点の彼女だ。だから何も知る必要はない。僕達の間に進むべき前方などない。僕が解っていることといえば,時々彼女はどこかへでかけ,疲れて帰って来るということだけだ。「……マンホールの中って興味ない? サンゴが生い茂げって微かに輝いているのよ」そんなことを,妖精は時々唐突に言う。それでいい。◇
「ゾーンの侵略に気を付けて。これが見納めになるかもね」リュックを担いだ僕に妖精が声をかける。
「縁起でもないこと言わない」
来訪以来初めてゾーンへと向かう。いまだになにが欲しいのか,自分でも定かではない。ゾーンの奥地へと向かい,形成にチャレンジしてみよう。奥地には答があるかもしれない。
「お土産,お忘れなく」
「何がいい?」
「あなた名義のクレジット・カード」
「引き出すのはジョークだけにしておくれ。それに日帰りなんだよ」
「こんな朝早くから,お見送りしてあげてるのに」
妖精はべットの中から顔だけ出して,そう宣うた。
ゾーンは冷えてる事だろう。ウールの肌着にタータン・チェックの登山シャツ。厚手の靴下にワーク・シューズを履くとスタートだ。
高さ三〇メートルの巨大な手首。アーケード北門の両口にそそり立つモニュメントだ。そこからゾーンへと踏み入れる。あとは濛々たる霧と樹海の支配する世界だ。
風は無い。五十メートルほど続いていたアスファルトの小道はふと跡切れた。歩を交すたび,重なり朽ちた落葉の間から,木霊の記憶をブレンドした液が滲み出てくる。何気なく開いた古文書からふと立ち昇ったような芳香が漂う。時折虫たちは這いずり回り,僕に個別の発生意義を訴えかけて消えて行く。なめし皮のリュックは思いのほか肩に馴染み,疲れを感じさせない。
冷える。二時間ほど歩いたところで,リュックから上着を出して着込む。
乳濁色の霧は依然何も見せてくれない。無限に広がる単調な世界を歩いているような,そんな不安感に襲われ始める。僕はなにも悪いことはしてない。
……そう?
……僕は砂浜に遊ぶ子供さ。
……そう?
……子供は砂でお城を作る。明日来れば,波に流され跡形もなくなってしまっていることを知りながら,僕はお城を作っていたよ。
……悲しいの?
……僕のこと?
……そう。
……少しだけね。
……いらっしゃい。抱いてあげるわ。
キキッと鋭い鳥の鳴き声が辺りに響いた。はっと我に帰る。危ない。ゾーンの侵略が始まっている。ゾーンは虚脱状態の心に忍び込み,人間の心を溶解させ,奪い取る。「形成」と「侵略」の地ゾーン。帰らぬ人となった来訪者も多い。
鮮かなオレンジ色の苔が密生した樹木にもたれる。樹肌は,ねっとりと濡れていた。歩みを止めた途端に身の細るような静寂が訪れる。時折,鳴き声が響き渡る。指先を揉みながら,僕は樹海の奥を覗く。
冷たいものを感じた。ゾーンの意識が,また周囲でさざなみのように立ち上がり始めている。全身に鳥肌が走る。突然,目に見えぬ強い力が僕に覆い被さった。樹海が僕の頭蓋骨を開き,中を硯く。震えが起り,全身の毛穴が開く。頭の中で,ゾーンがなにかを切った。僕は悲鳴を上げながら卒倒する。視界が暗転して行く。
静・か・だ。
その温水プールに人影は見当たらない。水面から立ち上る仄かな湯気が,霧と溶け合い境がおぼつかない。階段を下りフェンスを開ける。警備員もいなければ,監視員もいない。マリンブルーのタイルが敷き詰められ,まるでオープンを侍つばかりとなった新装プールのような清潔感が辺りを覆う。周囲にのびる枝葉の細い木々が,モノトーンとなって水面に揺めく。コースは9コース。赤いブイは濃霧の向うに消えている。何メートルコースなんだい?
僕は静寂を聴く。
5コースに立つ。
グレゴリアン聖歌が好きだった。十代の時だ。
僕は,神の存在を疑わない少年だった。
無音は緩やかに僕を圧縮する。僕は無音に鼓動を返す。
構える。風がわずかに吹いた。
ジャンプ!僕は鮮かにきめる。静けさを裂き,水飛沫が上がる。心地好い温かさだ。君は知っているか? この地平は常に包囲されているのだ。くそっ!僕は一直線に樹林の只中をクロールする。頭上には,数十匹の人面のコウモリが飛び交う。彼等は声高に笑った。
八十メートルもいったところで影が迫る。近付く。霧から姿を現したのは,墜落した飛行磯の巨大な機首だった。機首は小首を傾けたような状態で傾いていた。ジュラルミンの外壁は底面部が捲れ,その内部がうかがえた。機首の中に人影が認められる。目を細くして仰ぎ見る。それは,今は,亡き,父の姿だった。
父は読んでいた新聞をたたむと,じっとこちらを見た。
「さもしい奴め。なにを形成に来た」
恐怖感はなかった。懐かしさがあった。
「分らないんです」僕は答えた。
水に滴ったインクのように意識が拡散していく。
ボタン雪のためらい。
安らかな眠りに落ちる間際の静寂。
「僕はなにが欲しいんでしょう?」
波間に揺れるプディング。
「愚か者め」
父は穏やかに上昇を始める。霧は父の姿を包み隠す。
いつもそうだ。僕だけが一人残されて行く。
◇
四日間の徘徊のあと,僕は発見された。保護されたとき,僕はうずくまり歌っていたらしい。その後,意議が正常に戻るまでに五日間を要し,妖精の部屋に戻るまでに三日間を要した。アーケードは相変わらず,チューニングが狂ったギターのように猥雑な音を立てていた。
◇
妖精の部屋。転がるヘアーブラシ。ブラシにからまる無数の髪の毛。短いものが僕の,そして長めのやつが彼女のものだ。二人の交わった匂いがするだろう。
投げやりな視線を落したまま膝小憎を抱える妖精。彼女の膝小憎には,生々しい大きな擦り傷がある。
「どうしたんだい?」
「別に」
僕が形成にでかけている間に,彼女に何かがあった。アルコール漬けの臓物のように,のっぺりとした表情をして通り過ぎる時間。
僕は唐突に話し出してみる。
「実は昨夜,妙なものを見たんだ」
「?」
「真夜中の行進。真夜中に,何百人っていう人達が,アーケードから霧のゾーンに消えていくんだ」
「ペルモス教徒よ。礼拝にでかけたんだわ」
「いい趣味じゃない」
静かなるペルモス。彼等はゾーン域全体を神とし,そこに住う者は神に抱かれた存在であると信ずる。彼等にとって形成は神儀であり,必要欠くべからざる物のみを授からねばならない。生活必需品の店舗は,例外なくペルモスによるものだ。
彼等には,数千年間語り継がれてきた言い伝えがある。カリスマの伝説だ。創造主カリスマは,いつの日にか聖塔ロゴスより,御身を金色に照り輝かせこの地に降り立ち,霧と腐敗を清めるであろう。カリスマの意思の中,うたかたの幻にすぎぬ我々は常に謙虚であらねばならない,と。
「ロゴスの塔は五階より上に登る通路の入口が,そこでぷっつりとぎれてるの」
「じゃあ,壁を崩してみりゃいい」
「ペルモスが暴動を起こすわ。それに……」
「それに?」
「怖いわ」
「君も?」
甘いオレンジジュースを一口飲んで彼女は続ける。
「そう。あなたの愛する人がいたとするでしょう,この人がいなきゃ僕は駄目だってほど思いを尽くした人よ。その人のこと,過去の隅々まで知りたいって思う?」
「思うね」
「……あなた,幸せになれないわよ」
窓の外を覗く。霧が薄い。アーケードの屋根裏に這い回るあらゆるものが今日は見える。配線,パイプ,看板を支える無骨な鉄枠や錆びた針金,それらにからまるビニール製の紐,古くなりはげ落ちたポスター。けばけばしいちらしは風に寄せられ,一カ所でどろどろになりカビをふかせている。
目にしてはいけない光景だ。
ああ,青い空を見たい。
「このアーケードは膨大な無駄話の缶詰だわ」
彼女が言った。
「どうしたんだよ,急に?」
妖精は時々歪んだ笑いをみせる。「ネガとポジよ。分かってるから,高笑いをするの」いつか彼女が言った悲しいセリフだ。
「あなたもいつかは,このゾーンを出ていくわ」
「だろうね」
「出域の期眼日まで,あと何日?」
「十六日」
「消えないように注意することね」
「消える?」
「消えちゃうのよ。期限が来てもまだゾーンにいると」
「悪い冗談だ」
「本当よ。あなたが,ここで飲んだくれてた。期限が切れた。あなたは私の目の前で陽炎のように消えていくの」
「君はなぜ消えてない」
妖精は一瞬とても空虚な顔をした。まるで下降する瞬間のエレベーターの中のように空虚な顔だ。
「昔,一日に三冊ずつ本を読み続けたことがあったわ。くだらない時間に読む,くだらない本ばかりよ。あんまりくだらないんで,しばらくして自分でお話を考えて楽しむことにしたの。その中でも一番お気に入りだったのが,緑色のワニの話」
「縁色のワニ?」
それから彼女は,とつとつとワニの話をしだした。
「緑色のワニの話よ。この宇宙のどこかに緑色の星があって,その星には緑色したワニが住んでるわけ。ワニ達はちょっとした文明を持っているの。会社なんかにもスーツを着込んで通ってたり,エプロンをつけて家庭でまな板に向ったり,そんなことよ。解る?」
「ああ」
「けれどワニ達は,おかしな習性を持ってるの。時間があると,空を見上げるって習性。それにワニ達は,一端見上げると,空に見入ってしまって,ジッと動かなくなっちゃうの。少し口を開いて,ワニ達はまるで置物のように動かなくなるわけ」
「長いこと?」
「長いことよ。その緑の星には,ワニが八十二億五千万匹いるわけ。その多くが空に見入ってしまって,じっとしてるの。想像してみて。スーツを着込んで帽子を被ってカバンをさげたワニが,通勤の途中でジッと空を見上げていたり,エプロンをつけてスリッパを履いてフライパンを持ったワニが,自宅の窓からジッと空を見上げているのよ」
「口を開いたまま?」「そう。固まったように。緑色の何十億っていうワニが,宇宙を見てるの。どう?」
「……じゃあ,飛んでるやつらもいそうだね?」
「ううん。彼等は飛べないのよ」
「ふうん」
綺麗な光景だと思った。綺麗で悲しい光景だ。
「……あなたも,消えないで済む方法が一つあるわ」
彼女は,伏し目がちにポツリと言った。
「住民になるの。ロゴスの塔五階には,住民登録室があるわ。そこでヘルメットを被るわけ。適性検査よ。合格したら住民になれるわ」
「少し疲れたかい?」
髪を触りながら,彼女は深い吐息をついた。
「……今日はとてもね」
「僕がいない間になにかあったの?」
彼女は伏し目がちに首を横に振った。
僕の手元で電詰のベルが鳴った。受話器を取る。受話器から聞こえてきたのは,僕の知らない男の声だった。妖精に替わる。彼女はとても深刻な顔をして受話器を受け取った。
「はい……」
電話磯のコードをずっと手繰っていったその先に,僕が目隠しされた世界が広がっている。一緒に暮らし始めて,彼女の電話回数の多さに僕はまず驚いた。電話の相手は誰なのか一度も尋ねたことはない。そういえば,最初に出会った時でさえ彼女は電話をかけていた。
「電話は男の人からよ。どう驚いた?」彼女は受話器を手で覆うと,こちらを向いて笑った。
「それで?」
僕の方をしばらく見詰めた後,彼女はまた受話器に向かった。
「分かったわ。それで,どう?……」
「どうしたんだい」横から横は声をかける。
「静かにして。あ,ごめんなさい。こちらの話……」
冷蔵庫のモーターが自動的に動き始め低いうなりを上げた。どこかで僕のギアが入る。僕の頭は,薄くてだだっ広いセロファンだ。そいつに煮沸した湯をかける。セロファンは収縮し,くしゃくしゃになる。ナニカ,ヘンダ――静かにしてよ――花瓶二差サレタ,しるくノ薔薇ガ,異様二赤イ――でも何人ぐらい? ――呼吸ガ,深クナッテ,クル。頭ノ中二,痒ミガ,走ル。ネエ,ナニカ,へンダヨ――分かったわ。持っていくものはそれだけでいいのね――ぶちぶちト,音ヲタテテ……眉間ガがガがガがガがガがガが,パ熱シイッ!
妖精が叫んだ。
電話磯が粉々にふき飛ぶ。
砕けた破片が,四方に散る。
身を堅くする妖精。
ダイアルが床に落ち,転がり,輪を描き,そして僕の足もとで震えながら止まった。
な,なに?
互いに,説明を求めて視線をまさぐる二人。
……あなたなのね。C5。あなたがやったのね。
◇
この出来事は次の三点において,ちょっとした話題となった。第一点は,僕の持つ力の特殊性について。もう一度やってみせてくれと,ミルの常連達はリクエストした。けれど残念ながら電話機はおろか,お札さえ割れなかった。第二点は,なぜそういった力が,その時発揮出来たのかということ。僕のジェラシーのなせる技というのがもっぱらの有力説だったが,その辺りははっきりしない。ただ好みだけがあって,愛という粘着物がない生活こそ魅力的なものなのだから。第三点は,その時彼女が話していた相手は誰だったのかということ。これも彼女一流のはぐらかしで掴めず,結局すべてはまた日常の中に埋没していった。
◇
ショータイムだ。
ゲイバーのフロアいっはいに,PAがロックビートを叩きつける。僕の視覚から,平衡感覚が崩される。ブルーのフラッシュが点滅し,痙攣する闇と闇の間にハイレグのギンラメ姿がコマ落としのフィルムよろしくダンスする。ダイエットされたその男の腰は細くしなやかに,強いブルーの視線を僕に突き刺しながら,挑発的に微笑む。先ほどまで僕に付いていたニューハーフだ。
「タロちゃーん!」
妖精がビートをとりながら,ステージのその男に向かって嬌声を上げる。
彼女の向う隣に付いたレナと呼ばれるごついニューハーフが,アイシャドウを引いた瞼を返しておどけてみせる。妖精が笑い転げる。毛細血管の錯綜した瞼の裏をみせたまま,レナが何かを僕に叫んだ。ダンスショーの大音響に紛れて,よく聞きとれない。何? と張り上げた自分の言葉もビートに飲まれてしまう。妖精が,僕の耳に手をあてる。
「あなた・とじて・目を! おなじ・こと・やったげ・るって!」
「そだよ・できた・ぼくも・むかし!」
僕らは喘ぐように怒鳴りあう。
レナがニヤつきながら,こちらに手を伸ばす。僕はウイスキーをあおり,目を開じる。とたんにレナは僕にキスをした。一同爆笑。ただし笑い声は音響にかき消されている。フラッシュの中,白い歯むき出しの顔が引き付っただけだ。
「病気をうつしてあげようか?」僕が言う。
は?と妖精が首を傾けた。
僕は披女へ,テディベアのようにキスをする。ソファーから冷たいフロアに僕らは崩れ落ち,テーブルの足を揺らした。グラスが倒れたのか,ウイスキーが僕らの顔に降り注ぎ,とても優しい気持ちになる。甘ずっばいコロンとウイスキーの香りに包まれ,僕らは異教徒のようにキスを続けた。
ダンプテイ,ハンプティ……たしか,あの卵は割れるんだったかな?
なぜか彼女の吐息はよく聞こえた。
「僕は外に二人ばかり妻を侍たせているのかもしれないよ」
「三人になるのはいや?」
「君には生活臭さなんて似合わない」
僕らは横たわったまま一センチの間隔で見つめあう。セピア色の写真を見つめるように,
彼女は僕の瞳を覗き込んだ。
「どうしたんだい?」
「あなたのことが分らない」
「僕自身にさえ分らない」
「あなたはまるで,ゾーンの霧よ」
「多重構造の夢を楽しみたいね」そう言ってみる。
しばらくして,彼女は答えを返した。
「でも,時は単層構造だわ。解る?」
「みんな現実ならば,人生は一枚岩のように重くなるよ。夢でいておくれ」
「夢は突然に覚めるものよ」
「どうしたんだい?」
「予感がするの」
「人生の三分の一は,夢と妖精のために空けておくさ」
「よく言うわねえ」とレナが……!
突然,爆音が襲った。
一斉に歯を鳴らせたグラス棚の中へ,レナは足をとられ激しく横転した。
「ああ……」レナの髪からしたたる鮮血。
上だ,爆発はこの近くだ!
妖精に目配せを送ると,僕は彼のもとへ走り寄った。
「大丈夫よ」手を真紅に染めながらレナが呻く。
「大丈夫じゃない。ヨウちゃん,タオルを」
駆寄る妖精にレナを任せると,僕は弾かれたように外へ出た。霧は焦げた匂いだ。
たちまち路地に,驚愕した靴音が満ちる。群衆がいななき始める。
「潰せ!」
ハンドマイクの割れた声がアーケードに響いた。
近くだ。
街が鳥肌立っている。
群衆は逃走する。それをかき分け,僕は爆発音の上がった方向へ疾走する。ただならぬ予感だ。
二十メートルほど先の北塔入口から黒煙が昇っていた。
ついに来るべきものがきた。人々の顔にそう書いてあった。
なにかは分らない。けれど,皆知っていたのだ。そして皆,まるで口裏を合せたかのように,そのことについて語らず,素振りに表わさず,その不吉な影が見え隠れするたびに冷笑を持って葬り去り,日々の勝者のごとくふるまっていたのだ。
巨大な火の手が上がった。
北塔の十二階,域内議会付近だ。
「豚め!逃げ惑うことしか知らぬ豚め!」
火の手の方から,ハンドマイクが狂ったようにわめいた。
みるみる北塔が火の海と化して来る。
中年の化粧の濃い女が,足を絡ませ僕のそばで叫びを上げて倒れた。人波を避け抱き起こす。
「バカヤロウー」髪を七色に染めた皮ジャンが,僕らを押し分けて怒鳴った。「なにやってんだ!どけ!」
塔から避難してきた群衆は,顔を引きつらせている。
痛い,痛いと,女は僕に哀願するように叫ぶ。付け睫の脇から,アイシャドゥの溶け出した黒い涙を滲ませ,彼女は僕の腕を引く。赤いハイヒールが,あらぬ方向を向いている。骨折だ。
サイレンが,アーケードを覆う。煙が広まる。霧が,黒く染まり始める。辺り一面が汚濁した河となる。ネオンが,炎のオレンジ色を浴びて粘性の高いメラつきを繰り返す。喧噪が渦巻く。ハンドマイクの声は,北塔を包む炎の重なりによって掻き消されていった。
◇
そして火の手は,夜の帳に一層勢いを増した。折からの強風に煽られ,北塔の上部は手のつけられぬ惨状となりつつあった。
「残念なことです」
とイワサキは言った。
骨折した女を救急局に送り届けた後,現場に引き返すと,マーゼンのイワサキに出くわした。いつかミルでタロットを受けていた,ヘリンボーンのオーバーコートの男だ。機敏に部下へ指示を出している彼に声をかけると,そう唸った。「狂気の沙汰だ。ご協力を」
僕らは消火活動にあたった。まだ何千という人々が階上に逃げ場を失い,止どまっている。数えきれぬ野次馬とマスコミが人の不幸に押し寄せ,消化活動を決定的にマヒさせた。整理しようと当局はメガホンを掴んだが,野次罵は次から次に降って沸いたかのように現れた。作業はミルクに落ちた縄のように空転し,議場は大小のオレンジ球となって階下に降り注ぎ,階上の人々の悲鳴を連想させた。,議場は大小のオレンジ球となって階下に降り注ぎ,階上の人々の悲鳴を連想させた。
決断は下された。
北塔の五階に爆薬がセットされる。
アーケード全域を揺るがす大音響が上がると同時に,人々は息を飲み,水をうったように静まりかえった。
不用意な花嫁のように北塔は一瞬愕然とゆらぎ,その後きらびやかな火の粉を霧と黒煙の間に間に飛び交せながら,緩かにアーケードの外に広がる沼にしなだれ倒れていった。
アーケード全域は停電となり,巨大な暗黒が翼を降ろした。
火は,困惑した明け方の訪れと共に収まり,人々は十八時開ぶりの食事を口にし,ある者は眼り,またある者は飛び交う噂に口き耳を立てた。アーケードの通りは焼け出された人々で埋まった。煙で痛めた喉から咳が続き,そこかしこに着の身着のままの男と女が膝を抱え,あるいは横たわっていた。担ぎ込まれた坦架は通路にあふれだし,呻き声が満ちた。蛋白質の焦げた臭いをさせながら息を引きとって行く人々。
「マーゼンに棒ぐ」アーケード7セクションのトイレ壁面に発見された赤いスプレーの大きな落書きはそう告げていた。マスコミは相変わらず,口の軽い老婆のように無責任な記事を書き殴っていた。
混沌の中を人々は彿徊し続けた。角々に黄色いロープが張られ,立入禁止区域が設定された。火の燻りが去り,それに変って糞尿の臭いと,虫の飛ぶような低く唸るわだかまりが充満し始めた。ピリピリとした酸っぱい緊張が,わずかずつアーケードに漂い始めていた。
暴動は八階スタジアム近くから起こった。堰を切ったようにアーケードのあちこちで連鎖が起こった。きらめく店舗や公的磯関が対象として攻撃を受ける。不確かな噂の上で群衆が狂舞を開始した。ショーウィンドゥは,けたたましい音を立ててシャッターを降ろそうとし,興奮した人々の心に油を注ぎ逆上させた。方々で巨大なガラスの割れ散る音や,悲鳴が上がった。非常ベルが鳴り響き,警備員らが血まつりにされる。やけばちの目は白く剥けて獲物を求めた。カーニバルは変調子の残酷なビートに乗った。発熱はまたたく間に一般群衆を飲み,殴打は殴打を生み,破壊は狂気を盛り上げた。
戒厳令が敷かれる。ジュラルミンを鈍く光らせた機動部隊が制圧に乗り出す。マスクに顔を隠した彼等はマシンのように行動をとる。半日前まで消火活動に使用された消火栓が抜かれる。群衆に,凄まじい勢いで凍てついた水が放射される。正面からまともにうけ,もんどりうつ人波。アーケードのスピーカーは声をからせて,平生を保つように人々に呼びかけ続けていた。
 ホームページは欲しいけれど、高いのは勘弁してほしい。
ホームページは欲しいけれど、高いのは勘弁してほしい。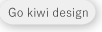 クリック!
クリック! トップ
トップ オススメ
オススメ 記事一覧
記事一覧 掲示板
掲示板 長崎マニアックガイド
長崎マニアックガイド 長崎の酒場
長崎の酒場 長崎を歩く
長崎を歩く 長崎キャンプ場
長崎キャンプ場 長崎インターネットラジオ
長崎インターネットラジオ 私の手作りキャンプ場
私の手作りキャンプ場 私の家づくり
私の家づくり デザイン
デザイン 絵
絵 音楽
音楽 小説
小説 メール
メール  リンク
リンク


