銅座界隈 ブルースを聴け
代治朗氏は製造業オーナーだ。豊かな緑の中に男の隠れ家を持ち、設えた大画面ホームシアターを観たり、囲炉裏端の料理を味わったりと、悠々自適の生活を楽しんでいる。
あるとき私が1枚の写真をサイトにアップした。銅座の路地裏の写真だ。
これをきっかけに、代治朗氏の原風景が語られることとなった。戦後復興期の都市生活。それは語り継がれるべき昭和の風景だった。
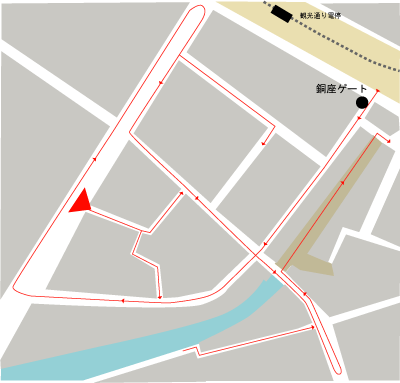
今回の彷徨は赤い矢印地点から開始する。
「60年前と比べたら小奇麗になっているけれど、ここは私が生まれた場所です。
『さつき』と『七福ビル』の間付近で産婆 村上テイさんに取り上げられたのです。体重は760匁とへその緒を納めた小さな木箱の裏に書いてあります。懐かしい路地です」

「私の生家は、二階建ての借家で、格子戸の引き戸を開けると、先詰から右上に上る階段がありました。二階は一間で寝室として使い、眼下の路地の共同水道で、洗濯をする若い女の胸や足首を眺めていました。夏の暑い盛り、汗に濡れた色っぽい女の肌を見詰めていたのです。
屋内には水道がありませんでした。階下床は黒光りしたタタキで、出入り口を入って右に小さな流しがありましたが、煮炊きは戸外に七輪を出して済ませ、かまどはなかったように記憶してます。左に土間より一段高い腰掛程度の縁があり、縁より一歩上がると食事をする居間でした」

「この中央の溝にはまって怪我をしたり、バーの前の盛塩を蹴飛ばして遊んだり、薄いドレスにカーデガンを羽織り、煙草を吸ってるお姉さんに頭をなでられたり、東館というエロ映画館のポスターに見いったり、その路地の突き当たりにあった『白馬車』という看板など次から次に思い出せます。
路地中央のドブ溝は、当時、蓋が木製でしたが、道自体は当時そのままです。匂いも当時とさほど変わらないでしょう」

「私が、小学一年生、昭和33年の春、博打で儲けたのであろう親父が、当時、銅座でも珍しいテレビを買ったのです。その居間の一角に鎮座ましましたテレビは、バーでも置いている処が珍しい時代でしたから、毎夜、近所の住人が「こんばんは、見せてください」と数人尋ねてきていました。私たちが食事している最中にです。居間は障子戸で仕切ることも出来ましたが、いつも開け放しで、今思うに両親はそれを断りきれないという迷惑顔ではなく、それでいて自慢げでもなかったように思います。誰もが貧乏な時代、互助精神なんて考えを持ち合わせていなくても、当然のごとく嫌悪感なんて感じなかったのでしょう。今では、考えられない光景です。
上がり口の縁に腰掛けた彼らに、お茶を出すわけでもなく、私たちは黙々と食事し、テレビを一緒に見ていました。
毎夜来る一人の青年がいました。煤け汚れた顔に似つかわしくない大きな目をし、いつもニコニコした青年でした。ある夜、親父が酔って帰り、青年に悪態をついたのでしょう。その時の青年の悲しげな目が、脳裏に焼きついています」

染み入るブルースだ。
歴史は勝者の成功談として描かれることが多い。それが国家レベルのものであれ、一成功者のものであれである。代治朗氏の吐露とも言うべき、実直な戦後都市生活者の話は貴重である。生活感のないドラマが跋扈するようになった今日、いよいよこうした生活の描写は影を潜めつつある。
もしかしたら、それが現代日本の弱みなのかもしれない。生きる力はこうした生活のリアリティによってしか裏打ちされない。現在からみると抜き差しならない苦労を、戦後立ち上げ期の世代は通り抜けてきた。周囲もまた同様の中にあることによって可能なことだったのかもしれない。それはとりもなおさず国家の成長であった。
銅座や思案橋界隈を描くこと、スタイリッシュな街並みの普段見えづらい深奥を描き出し残すことの大切さを再認させられる。
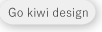 クリック!
クリック! 生きてることを楽しもう。座右の銘は荘子の「逍遙遊」。長崎県。
生きてることを楽しもう。座右の銘は荘子の「逍遙遊」。長崎県。

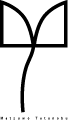
 トップ
トップ オススメ
オススメ 記事一覧
記事一覧 掲示板
掲示板 長崎マニアックガイド
長崎マニアックガイド 長崎の酒場
長崎の酒場 長崎を歩く
長崎を歩く 長崎キャンプ場
長崎キャンプ場 長崎インターネットラジオ
長崎インターネットラジオ 私の手作りキャンプ場
私の手作りキャンプ場 私の家づくり
私の家づくり デザイン
デザイン 絵
絵 音楽
音楽 小説
小説 メール
メール リンク
リンク