第二段
戦雲編
【 一 】
「速魚川」の坪庭の片隅には、昔から一個の錆びた鉄の砲弾が置いてある。主人は亡き父から「西南の役」で使用された大砲の弾であると聞いていた。初代・信平がこの地・島原に来たのも西南の役の年、即ち明治十年である。
主人は、父が言った「西南の役の砲弾」の真偽や詳細を調べたくなり、市内在住の郷土史家である本田宗也氏に調査を依頼したのだった。本田氏は砲弾を手に持ち、しばし凝視した後「4、5日これを貸してくれませんか?」と言ってその砲弾を持ち帰った。
数日後、その砲弾を持参した本田氏は、「結論から言うと、まさしく西南の役に使用された砲弾です」と断言した。
-
「アームストロング砲の砲弾である。英国で1855年に開発され、その後の近代後装砲の先駆けとなったものである。
日本で最初に使用されたのは、1863年(文久三年)の薩英戦争の時で、薩摩の小型四斤山砲を圧倒的に凌駕した。薩摩兵は落ちた砲弾を見て驚いた。自軍の砲弾は旧来の円弾であるが、英軍のそれは先が尖った円筒形の弾であった。のちに言う尖長弾である。
射程距離は円弾が千メートルに対し、なんと四千メートル。その上、砲弾の周囲十二箇所に鉛が詰められており、着弾すると内部の火薬が爆発して鉛の弾が周辺に飛び散り、人馬への被害を甚大にする。 薩摩藩は驚愕した。
戦い方が一新したことを認識して、すぐに英国に大金を払いアームストロング砲を輸入した。その当時、薩摩はすでに製鉄所を所有していた。今で言う集成館工場群の中にあった。輸入した大砲を徹底的に分析し、わずか数年後にはアームストロング砲を創り上げた。幕府はまだ旧式大砲しか持たず、その後の鳥羽伏見、上野彰義隊も薩摩、鍋島軍のアームストロング砲の威力に為すすべなく大敗を喫する」
初代・信平は何故、西南の役の砲弾を島原に持ち帰ったのか?
【 二 】
その後の信平の足取りを追おう。
小倉で連絡船を下船した信平は長崎街道に入った。
長崎街道は小倉長崎間の五十四里で、宿場が五十二箇所で繋がれていた。幕末、長崎街道は重要な役割を果たした。文政九年(1823年)、シーボルトもオランダ使節参府随員としてこの街道を通り、長崎で海軍術を学んだ勝海舟、海援隊を設立した坂本竜馬や初代総理大臣・伊藤博文など、長崎街道はこれら維新の志士達の熱い思いを見守ってきた。
筑前原田宿を過ぎ、田代宿からは佐賀路である。
猪原家にある資料、嶋原藩士・水谷勝兼記するところの「御徒場附」(文化十三年・1831年)によると、佐賀路の宿は、田代から嬉野までの十三宿である。
佐賀路に入ると、筑後川で育まれた肥沃な平野が延々と広がり、今は刈り入れも済んだ広大な田の連らなりが果てしなく続く。有明の海から筑後川へと渡ってくる風が、遮る山々が全くないのでまともに旅人に襲いかかる。秋の風は、ここ九州でもすでに冷たくなっていた。
信平の旅姿は、菅傘を被り、急な風雨の対策にマント状の「引き回し」と呼ばれるものを羽織り、脚絆を足に巻き、草鞋を履いている。すこし大きめの振り分け荷物に《青龍の掛け軸》の木箱を背中に渡していた。江戸年間の旅人姿と変わらない。
折からの強風で信平の合羽の裾は舞い上がっていた。しかし委細かまわず先に進む信平であった。
【 三 】
佐賀路は田畑を通す一本道である。行き交う人ももう居ない。秋のの日足は早い。辺りは暗闇に包まれようとしていた。卒然と雨までも降ってきた。
さすがに信平も足を止め、雨宿り先はないか辺りをうかがった、が適当な所はなさそうである。また半丁程歩いた。と、小さな祠らしきものが薄闇の中に浮かんで見えた。幟が二棹、祠の左右に立っている。具合がいいことに軒が出ていて雨が防げそうだ。祠というより小さくても立派な社であった。信平は入り口の木の階段に腰を落ちつけた。
雨の音しか聞こえてこない。少し安堵した信平に睡魔が襲ってきた。
どれぐらい眠ったのだろうか? 信平はかすかな人の気配でフッと眼が覚めた。と、その刹那、腹に当て身を食い、気絶した。
気がつくと、知らない家の座敷牢にころがされていた。身の回りのものは全て奪われている。あの《青龍の掛け軸》もない。
「お~い、誰か!」と、信平は廊下と部屋を遮断している太い木の格子を掴み、外に向け大声で叫んだ。二度、三度繰り返した。すると奥から人が来る足音がした。
「これ、大声を出すでない!」と制しながら四十がらみの男がやって来た。
信平はその男に向かって、「一体どういうことだ? 今すぐここから出せ!」と抗議した。
「そうは、いかぬ」
「何故だっ、何ゆえあって俺を押し込める!」
「訳はある」
「どんな理由か?」
「まぁまぁ、今から詮議が始まる」
「詮議?」
「我らがお頭様が見えるから、其処で今しばらく待っておれ」と言うとまた奥へ戻って行った。
半刻後、今度は五人の人間がやって来た。なんとその中の一人は女だった。
「これ、起きろ」
「何だ」
「こちらの方が、お頭様だ」と女の方に目配せした。
女は浅黄色の内掛けを纏い、どう見ても旅姿であった。年のころ三十四、五、柔和な瞳をしていて、悪党には見えない。
五十がらみの男が主に信平に質問した。出身地、旅の目的、行き先、等である。信平は必死になって、今までの経緯を説明した。
しかし不当な拘束をした一味の方に非はあるとの思いに駆られ、
「何故こんな非道なことをする、俺は納得がいかん」と言うと、頭目である女が初めて口を開いた。
「貴方の主張は分かりました」
「ならば出してくれ」
「それは、まだ」
「何故だ、分かったと言ったではないか!」
「言い分が分かったと申したまでで、貴方への疑いが晴れたわけではありません」
「何の疑いか」
「政府の密偵ではないか、という」
「えっ! 密偵! ち、違う!」
「貴方は我等と、ある所へ同道して、我等のお使えする方の審判を受けなければなりませぬ」
「その人はだれだ!」
「今は言えませぬ」と微笑みながら女は言った。
「明日から我々と旅立ってください」
「何処へだ」
「薩摩です」
「さ つ ま?」
「そうです」
「行かぬっ!」
「ならば、ここで死んでもらいます」と、眉を引き締めながら女は静かに言った。
信平は、おめおめと得体の知れない一味の脅しに服従する屈辱が耐えられなかった。しかし、重大な任務の遂行の途中で死ぬことは絶対に出来ぬ、と煩悶しながら激しく葛藤した。が、やはり生き抜いてなんとしても任務を遂行する、と覚悟を決めた。
「分かった……薩摩へ行こう」
【 四 】
翌朝のまだ暗い内に一行は旅発った。《青龍の掛け軸》と黄金は一味の誰かが持っている様子はなかった。信平はわが身の不覚を悔やんだが、今は囚われの身、いかんともしがたかった。
一行は有明海沿いに熊本を経て、日奈久、水俣を通り薩摩の入り口である出水に到着した。七日間の旅程であった。途中、脱出の機会はあったが、薩摩で一味の大将とやらにわが身の疑いを晴らし、青龍の掛け軸を取り返すまではどうしても薩摩に行かねばならなかった。
出水に一泊した。宿屋で信平は一部屋与えられたが外の廊下には男が二人ずつ交代で見張っていた。
寝支度を整えようとした時、障子が開き女が入って来た。
「明日ここに、或る方が尋ねてきます」
「どなたですか?」
「篠原国幹さんです」
「え? あの近衛大隊長の?……その方が尋問するのですね?」
「はい」
「……分かりました」
「私はここまで来る道中、貴方をずっと見ていて、少しだけ疑いが晴れました」
「そうですか」
「はい、貴方の挙動には少しの曇りもない」
「ですから、初めから政府の密偵ではないと言っておるのです」
女は艶然と微笑みながら出て行った。
翌朝、早い時間帯に篠原国幹はやって来た。
「篠原さんが参られた」
「分かりました」と信平は居住まいを正した。
「篠原です」
「猪原信平です」
「国幹です。こん度はお疲れ様でごわした」
篠原は頬骨が高く秀で、眼光鋭く、背筋が伸びた偉丈夫の男であった。
「元武士として疑いを晴らすまでは、と思いまして」
「おはんの事は、島さんの未亡人にいろいろ聞きもした」
「あの方は、島といわれるのですか?」
「おんしの疑いは、もう晴れもした」
「えっ、詮議があるのでは?」
「もう、よかでっしょ」
「もういい、といわれると?」
「詮議なし、という意味でごわす」
「詮議なし、ですか?」
「ちょっとでん、疑いばぁ持っちょたら、直ぐ斬り申した」
「……」
「まっこと、信平どんにはご迷惑ばかけもした。許してつかぁさい」と大小を差し出し平伏した。
「もう気になさいますな。私も疑いが晴れてうれしいのです」
「まぁ 二、三日、旅の疲れ休めに鹿児島ばぁ、見ていってください。こん度のお詫びに、おいが案内ばしもそう」と言うと深々と一礼して帰って行った。
そのあと《青龍の掛け軸》と黄金を渡された信平は、やっと安心することができた。それにしても後の薩摩軍一番隊・指揮長となる篠原国幹との初めての出会いは、信平にとって一陣の春風にも似た爽やかなものだった。
【 五 】
翌朝、信平は鹿児島・吉野町の工場群にいた。
「篠原さん、ここではどんなものを作っているのですか?」
「反射炉を中心に、大砲、火薬、陶器、ガラスの器などです」
「反射炉とはどういうものですか?」
「あの高い煙突のある建物でごわす」
見上げると、二十mもあろうかと思える二基の煙突から、もうもうたる煤煙が空へ吹き上がっていた。信平が見たこともない光景であった。
「鉄の原料に直接火を当てて溶かすと不純物が混じり申す。周りの煉瓦に火を当てて、その反射熱で原料ば溶かす。そいで反射炉というそうです」
朝廷は「黒船来航」でその近代兵器、それも鉄の威力に腰をぬかし、各藩に「お寺の梵鐘を壊して鉄砲を作るでおじゃる」と朝令を出した。近代製鉄の先駆けは「鍋島」であったが、「反射炉」製鉄法はここ薩摩が日本初であった。
信平は青空に黒々と二筋の黒煙を描く反射炉の双連2基の煉瓦の壮大な工場を見上げながら、「鉄の時代の到来」を強く意識した。自分の拠って立つ生業も、この「鉄」に関わりのあるものを、と確信しはじめた。
【 六 】
次に案内されたのは鶴丸城内の「私学校」であった。
「西郷どんの提唱で作りもした」
「西郷先生はこちらにいらっしゃるのですか?」
「六年の秋から、薩摩に帰られた。おいどんも翌年、後を追って来もした」
「で、学校では何を教えているのですか?」
「大砲術、鉄砲術、兵士の教養の三点です」
正に兵学校ではないかと信平は訝しがった。維新以来、軍隊は政府の専権行為でなかったのか? なぜ、薩摩に兵学校があるのか?
これはもしや……と自問していると、突然、「きえ~っ」「ちぇいすとーっ」と甲高く気合のこもった声がした。学校の前庭で、撃剣の稽古を生徒達が行っていた。
「示現流といいます」と篠原は目を細めながら言った。立木の前に縦列し一人づつ打ち込んで行く。
これが、天下に名高い示現流か、と信平はしばし足をとめ見いった。一の太刀を疑わず、二の太刀は負け。刀は敵を破るものにして自己の防御に非ず、と示現流は教える。凄まじい必殺剣である。
次に「こちらに どうぞ」と促されていくと、教室で生徒が行儀よく書見台を並べ書物を音読していた。
-
「道は天地自然の物にして、人はこれを行うものなれば、天を敬するを目的となす。天は我も同一に愛し給うゆえ、我を愛する心を持って人を愛する也」
「それは、どんな意味でしょうか?」
「会うて、話されたら分かりもそう」
「えっ! 会うって?」
「はい、あん教室の別室で、おはんが来るのを待っちょられます」
急な成り行きに、信平は戸惑いの連続であった。
【 七 】
「しのはら です。いのはらさんば、おつれもうした」
「うむ、入ったんせ」とやや野太い声がした。部屋へ通された。
西郷隆盛は巨漢であった。眉が太く、瞳も太かった。なにもかも大きい人である。幕末から維新にかけて西郷と共に日本の歴史を動かした人物達の西郷評を紹介する。
-
哲学者 阿部次郎
「私が子供時代に最も直接的に、濃厚に、現実的に、感化力が多かったものは何であるか。それは西郷隆盛である」
藩主 島津斉彬公
「西郷一人は薩国貴重の大宝なり」
坂本竜馬
「西郷はつり鐘のような男だ 少しく叩けば少しく響き、大きく叩けば大きく響く。もしばかなら大きなばかで、利口なら大きな利口だろう」
中岡慎太郎
「当時洛西の人物を論じ申し候えば、薩藩に西郷吉之助あり」
勝海舟
「おれは、きょうまで西郷ほどの人物を二人とみたことがない。どうしても西郷は大きい。厚かましくも元勲などとすましているヤツと、とても比べようがない。西郷との談判はそりゃ きつかったよ。しかし西郷はおれのことを信用して、『いろいろむつかしい議論もありましょうが、私が一身にかけてお引き受けします』の西郷に一言で、江戸百万の人の命が救われた」
「いえ、今は疑いも晴れました故、気になさらないでください」
それを聞くと西郷は信平の方ににじり寄ってきた。正面からじっと信平の眼を見つめ、その大きな手で信平の両手を取り、しっかりと包み込んだ。
「許してたもんせ」
あの幕府も恐れた大西郷が自分ごとき軽輩に優しく接してくれている、と信平は感動した。温かい。とにかく温かい手であった。
「信平どん」
「はい」
「こいから、おいどんの本心ばぁ、お話し申す」と両手を離し信平を見つめた。
「青龍の掛け軸ば見させて貰いもした」
「そうですか」
「信平どん、是非、あん青龍さんば、おいどんの側に置かせて欲しか」
「えっ……そ、それはできませぬ」
「そこをまげて、お願いもうす」と両手をついた。横を見ると篠原も頭を下げている。
「どう言われても、あの掛け軸だけはお渡しする訳には……」
「信平どん」
「はい」
「おいどんは、政府に尋問の廉これあり、で立ち申す」
「えっ! やはり兵を挙げるのですか?」
「まだ、数人にしか言うちょらんが」
「……そうですか」と、信平は重大な決意を聞かされ戸惑った。
「東上するに当たり、是非【青龍】を側に置いときたかとでごわす」
「……」
「おいどんは死んでんいっこうにかまわん。じゃっどん、有為なる若っかもんの事ば思う時、青龍のご加護ば頂きたか一心でごわす」と、西郷は再びにじり寄り信平の両手を強く握り締めた。少し瞳が潤るんでいた。
信平は、もう拒否できない心境になりつつあった。どうみても兵員数、火力とも政府軍とは比較にならない。それなのに敢えて異議申し立てで兵を挙げる西郷に、武人の魂を、それも最後のサムライの存在を見た。
「……分かりました」
「誠でごわんか」
「はい。でも西郷先生、この猪原も参戦させて下さい。それが条件です」
「誠よかとですか、信平どん」
「はい……師も許してくれるでしょう」
今度は西郷が大きな身体を折り曲げ平伏した。
【 八 】
翌明治十年二月十五日、1万3千の薩摩軍は進撃を開始した。「信平どんはおいどんの側に」とのことで本営付護衛隊に入った。一番大隊長は篠原国幹である。
信平は野営のつれづれに西郷に呼ばれ会話する機会を得た。
「先生は武士道のなんたるかをどうお考えですか?」
「いろいろ意見はありましょうが、おいどんの思うところは、人の道を重んずるが故に、悪を憎んで断固としてこれを封ずる、ということです」
薩摩軍の当面の狙いは熊本城の占拠であった。政府軍は名将・谷干城の下、約4千の兵力をもって守城することになった。最終的に政府軍5万8千、薩摩軍3万の戦いが熊本城攻防で事実上始ったのである。
二月二十日よりの薩摩軍の攻城戦はことごとく失敗に終わり、二十四日以降は両軍対峙状態に陥った。各地で小競り合いがはじまったが、薩摩軍の少ない大砲と装備の劣った銃では劣勢になるのは火を見るより明らかであった。
【 九 】
西郷は銃弾の飛んでくる距離まで進み、馬を止め、そして不動の状態になる。自殺行為に近かったが不思議と弾が当たらない。夕日を背に受け、微動だにせぬ馬上の西郷は、まさしく薩摩軍の象徴であった。
「先生、前に行かれるのは止めてください」と信平が言うと、「おいどんには、当たりもうさん。《青龍さん》が側に居もうすで」と笑っていた。
三月から一ヶ月、田原坂、吉次峠の激戦が行われた。四日、吉次本道の決戦で篠原国幹が戦死した。篠原は外套を羽織り、銀装刀を提げ、無言で、身振りだけで先頭に立ち指揮した。この時の目を引く赤裏の外套が目印となって狙撃された。進むを知り、退くを知らない男であった。享年四十二歳。
《ふたつなき道に その身をふりすてて みがき尽くせ うみの子ら》を家族に残して出陣した。
「篠どんこそが、誠の武人よ」と西郷は信平に言った。
田原坂の激戦が終了した時、薩摩軍は8千になっていた。先立つ三月十八日、薩摩軍の背後を衝く官軍別働隊が八代に上陸した時点で事実上雌雄は決していた。三月二十五日、後退した薩摩軍は人吉付近まで来ていた。残り3千までになっていた。
その夜、西郷は信平を呼んだ。
「信平どん、ここいらでよかろう」
「……と言われますと?」
「おはんは、よう戦うてくれもした。じゃっどん、もう、戻ってたもんせ。おはんをここで死なすっ訳にはいかん。おいどんは戦い抜いて武士の一分ばぁ守りもうす。信平どんは生き抜いて武士の魂ば通してたもんせ」
そう語りながら、西郷は信平の眼をしばし見つめて、ふっと微笑み、本営に引き返して行った。
【 十 】
その年の秋、信平は長崎にいて西郷自刃を聞いた。その夜、信平は男泣きに泣いた。西郷の姿が、篠原の姿が、ぼうぼうたる火炎が、爆裂音が、脳裏に現れては消え、消えては現れてきた。
その後、《朝敵》と言われた西郷が名誉を回復したのは、十五年後の明治二十五年であった。日蓮宗・不受不施派の命運と深く通じるものがある。
明治十年九月二十四日午前4時、城山にて、お付きの別府晋介に「晋どん、もうここでよかろ」
と言い、座を正し、遥かに東方を拝礼し静かに目を閉じ、褌を両手で押し下げ、右手に軍刀を持ち、
左手で下腹を揉み柔げた。
刀を前に廻し、腰を持ち上げ、下半身が刀先にかかるようにして、身体を押し込んだ。血が流れ出した。「晋どん……」とかすれた声で言った。別府は「ごめんなったもんし!」と叫ぶや一刀のもとに西郷の首を切り落とした。
西郷隆盛、享年五十一歳。西郷は死んだ。
しかし、天翔ける《青龍》は、西郷と信平の思いをすでに果たしていた。
先立つ、五月十四日 大久保利通は宮中に赴く途中、刺客に襲われ死亡。五月二十六日 木戸孝允は京都で病死。西郷を追い詰めた新政府の重鎮二人は、いずれも非業の死を遂げていたのだった。
英雄の最期を詠う 西道仙・作 「城山」
孤軍奮闘 囲を破りて還る
一百の里程 壘壁の間
吾が剣は 既にくだけ 吾が馬はたおる
秋風 骨を埋む 故郷の山


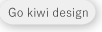 クリック!
クリック!



 トップ
トップ