第四段
普賢岳鎮撫編
【 一 】
-
私は、信平さまのお在します方角に向かって「信平さま~」と、大きな声でお名を呼びました。波涛が繰り返し繰り返し小舟に打ち寄せ、私の身体は翻弄されました。「さよ~、さよ~」と波の轟音の中から亡き母の声が聞こえてくるようで、涙があとからあとから流れ出てきました。
「ははさま~っ、ははさま~っ」と、塩辛い喉の奥を震わせながら出来る限りの大声で呼びました。
-
(歌) 信じる道もあらざりき 人恋ふる 深き想いは千年も変わらじ
信平さまのお側に仕え、私の生涯をお捧げしたく候らえば、の一念で必死で櫓を漕いだのです。
小夜はある夕暮れ、日見峠を越え、矢上の海岸に寄り付いていた小舟に乗り込み、信平が先行している肥前嶋原を目指した。憑かれたように櫓を漕いでいた。
陽が落ちて辺りが暗くなってきた。小夜は念じた。
-
夜が来て周りが暗くなっても
月の光だけしか見えなくても
私はちっとも怖くないわ
あなたの側に行けるだけで
私は強くなれる
だから、貴方の側にいたい
いつも、貴方の側にいたい
【 二 】
一方、信平は「普賢」の山中深くに入り込んでいた。行基が開き、弘法大師が鎮撫祈願した「火の山」を、自らも師・龍雲の厳命のもと、今までの修行の限りを尽くし、鎮撫する為にである。姿は修験僧である。しかし、《青龍の掛軸》の木箱だけは背負っていた。
古来より日本にあった山岳信仰が、外来の密教、道教、儒教などと結びつき、平安時代の末に成立した修験道。信平もまた、師より「不受不施派」の法華経とは別にこの道も深く教わっていたのだ。御禁制を生き抜く術として体得したのである。
修験道の目指すところは山岳修行による超自然の獲得と、その力を用いた呪術的宗教の実践である。この修験道もまた、こののち、政府より禁止令が出る。
信平は有明の海が一望に見渡せる尾根にいた。朝日が阿蘇の外輪から湧いて出た。明々と昇る朝日に向かい錫杖を振り、大日如来真言を唱え、般若心経を唱え、「万民平和 ナモフカシギコウ、無病息災 ホウゾウボサツインニジ、五穀豊穣 ザイセイジザイ オウブッショウ……(仏説阿弥陀経)」と唱える。
その後、坂を上り、草原の道に分け入り、杉木立に入り、目的としていた行基上人の開基した温泉権現へ向かった。温泉権現は、尾根伝いの道の行き止りに巨大な巖があり、その上に社が乗っていた。信平は巖を這い登り、巌の裂け目から腹ばいになり、チロチロと流れ出る神水で口を濯ぎ呪文を唱えた。
儀式の間、錫杖の音は絶えることはない。出生灌頂を終えた行者は霊験を得て、衆生斎度の役目を担う一員となる。
儀式を終えた信平は、「六根清浄、懺悔、懺悔! 南無温泉権現、南無温泉権現」と繰り返しながら歩き始めた。
【 三 】
次に向かったのは、弘法大師が百万遍の経を唱えた洞窟である。
里の寺に尋ねると「そりゃ、常人では無理です。おやめになったほうが」と引き止めたが、「言い伝えられた話ですから、明確な場所とはいえません」と断りながら、概略を教えてくれた。
信平は、その洞窟を目指し山中深く分け入ったが、とうとう迷い込んでしまい、途方に暮れた。
と、その時、背中の《青龍の掛け軸》の木箱が「コトリ」と揺れた。信平はハタと歩みを止めた。すると「我に従え」という声がはっきり聞こえた。耳を疑い、周りをみたが勿論誰も居ない。
しばし立ち止まっていると、今度は「弓手(左手)に回れ」と声がした。信平は従った。しかしその方角へ行くと、道が消え、足元からほぼ垂直に見えるほどの絶壁があった。
信平はさすがに躊躇した。再び、そして今度は力強く「降りろ」と声が聞こえた。その声に押されるようにフラフラと信平は絶壁に取り付き、降り始めた。一m進むのが十mにも思えた。恐怖で手足が振るえ、その度に絶壁の砂が、数百m下の谷に舞い落ちて行く。
三十mぐらい降りたところで、幅五十センチぐらいの踊り場のような岩場があった。信平はようやく一息つけるとやや安堵した。その岩場につくと、なんとそこから横穴が覗いていた。ひと一人がやっと入れるぐらいのものだった。
「これだ、大師さまが祈願された洞窟は」と確信した。もう天の声はしなかった。
信平は横穴に頭から入り込んだ。匍匐で三十mくらい進むと、先のほうにかすかに灯りが見えてきた。進むに連れて次第に明るさが増した。尚も行くと、急に視界が開けたのだった。
信じられない光景が目の前に出現した。そこには広大な空間が広がっていたのである。広さ200畳は優にあり、天井まで4mはあった。その天井の中央辺りに空に通じる穴が穿たれてあり、一条の光が差し込み、洞内を明るくしていた。
信平は感慨深く、しばし佇んでいたが、ややあって奥へと進むと、壁の前に小さい石積みがあった。おそらく大師が祈願をされた場所であろう、と信平はその前に正座し手を合わせた。その後、略式の護摩を焚き、「オン サンマカ サトバン(普賢菩薩)、オン バザラ ダトバン(大日如来)、ノウマク サンマンダ バザラ ダンカン(不動明王)……」と、真言を唱え始めた。
大師は百万遍唱えたというが、信平は数を数える余裕もなく一心不乱に唱えたのだった。
幾度、陽が没し昇っただろうか。信平は呪文を唱えながら次第に意識が遠のいていき、その場にくずれ落ちるように倒れ込んでいった。
【 四 】
どれくらい経ったのだろうか。
「お師匠さま、お師匠さま」と、肩を誰かに揺すられて目が覚めた。
「……貴方がたは?」
二人の男が信平の前に正座していた。
「降伏と申します」
「敬愛と申します」
「何故ここに?」
「我が父より、この秋にはお前の師となるべきお方が、このお洞に参られる故、何はさておき助力せよ、と命を受けました」と降伏が云うと、「私も同様です」と敬愛も云った。
「不受不施の方々か?」
「はい、そうでございます」と声を揃えて言った。
「その方は普賢の鎮撫と、半島における我が派の本拠となるべき御寺の建立の為に、備前岡山から来られる、とも父は申しました」
「分かりました。共に力を合わせましょう」と信平は二人の手を取り、目を合わせた。
「はい」と降伏、敬愛もまた強く手に力を入れた。
「ところで、お二人に問うが、備前のわが師・龍雲から、富士と普賢とは火の道の理がある、と聞いたが、それはどのようなものなのですか?」
まず敬愛が応えた。
「わが家は、代々この山の麓に住まいし者ですが、祖父から聞きましたところ、富士と普賢の両山は、わが国における明と暗、はたまた陽と陰の関係なのだそうです」
「陽と陰の関係?」
「私の祖父が語るには、そもそもわが邦は、その国土に神霊を認め、一島四面の面ごとに、神霊が存在するものと信じられていたそうです。それが国土鎮護の神として祀られるにいたったのです」
「その沢山の神々はそれぞれ独立していたのですか?」
「それぞれの主旨はありましたが、大本の系統が厳然と存在していたのです」
「その大本とは、どのような?」
「伊勢と出雲です」
「伊勢と出雲?」
「伊勢がアマテラスで正統とされ、のちの大和朝、出雲がスサノウで異端とされました」
「で、この普賢のある肥前はどちらでしょうか?」
「もちろん、出雲です」
「富士と普賢、陽と陰、伊勢と出雲、アマテラスとスサノオ……ウ~ム……」
信平は、師・龍雲より命じられた普賢の鎮撫が、只ならぬ深い意味を孕んでいることに、戦慄を覚えたのだった。
【 五 】
敬愛が祖父から聞いた話は、さらに続く。
そもそも、肥前、肥後の「肥」は「火山」の「火」を用いていた。その「火」とは、普賢岳を意味し、この火の山を基準にして「火前」「火後」と呼んだ。しかし、ある時代から隠語となり、現在の肥前、肥後と当て字を使うようになったのだ。
普賢岳を【陰】とせざるをえない歴史的な深い理由があった。
肥前を含む九州地方は、出雲王朝に属し、従ってスサノオ命の統べり給うた、海原の国、または根の国の範囲なのである。
肥の最高峰である雲仙岳の普賢、国見、妙見の三峰はまさしく出雲派の霊山であった。対する富士は、伊勢派の最高霊山である。
本邦史上の始まりから出雲朝と大和朝は、対立関係の図式を呈してきた。
神話の砌、出雲が大和に戦いを挑んだ。所謂「倭国大乱」である。しかし日本の正史といわれる記紀(古事記、日本書紀)は、あえてこの一大事件の記述を避けている。何故か? スサノオ以来十五代も続いた「出雲朝」に対する抜きがたい引け目が存在していたからだ。
且つ又、九州の福岡、佐賀、長崎、の各県、旧筑紫、肥前、肥後にはまともな神話が存在しない。「倭国大乱」で勝利した大和政権より歴史を奪われてしまったのである。従って、神話に由来する地名や人名は、隠語として当て字などを使うようになった。
以来、普賢岳も普通の活火山として【陰】の存在となったのだ。
その後、継体二十二年(528年)夏、九州の雄「磐井氏」が大和と列島統一を賭けた戦いを始めた。後世に伝わる「磐井の乱」である。古代日本を震撼させた戦争である。両軍入り乱れた白兵戦が一年半も続いた。からくもこの戦いに勝利した大和朝は名実とも列島の国家的統一を果たすが、九州、とりわけ筑紫、肥前、肥後を、常に反乱を窺う地域として、更に強い監視下に置くことになった。
【 六 】
信平は話を聞いているうちに、「磐井氏が、のちの天草四郎であり、西郷隆盛だったのだ」と思い始めていた。
その後の歴史において、度々英雄達が、時の中央政権に異を唱え、一矢を報おうとして本拠にしたのはことごとく、この地、筑紫、肥前、肥後である。のちの有馬氏の始祖と言われる藤原純友、源為朝、護良親王、足利尊氏などもそうである。
信平はここ肥前の歴史上における意味合いが分かってきたような気がした。
「この普賢はそのような山だったのですね」
「両山ともこの国有数の火山であり、国の命運を左右する霊山なのです」
次に、降伏が話し始めた。
「両山のうち、先行して噴火を繰り返したのは富士山でした。国が定まりし時からは天応元年(781年)の大噴火以来、宝永四年(1707年)まで七度の大噴火を起こしたのです。しかし寛文三年(1663年)に、ここ普賢の噴火があり、寛政四年(1792年)の、所謂「嶋原大変」で「攻守ところを変える」ごとく、富士は鳴りを潜めています。ある意味、この半島の荒ぶる普賢が、自ら「荒ぶる」ことによって、およそ、その山容が十倍もある富士の胎動を抑え切っていると言ってもいいのではないでしょうか」
信平は、師・龍雲が言った「火の道の理」の意味をはっきりと理解した。富士と普賢は、対立しているように見えて、実は連動した相関関係を保ってきたのだ。江戸三百万人が噴火災害に遭わずにすんだが、この嶋原半島の犠牲も終わりにしなければならない。信平は、普賢岳の鎮撫の意義を確信したのだった。
【 七 】
風が吹いて来た。波も荒くなってきた。そして雨までも降ってきた。激しき雨と風、山なす荒い波は猛り狂い始め、橘湾を漕ぎ進む小夜の小舟は翻弄された。
-
「だけど私は往く、信平さまの御跡を慕いて」と、私は己を叱咤しました。
強風に吹き上がる波浪は高く高く舞い上がり、低く降りた雲の中に入るかと錯覚する程に舟を持ち上げ、次の瞬間は奈落の海底へ急転直下に落ちてゆき、海底に突き当たるのかと思え、私は目を閉じて身体をすくめるだけでした。
しかし舟は海底に衝突することなく直ちに波頭に持ち上げられます。私は櫓を漕ぎ続けるだけでなく、波が舟の中に入り続けるので、その度に海水を汲みださなければならなかったのです。
「のぶへいさまぁ~」と、幾度、御名を呼んだことでしょう。
「さよ~ さよ~」と、はは様の声も聞こえてきました。
「はは様も父様への愛は、小夜のようになされたのですか?」
全身凍てつくような強風。
「晩秋の寒気は激しく、手と足はしびれて自由がきかなくなってきました。私はここでもう死ぬのかも知れない」と、諦めが胸の奥でちらりと動きました。しかし、長崎での信平様との出会いを思い出すと、忽然と力が湧き、再び海水を汲みだす手に力が入りました。
「信平様にお会したい」という想いが強まるほどに、「死」を怖いと考えなくなりました。むしろ、雨、風、波に曝されている自分が誇らしく思えました。
「肉体は滅びても霊魂は神のみもとに」との、亡きはは様の教えを胸裏に深く納めているからなのでしょうか。人の縁とやら運命とやらの拠って来る縁は、私には解らないけれども、信平さまと私の縁は前世からの縁のように思えてならないのです。
ふと見上げると、揺れる波間から野母崎の灯台下に、誰かが発光信号を送っていました。目を凝らして見詰ると、「ナミカゼアラク フネガダセヌ ガンバレ ユウキアルヒト ガンバレ ガンバレ」と読めて、私は胸がこみ上げてきて、再び涙があふれました。
【 八 】
信平、降伏、敬愛の三人は、洞窟の中で多くの事を語り合った。普賢岳や嶋原の歴史、不受布施派の受難、西南の役、明治という新しい時代の到来……。やがて、三人の心には強い絆と揺るぎない使命感ができていった。
そして、普賢鎮撫の為に、一心不乱に真言と法華経を唱和し続けた。わずかの乾飯と水だけしか口にしなかったが、昼夜を問わず力強い読経が洞内に響き、次第に彼らの内部に強い法力が生まれようとしていた。
「師匠、これより普賢山頂に参りまして、最後の鎮撫祈願をいたしましょう」との降伏の提案があり、信平以下三人は洞窟を出て普賢山頂を目指した。
途中つつじ野の一本道があり、三人は錫杖を振り、一心に歩き進む。
と、つつじ野が途切れる辺りの岩場に一人の異様な風体の人間が居て、こちらを睨んでいる。髪を腰まで垂らし、手足を岩場に着け、動物のような姿勢をしていた。
眼光が獣じみていた。「人ではない……」そう直感したが、立ち止まらなかった。
三人が通り過ぎようとした時、
「どこへ いく!」
女の声であった。
「言えぬ!」と、信平が言うと、
「キエーーーッ」と凄まじい奇声を発し、異様な女が岩場を蹴って空に舞い上がった。
三人は振り向き様に錫杖を激しく振り、右手を眼前に捧げ、「ノウマク サンマンダ、(慈救呪・ジクジュ)バザラダン センダ、マカロシャダ ソワタヤ ウン タラタ カンマン……」と呪文を唱和した。
一般の人には、三人がただ岩場に向かい呪文を唱えているように見えるだけだが、三人には全く別の物が見えていた。
それは、先ほどの女が空に舞い上がり、瞬間のうちに化身した大土蜘蛛である。八本の足を広げると優に十メートルはあるだろう。日輪さえも遮られて、辺りは薄暗くなり、雨が降ってきた。
大土蜘蛛は口から白い糸を無数に吐き出し三人を絡めていった。三人の身体は蜘蛛の糸に緊縛され、呪文が途切れがちになった。
-
我を知らずや その昔
此の日の本に 天照らす
伊勢の神風 吹かざらば
我が眷属の 蜘蛛群がりて
六十四州を我がものとなしたものを
その刹那、背中の木箱から一条の煙が立ち昇り、一直線に大土蜘蛛に突進していった。その直後、三人の頭上で大破裂音がした。
見ると、大土蜘蛛の腹が真っ二つに裂けていた。そしてその裂けた腹から、蠢く黒い塊が、わだかまって出てきた。何万匹もの土蜘蛛である。折からの疾風に煽られたように、風に乗り、その土蜘蛛達が、ある方向に流されて行く。
三人はしばし呆然とした、が、我に返り、「あれは、どちらの方角か?!」と、信平が叫んだ。
「有馬の原城でございます」と降伏が応えるやいなや、信平は走りだした。二人も続いた。三万余の死霊が漂う、有馬の原城を目指して、走りに走った。轟々たる雨の中を。
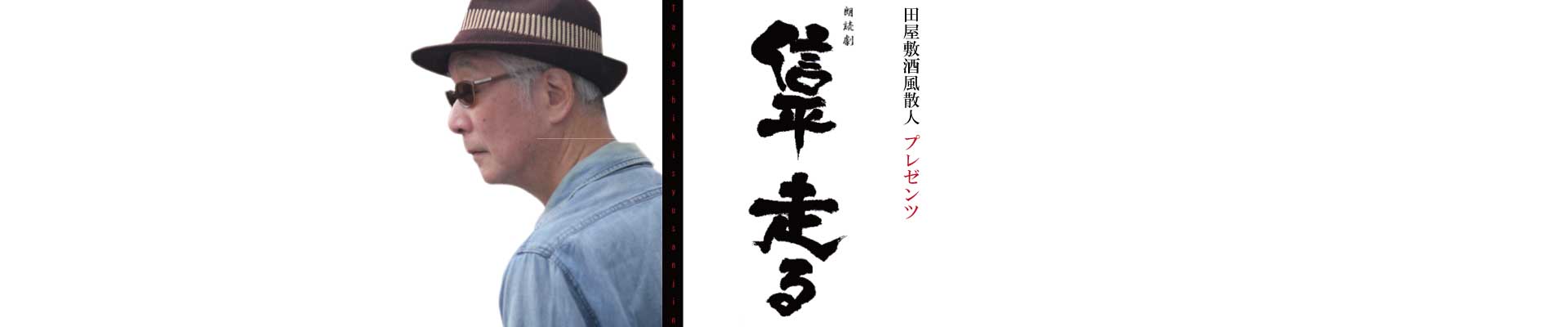
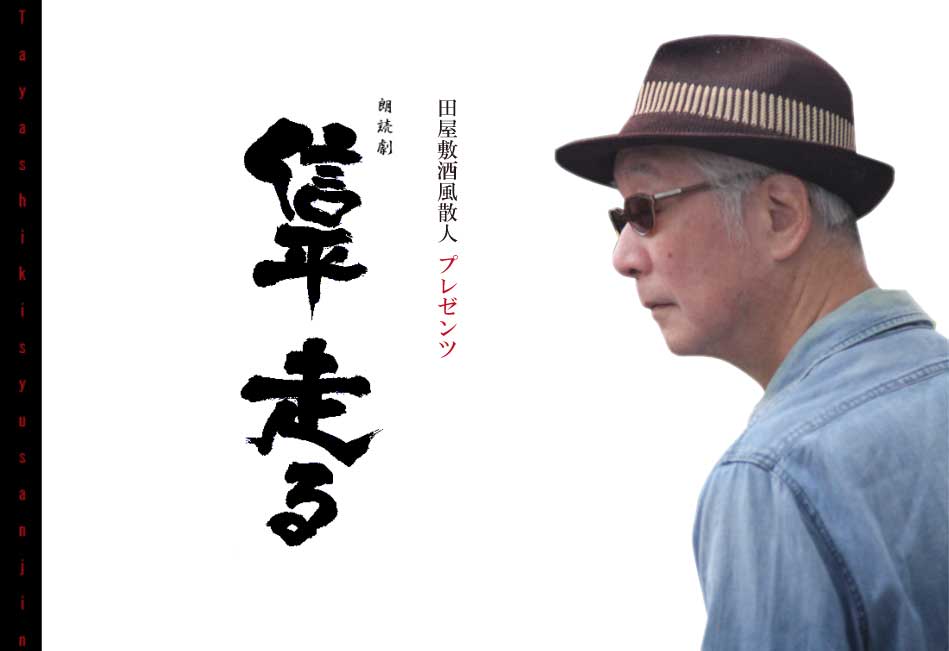
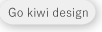 クリック!
クリック!


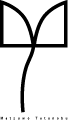
 トップ
トップ