第五段
原城レクイエム編
【 一 】
-
「まず、私の運命の試練を言って聞かせよう。私がどれほどの苦しみに耐え、困難に打ち勝って、今そなた達の眼にうつる、不死の勲の主となったかを。
よく思うがよい、そなた達にしても同じことだ。苦悩に満ちたけわしい運命は、苦しみぬいた生涯の果てを、栄えあるものとする為に、神が与えた賜物だ。
行こう! この私と共に日野江城に!
この陣中で、並ぶもののない勇士の誉れを勝ち取りたい者は、この戦いと禍の元・松倉を自らの弓と矢でしとめ、日野江城を落とすのだ!
並びない勝利の品々を父デウスの御前にかざり、そのよろこびを分かつのだ。
だがそなた達、忘れてはならぬ、城は落としても、神を忘れてはならぬ。父デウスは、ことのほかこれを望みたもうたのだ。神を思うこころは死よりも強い。それは人の世を貫いて不滅なのだ」
寛永十四年(1637年)十一月末、老若男女三万七千人のキリシタンが、有馬の原城に立て篭もった。所謂「島原の乱」である。
今、折りしも総大将・天草四郎時貞が、戦闘開始の檄を朗々と壇上より謳い上げた。御年弱冠十六歳。洗礼名・フランシスコ四郎。
「今から二十六年後、一人の神童が現れて人々を救うだろう」かつて、こう予言して天草を離れたバテレン、外国人宣教師・ママコスがいた。「島原の乱」で総大将として一揆軍を率い、「神の子」と尊称された天草四郎時貞が、今まさに救世主として現れたのである。
【 二 】
一揆鎮圧に向かった幕府軍の原城攻めは十二月に始まったが、統制を欠き、当初大損害を蒙った。途中、オランダ船を頼んで海上から砲撃すら行われた。
それでも抵抗を続けるキリシタン達に業を煮やした幕府軍は、戦術を転換し、兵糧攻めで一揆軍の疲弊を待った。
城内の食糧も底をついた翌寛永十五年二月二十七日、総攻撃の火蓋が切って落とされた。守る一揆軍はあるだけの銃弾を放ち、石臼や鍋釜までも投げつけ、必死の抵抗を試みたが、孤立無援の原城は、翌日の二十八日、総勢十二万の幕府軍の前についに落城。城内にいた一揆軍のほとんどは惨殺された。
四郎と首謀者たちの首は、長崎の出島で晒されたといわれるが、謎は多い。四郎にまつわる謎めいた伝説が今なお伝えられている。
一つは、原城の戦の七年前、尾張藩丹羽郡扶桑村にキリシタンが居るとの報を受けて、藩の役人が急行し、該当者を捕縛した。ポール兵衛門、その子・シモンコスモ久三郎とフランシスコ四郎、医師・コスモ道閑、レオン庄五郎の五人であった。五人は牢に入れられ、翌朝、処刑される予定であったが、朝になるとフランシスコ四郎がいない。
牢番に聞いても、何も不審なことはなかったという。キリシタン四人は黙して語らず、四郎がいないまま四人は処刑された。「空から天狗が舞い降りて来て、四郎は西の彼方へ連れ去られた」と言い伝えられた。
もう一つは、原城落城の折、四郎は討ち取られ、その首を長崎出島に晒されたとのことだが、それは別人で、四郎は落城前に落ち延びたという。本丸の抜け穴はが1963年に発見された。不思議なことに、尾張扶桑村には、原城落城の数年後、四郎が諸国に潜むキリシタンを励ます旅をし、途中、生まれ故郷の扶桑村にも立ち寄ったと伝えられている。
-
月見草 咲きやれ
四郎どんがった
【三】
国内におけるキリシタン弾圧の歴史は次のとおりである。
-
「あるいは火と燃え、光と輝き、自由を希求した我々の、あまねく世界を治める父デウスの御子である我々が勝利すると信じて戦ってきた。
しかし事ここに至って、戦果は我々に利するところあたわず。
先に逝きし我らが父、母、嫁、夫、息子、娘達は全能デウス様の御元で、天国の門を叩いていることだろう。
何事にも比して、暮らすべき地は、もはやこの地上には存在しない。
願わくば終世をこの山、海、川、田地田畑と共に全うすることを神に日々祈ってはいたが、もうそれも明日からは叶わぬ。
さぁ! 我に続け!
最後の一戦を華々しく、雄々しく、挑もうではないか!」
四郎最後の言葉である。
【四】
司馬遼太郎は「街道をゆく」で、原城をこう語っている。
「本丸台上の平坦地にのぼりつめると、まわりの景色がにわかに大きくなる。西方いっぱいに裾野を豊かにひくおだやかな山容の火山群が峰を重ね、白っぽい天をふちどっている。気の晴れるような大観と言っていい。原城にいれば、終日、海景と山景に飽きることがない。このため『日暮城』と呼ばれた」
現在の原城跡発掘作業で、当時の戦いの苛烈さ・痛ましさを物語る、おびただしい数の人骨と砲弾、火縄銃の玉などに混じって鉛製十字架、青銅メダイ、青、緑、白色のガラス製ロザリオの珠が出土している。そのいくつかは人骨の顔の付近から出土しており、死を目前にしたキリシタン達がそれらを握りしめ、最後の祈りを捧げたのではないかと想像される。
特に昭和二十六年二月、原城本丸跡から発掘された金の籠状筒型十字架は二十二金製の極めて精巧なもので、当時の輝きを今でも失っていない。おそらく天草四郎の胸で輝いていたのではないか。
「島原の乱」以降、領内の住民のほとんどが死に絶えた島原半島南部では、幕府が「強制移民令」を出し、村の復興が計られた。九州一円、小豆島、その他から移民は行われ、現在の南有馬の母体となる村づくりが始まった。
しかし原城は乱の後、歴史から抹殺されるがごとく、その全てを幕府軍より徹底的に破壊されて埋め戻され、『封印』された。それより数百年、四郎以下三万七千の御霊は『殉教』の呼び名すら授かることなく、「島原の乱」は日本の歴史上から消されてしまった。
ローマ法王庁は未だに「島原の乱」で死んでいった、三万七千人の誰一人として『殉教』の称号を与えていない。第一の理由は、神父が存在しないところでの事件だったからだ。さらに、カトリックの教義が、地上の王 為政者に対する反乱を認めていないからである。ローマ法王庁の見解では、現在も「島原の乱」は宗教上の戦ではなく、農民一揆とされている。
死後の安住の地を見出せないまま、漂う数万の御霊達。
-
義を取り 生を棄つるは
わが尊ぶところなり
ただ まさに一死をもって主恩に報いむ
【五】
小夜の乗る小舟は、風雨による荒波に翻弄されながらも、橘湾を横断し、天草灘を通り抜け、目指す有明海に近づきつつあった。
-
いつの間にか雨は止み、険しく走る雲間から月の光がさしてまいりました。その光で、波間から黒い山を頂く陸地がかすかに見え始めました。
月齢は十七夜のように思え、やがて潮流は引き潮へ移る頃合いかと考えた時、私は急に奮い立つ思いに胸をせかされました。
引き潮に移る前に、舟を浜のほうに寄せなければ、大変なことになると思ったのです。有明海の引き潮は足が早く、小さな舟は瞬く間に外洋に流されてしまうでしょう。そうは思っても、舟をどうしたら良いものか、漕げども漕げども、外海へ外海へと引き戻されるように感じられ、そしてそれは次第に強くなっていったのです。
風の強い海は、浪の寄せ引きも分からぬ程に、大波が次々と寄せてきます。この大波で舟が岩礁に叩き付けられたら、舟もろとも私の肉体も瞬時に木っ端微塵になり、血と肉の飛沫となって波と共に散ってしまうでしょう。
-
聖母マリアさま わが魂が肉体と離れた時に
貴方様の御前に導きたまえ
【六】
信平以下三名は土蜘蛛の大群の後を追い、有馬村に達していた。
「蜘蛛の大群はあの高台に向かったようです」
降伏が指し示した先は、有明海を望む岬の突端へと続いており、小高い丘が見える。その辺りにひときわ黒く、不気味な雲が渦巻いている。
「あれは……?」
「有馬の原城跡です」
「あの、天草四郎以下数万の一揆軍が立て篭もったという」
「はい。あの高台は本丸跡と聞いています」
「行こう!」
と、敬愛、降伏も後につづいた。
畑の中の一本道は次第に坂道となり、急に曲がりくねった道になる。明らかに、戦いの跡が残る城に続く道である。本丸台地に出ると、そこは荒れ果て、雑草が生い茂り、乱以降うち捨てられたまま永い年月を経た様子がうかがわれた。
「師匠、あれを!」
と、敬愛が指差す方向を見ると、何万もの土蜘蛛の大群はさらにその数を増やして地面を覆い尽くし、巨大な土蜘蛛の柱となり空へ立ちのぼるや、上空二十メートル辺りで反転し、次々に四方に拡散していった。それからまた一つに固まり、信平達の頭上に突進してきた。蠢く土蜘蛛の中に、苦痛に歪み、断末魔の叫びを上げる顔が浮かんでは消える。
野太い声が三人の頭上から聞こえてきた。
「おのれら邪教徒が、われわれの聖地に足を踏み入れるとは、ふとどきなり!」
その声を期したように、土蜘蛛は幾千の手負いの武士、農民へと姿を変えた。その顔は、皆、死人のように青白く、光のない目は信平達を見るではなく、虚空を見詰め、何かをかぼそくつぶやいている。その声が地鳴りのように本丸台地に広がっていた。
「我等は普賢岳を鎮撫するものだ。何故、我等の邪魔をする!」
信平は印を結び、呪文を唱え始めた。敬愛、降伏も続く。
-
「ノウマク サンマンダ、バザラダン センダ、
マカロシャダ ソワタヤ ウン タラタ カンマン……(慈救呪・ジクジュ)」
【七】
傷つき血にまみれた怨霊達は、じわりじわりと信平たちに迫ってくる。
突然、正面の武士の怨霊が手に持った槍をかざし、信平に向かってきた。
「∩!」
信平の発した「気」は、武士の頭部で炸裂し、首がちぎれ、頭部が地に転がり落ちた。しかし頭部を失った胴体から槍状のものを無数に突き出し、またもや信平に襲いかかる。
再び「気」を発する信平。その気は胴体だけの怨霊武士を吹き飛ばした。が、その間に地面に転がっていた頭部から半身を再生した怨霊が襲いかかってきた。
どちらか片方を倒しても、もう一つが再生して襲いかかる。そんな攻防が幾度か続いた。信平に疲労感が漂い始めた。だが怨霊達も信平らを包む結界を破ることが出来ない。
今度は怨霊の背後にいる数百の一揆軍の怨霊兵達が、念動力を紅い閃光弾に変え、三人をめがけて続けざまに撃ちこんでくる。
三人も新たなる「気」を、青い光線に変えて迎え撃った。紅蓮と青の光エネルギーが空中で激しくぶつかりあい、砕け散り、火の粉のように降り注いだ。
バリッ、バリッと稲妻に似た轟音が響き渡り、すさまじい風が樹々をなぎ倒す。
息をつく間もない攻撃に、信平以下三名の疲労の度合いは頂点に達しようとしていた。
信平が膝を屈した。
「師匠!」と心配気に降伏、敬愛が駆けよった。
それを見てとった怨霊達は、火の玉に形を変え、三人にとどめを刺すかのように上空へ集まっていった。幾千もの怨霊の集合体が巨大な幻影を浮かび上がらせた。
【八】
まだ幼さの残る顔立ちをした少年の幻は、きらびやかな衣装を纏い、その胸元には黄金の十字架が輝いている。その姿は、天草四郎に他ならない。
「何故、我等を撃つ! 何故、戦わねばならぬ!」信平は叫んだ。
やや甲高い声がしてきた。
-
「戦場で立派に死んだ皆々の親しみを受け、死後もなお、尊く畏い君主として、誉を受けていたものを。
だが今も尚あの世とやらに行くことも叶わず、この憎き島原の地を漂うだけだ。
あまつさえ優しく迎え入れてくれたのは、荒ぶる普賢岳のみであった。
信じる道は異なれど、時を統べる者どもに一矢報わんとして敗れた我々を優しく育んでくれていたものを、お前達は何故に揺り動かし、覚醒させる。
あ~ぁ、なんということか。黄泉の者らを治める全能の神デウスさま、殺された幾万の力強い呪いを今こそご高覧あらんことを。
しかし、事ここに至ってそのデウスの子らが、今どんなに力ない、みじめなざまになっているかを見ていてください」
信平に絶体絶命が迫ってきたその時、信平の背中から竜巻のごとき蒼雲が湧き上がり、火柱を包み込んでいった。火柱と蒼雲は激しくもみ合い、稲妻が何度も宙を走った。
次第に四郎の幻影が空に引き上げられるように浮き上がり、その顔に苦悶の表情が
見て取れた。その直後、四郎の正面から蒼く太い矢のような光が鋭く飛んできて、ド―ン! と、四郎の胸に突き刺さった。四郎の幻影は霧散した。
信平には、消える直前の四郎の顔が微かに微笑んだように見えた。
ひとしきり、原城跡は降りしきる豪雨に包まれていた。
【九】
-
舟を放り出された私は一瞬にして海中に沈み、死を覚悟いたしました。それでも、荒れ狂う波にのまれながら懸命に海面に浮かび上がっては息をし、必死で岸を目指しました。
二度、三度と繰り返したのですが、女の力ではもう、限界と思われました。
「もはや、これまで。信平さま、残念ですが、小夜は力尽きました」と観念し目を閉じた時、沈みゆくわが身から恐ろしいほどの速さで潮が引いていくのを肌で感じたのでございます。
僅かに残る力を振り絞り、必死に手足を動かしたその時、海底に足がつき、またたく間に、海面が肩まで引いてゆきました。また降りだした激しい雨が、海面を叩いておりました。私には聖母マリア様が起こされた奇跡としか思えませんでした。
「生きている、私は生きている! 信平さま!」
「師匠、あれを!」と敬愛が指をさし、叫んだ。
信平は見た。揺れる陽炎の中に人の姿を。
「誰かこちらに向かってきている」と降伏。その姿が大きくなってきた。
「小夜だっ! あれは確かに小夜さんだ。さ~~よ~っ」
有明海は世界でも有数の干満の差が激しい海である。そんな有明海の中でも、原城三百メートル沖に、年に二、三度だけ大潮の時、「幻の島」が出現する。土地の人たちは古くから「真砂の白洲」と呼んでいる。正式には「リソサムニューム礁」というその白洲は、この地球上にイギリス海岸、インド洋、原城沖の三箇所にしかない。この「真砂の白洲」から対岸の有馬村までは歩いて渡れる。しかし、それもほんの三十分間程度である。そしてまた、何事もなかったように、海の底になる。
小夜はまさにこれによって救われたのである。


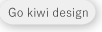 クリック!
クリック!



 トップ
トップ