第七段
小夜走る編
【 一 】
明治十二年六月、梅雨に入りここ数日雨が降り続いていた。店を敬愛と小夜に任せ、信平は降伏を伴い半島内を歩きまわっていた。信仰の拠点となる、日蓮宗不受不施派の寺の建立計画の実施である。
敬愛と降伏の先祖が残した名簿を頼りに、一軒一軒信者たちを訪ね、趣旨を説いて回った。明治御一新後の解禁で各信者の反応は良好なものだった。
そんなある日、信平が信者訪問から店に帰ってくると、小夜が、「信平さま、岡山から御子息の辰十郎さまがまいられました」と言った。
「辰十郎が? どこにいる?」
「奥の座敷で休んでおられます」
行くと確かに辰十郎であった。きっちりと膝を揃えて座り、床の間に飾られた《青龍の掛け軸》をじっと見つめている。
「辰十郎、久しいな」
「父上、ご無沙汰でございます」
辰十郎は信平を見るや、手をつき、折り目正しく頭を下げた。信平が岡山を後にした頃には、まだ少年のにおいが濃かった辰十郎も、たくましく背も高くなり、立派な青年へと成長していた。
「なんぞ岡山で起こったのか?」
「これを」と辰十郎は懐から一通の手紙を差し出した。妻・雪野からの手紙であった。
-
信平さま
貴方様が島原へと旅立たれて、幾たび桜の季節が過ぎましたでしょうか。
先達て、私はお医者さまより労咳という不治の病を申し渡されました。
一時は病に恐れ慄き、鬱々とした心で眠れぬ夜を繰り返しながら、貴方様との思い出ばかりを心に浮かべる日々を過ごしておりました。
思い出は寂しさの別の呼び方かもしれません。寂しいと口にするには寂しすぎるから人はそれを思い出と呼ぶのでしょうか。
『人はみな孤独なもの』という理の向こう側にあるものを、私は懸命に貴方様の中に見つけようとしていたのやもしれません。
『出逢いは偶然ではなく全て必然なのだ』と貴方様に教えられたことを想うにつれ、また別離も必然ではないのかと問ううちに、私は一筋の道を見い出し、今は晴れやかな心持ちで毎日を過ごしております。
信平様、長い間ありがとうございました。
どうぞして、私のためにお心をくだくことなどなさいませんよう。
辰十郎のことのみは、末永くお頼み申し上げます。
「雪野は……母は何と言った?」
「父上は大望を達成させんがために、更に険しく困難な道へ進まれることを選び、島原へお発ちになられたのだから、あなたも一人前の男として、父上のもとでそのお志に従い、父上を援け、私たちの信仰の拠り所を建立するために力を尽くしなさい、と申されました」
「母の病のことは」
「存じております。ですが母上は……」
一瞬言いよどんだが、辰十郎は
「母上は、まず、父上のお指図に従うようにと。そして母上自身も、病を得たからこそ、みずから進むべき道を知り、信心をきわめるためにその道を歩む、と申されました。私には、岡山に戻ることは断じてならぬ、と」
【 二 】
信平は小夜を長浜海岸に誘った。
少し前から、雨は小休止するかのように止んでいた。有明の海は一面に靄がかかっていて、岸まで迫っきて信平と小夜を包み込んでいた。
信平は懐から雪野の手紙を取り出し、「これを」と小夜に手渡した。
小夜は手紙を受け取ると、かすかに震える手で手紙を開いた。
手紙を読み終えると信平を見上げた。
「御いたわしい」
「うむ」
それ以上の言葉はなかった。
無言ではあったが、小夜のその眼差しに、ある決意が込められているように信平には感じられていた。
その夜、信平は雪野の病や、辰十郎の今後についてあれこれ考えていると、なかなか寝付けなかった。
東の空が白む頃になってようやく微睡
んだのも束の間、「お師匠さま!」と寝室の廊下側から、緊張した降伏の声がした。
「どうした?」
「小夜さまが、いらっしゃいません」
「えっ」
信平が小夜の居室に行くと、綺麗に寝具が重ねられている。
「もしや」と信平は呟いた。
「行き先にお心当たりでも?」
「心当たりというまでもないが……皆には急の用事で里の浦上村まで帰った、ということにしておきましょう」
「はい」
その日から小夜は不在となったが、普段と変わりない明け暮れが営まれた。辰十郎には、しばらくは旅の疲れを癒し、何事も敬愛の指示に従うようにと伝えておいた。
【 三 】
小夜が居なくなって二日目の午後、一人の青年が信平を訪ねてきた。二十五、六歳ぐらいの眉が濃く、引き締まった体つきの青年である。
「私は樽井藤吉と申します。」
「猪原信平です。御用の向きは?」
「はい、ご尊宅にあるといわれる、西郷先生ゆかりの品々を拝見させていただきたく、まかり越しました」
「では、あなたは西郷先生のご縁者の方ですか?」
「はい。お聞き届けいただけますでしょうか」
「よろしいでしょう。西郷先生の縁の方とあらばお断りできますまい」
信平は坪庭の泉水の近くに青年を案内した。かの砲弾を指し示すと青年は、「ほーう、これが……」と言って、しばし沈黙した。
その後、信平は青年を奥の座敷に誘い、茶をふるまった。青年はニ副一対の《青龍の掛軸》の前に座りしばし瞑目した。
「ありがたいものを拝見しました」
「なんの、こちらにおられる間は、好きなだけご覧になられると良いでしょう。さて、あなたと西郷先生のご縁を伺いたいと思っているのですが。お見受けしたところ、ほかに故あってこの島原においでかと」
「さすが、鋭いお方だ」と樽井青年は語り始めた。
「私は大和の出身で五条の材木商の次男に生まれまして、もの心つくと学問をしてみたくなり、儒者の森田節済先生に学びました。二十五歳の折、明治六年に家を出まして、更なる学問を積みたく上京し、諸先生を訪ねる日々でございました。当時、国論は朝鮮との国交回復の是非で沸いておりました。そんな折、同郷の先輩に『そんなに、君が西郷の論に賛同しているならば、彼の書生になったらどうか』と勧められ、それならばと、西郷先生を訪問しようとした矢先、先生は論に破れ、鹿児島に帰られて、残念ながら私の目的は果たせなかったのです」
「そうでしたか。先生の砲弾の事はどこで耳にされたのですか?」
「西南の役が終わったあと、鹿児島に参りました」
「城山へ?」
「はい、せめて西郷先生の御霊に手を合わせようと」
「私も城山へはいつか、と思っています」と信平は遠くを見つめるように言った。
「手を合わせていると、年のころ五十歳前後の屈強な方が声をかけてきました。
しばらく話をするうちにその方が云うには、西郷先生が劣勢の中、この鹿児島まで帰ることが出来たのは、当時、先生のお側におられた猪原信平さんという方が持っていた《青龍の掛け軸》、その青龍のご加護の賜物なのだと。
そして西郷先生は、猪原信平さんに一発の砲弾を預けておられるから、あなたは島原に行きなさい、行って猪原信平さんと会い、西郷先生の預けた砲弾と《青龍の掛軸》を見せてもらいなさい。そう聞かされて、やってきました」
「恐らく、その方も西南の役に従軍されたのでしょうが……」
「左様、そのように申されておりました」
「砲弾や青龍を見てこの旅は終わり、ではありますまい」
「いかにも。実は、私は西郷先生の意志を微力ながらも継ごうと思っております。猪原さん、あなたにもご助力をお願い致したく」
「まずはお話を承りましょう」
樽井藤吉は座を正して話し始めた。
【四】
『征韓論』のことの起こりは、明治初年、新政府が朝鮮に対して国交を復活させようとしたことである。
幕末期、欧米列国の圧力に負け、通商条約を結んだ日本に対して、鎖国政策を取っている朝鮮は国交を断絶した。明治新政府が樹立されると、朝鮮との国交を復活させようとの動きがでてきて、まず新政府は国書を朝鮮に送った。
がしかし、朝鮮政府は明治政府の国書の中に『皇上』や『奉勅』という言葉を見て、国書の受け取りを拒否した。『皇上』や『奉勅』という言葉は朝鮮にとっての宗主国である清国の皇帝だけが使う言葉であると考えていた。
次に新政府は外務権大録・佐田白芽を主席に交渉団を派遣したが、朝鮮の首都にも入れず帰国を余儀なくされた。帰国した佐田は政府大官達に『即刻朝鮮を討伐する必要がある』と説いて回った。
明治六年(1873年)六月十二日、太政官(だいじょうかん)閣議が正式に開かれた。
その閣議でのそれぞれの主張するところは、
-
木戸孝允 --- 主として武力をもって、朝鮮の釜山(プサン)港を開港させるべし。
外務小輔 上野景範 --- 朝鮮に居る居留民の引き上げを決定するか、もしくは武力をもって朝鮮に対して修好条約の調印を迫るか、二つに一つだ。
板垣退助 --- 朝鮮に滞在する居留民を保護するのは、政府としては当然であるから、直ぐ一大隊の兵を釜山に派遣し、その後、修好条約の談判にかかる方がいい。
と兵の派遣に大勢が傾く中、西郷は首を横に振り述べた。
西郷隆盛 --- それは早急に過ぎもす。兵など派遣すれば、朝鮮は日本が侵略してきたと考え、要らぬ危惧を与える。ここは責任ある全権大使を派遣することが一番の良策でありもうす。
三条実美 --- では、その全権大使は、軍艦に乗り兵を連れて行くのが良いでしょう。
というと西郷は、
西郷隆盛 --- いいえ! 兵を引き連れるのはよろしくありもはん。大使は鳥帽子に直垂を着し、礼を厚うし、威儀を正して行くべきでごわす。
しかし西郷は「新政府の首脳が一同に会した閣議において国家の大事の是非を決定できないなら、今から正門を閉じて政務を執るのを止めたほうがよか」と一喝した。
その後、西郷自ら全権大使を志願するが、帰国した岩倉は、余りにも天皇の親任の厚い西郷を退ける為に、閣議で決定されたことを天皇に奏上しようとはせず、自分の個人的意見である西郷派遣反対を奏上するという腹黒い一計を講じた。この一計が功を奏し、ここにおいて西郷の平和的国交回復の目論見は潰えた。
時を置かず西郷は鹿児島に下野した。西郷の居ない政府は、大久保らを中心に明治七年、台湾を武力で取り、八年には朝鮮と江華島で交戦し、徐々に武力外交を強めていった。そしてそのことが後の第二次世界大戦に繋がっていくのである。西郷を失ったことが日本の舵取りを大きく狂わせたのである。
「西郷先生は、『征韓論』などという乱暴なことを主張したことはただの一度もなかったのです」
樽井青年の話を聞き終えると、信平は、
「西南の役従軍の折、先生のお側におりましたけれど、先生はどんなことであれ、只の一度も言い訳がましいことを口にされたことなどありませんでした」と当時を思い返して言った。
樽井青年は、さもありなん、といった顔で繰り返し頷いた。
「猪原さん、今度は西南の役の際の、西郷先生の話をお聞かせ願えませんか」
「分かりました」
信平は、西郷との出逢いから、西南の役出陣、戦の時の言動、武士道についての考え方、篠原国幹の勇ましさなど思い出す限りの話を樽井青年に語って聞かせた。
やがて正座して耳を傾けている樽井青年の頬を、一筋、二筋と溢れ出る涙がつたい、握り締めた膝の上の両手に落ちる音が、ポタ、ポタ、と響いた。
信平の話を聞き終えると、樽井青年は涙で濡れた顔を挙げ、《青龍の掛軸》に向かって一篇の詩を謳いあげた。
-
水の中には 水ばかりあるのではない
空には あの空ばかりあるのではない
そして僕の中には 僕ばかりいるのではない
僕の中にいる西郷先生の魂は
僕の中で 僕を揺さぶる
水のように空のように
僕の深いとこを流れて
密(ひそか)なる僕の夢となる
先生は今 天にいるからこそ
尚更(なおさら)、僕は先生が恋しい
「はい」
樽井青年は涙をぬぐい、再び座を正すとまっすぐに信平を見つめて言った。
「私は、いずれこの島原の地で決起します」
【五】
その頃、小夜は小倉を目指していた。
島原から、江戸年間より対岸の肥後・長洲までの航路が開かれている多比良村へと入り、航路で長洲に上陸し三池、柳川を通り、久留米の府中より長崎街道の脇街道となる秋月街道へと入った。
九州の街道の全てが小倉の紫川にかかる常盤橋に繋がっている。
「吉備岡山の雪野さまにお逢いしたい」
その一心で、何かに衝かれたように、ただひたすらに走る小夜。
「雪野さまにお逢いしたい、逢ってそのお手を握り締めて差し上げたい」と念じながら走り続けた。その思いにいつしか亡き母・ゆりの信仰への強い信念を重ねあわせ、ひた走りに走った。
「ここにおります私どもは、みんな神父さまと同じ心でございます」と自らキリスト教信者を名乗り出て、新政府に捕縛され流罪に遭い、獄死した母。
母や小夜達を育んだ浦上村・家野は連綿とキリシタン信仰を守り続けた。その昔、家野にはサンタ・クララ教堂が建っていたが、慶長十九年(1614年)の切支丹禁令で破壊された。それでも近代まで信徒は残っていった。
-
家野は 善かよか 昔からよか
サンタ・クララの土地じゃもの
明治初頭に起きた浦上信徒に対する虐待と苦役と拷問の連鎖した流人生活こそは、誠に惨憺たる『旅』であった。ある歴史家は、これを日本近代史上の一大汚点と評している。
小夜の旅は、雪野に逢いたい一心の旅ではあったが、浦上村のキリスト教徒であった母の死出の旅をなぞる意味も心の奥底に流れていた。
「信仰とはわが身と我が命を捧げることでしょうか? 母様、サンタマリア様、微笑んでばかりいないで、お教えください」
「小夜、救いを施し給う神さまは、いつも見えないとこにお隠れなのよ」
「では、目には見えないけれど、確かに神さまはいらっしゃる、ということでしょうか?」
「はい、でも誰も神さまのお姿を見ることはできないし、そのお手に口付けることもできないのよ」
「母様、それでは神さまはいらっしゃらないのと同じではないですか?」
「ですから、賭けるのです。神さまが存在する方に自らを賭けるのです」
「母様は、命まで賭けたのですね」
慶応四年、明治元年(1868年)の長崎キリシタン流配では、浦上信徒の中心人物・百十四名を山口、津和野、福山の三藩へ流し、小夜の母・ゆりは福山に配流された。福山には二十九名が流された。世に言う『浦上四番崩れ』である。慶応三年(1867年)十二月九日、徳川幕府が倒れ、明治政府が成立し、慶応四年二月参与に任ぜられた沢宣嘉が長崎に着任した。彼がまず着手した仕事は浦上キリシタンの処分である。
-
一、 切支丹・邪宗門之儀は堅く御制禁たり、若不審なる者之有れば、その筋之役所に申出向、ご褒美下さる可事。
四月には大阪にてキリシタン処分の御前会議が行われた。三条実美、木戸孝允、伊達宗城、井上孝、大隈重信、が出席。
席上、最強硬案であった木戸孝允の意見が通った。木戸の強硬意見の中の大きな要素として、なんと二百五十年前の『島原の乱』が存在していた。『一村が全てキリシタンであれば、どのような暴動を起こすかも計り難い』という訳である。
六月一日を記して、百名以上のキリシタンの、謂わば『死の行進』が始まった。遠くから眺めると黄木綿の手拭を被ったり、洗礼の時の白布を被った人の群れが続いて行った。見ると幾ばくかの手荷物を下げ、或いは幼子の手を引き、乳飲み児を背負うて行く母親達がいた。健気にもロザリオをまさぐり、頬を真っ赤に染めながら小雨の中を歩く青年や娘達もいた。杖にすがりながらヨロヨロと歩く老人の姿は、沿道に人垣をつくる人々の涙を誘った。その中にいた小夜の母・ゆりは常にあることを念じながら『死』への歩みを進めていた。
-
たとえわたしは
死の陰の谷を歩むとも
わざわいを恐れません
あなたが私と共に
おられるからです
わたしの生きてる限りは
必ず恵といつくしみとが
伴うでしょう
私はとこしえに
主の宮に住むのですから
四番崩れの後、浦上は無人の村と化した。


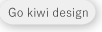 クリック!
クリック!



 トップ
トップ