信平走る外伝
龍奇伝
-
この国が平和だと 誰が決めたの?
人の涙も乾かぬうちに
アメリカの傘の下 夢も見ました
民も棄てた戦争の果てに
蒼いお月様が泣いております
忘れられないこともあります
遠い昔の、ある夏の日。蒼い空が広がっていた、あの暑い日。
八月六日
妹のよしこちゃんが やけどでねていて
トマトがたべたいというので お母ちゃんが
かい出しにいってる間に よし子ちゃんは死んでいた
いもばっかりたべさせて ころしちゃったねと
お母ちゃんはないた わたしもないた
みんなもないた
八月九日
のどが渇いて たまりませんでした
水にはあぶらのようなものが一面に浮いていました
どうしても水が欲しくて
とうとう油の浮いたまま飲みました
【一】
その年、三人の少年が長崎県の島原でひと夏を過ごしていた。少年たちは『カズ』、『アル』、『ミツ』と呼ばれていた。
本当の名は別にあるのだが、三人は同年の同月・同日に生まれ、それぞれ由緒ある寺の僧侶や神職から命名されたにもかかわらず、不思議なことにまったく同じ名前がつけられたために
親たちが愛称をつけ、呼びならわしていた。
ここ数年、世界中で予測できない気候変動がおこり、大きな災害や人災とも呼べる大事故が次々に人びとの生活を襲っていた。
彼らが過ごしている家の旧家屋も、現在では蔵がわりに利用されているだけだったが、たて続けに起こる台風や地震に傷みつくし、一旦は取り壊すことが決まっていた。夥しい収蔵品の整理などに大人たちは追われていたが、子供にとっては格好の遊び場所であり、探検するにはもってこいの場所であった。
ある日のこと、三人は今までに気づかなかった扉が書棚の裏に隠されていることに気づいた。開けてみると上へと続く階段である。
「ねえ、なんだと思う?」
「さあな。もしかしたら屋根の上に出られるかもしれないな」
「行ってみようよ」
薄暗く、一段あがる度にギシ、ギシ、と軋む階段を昇った。行き止まりにある古い扉には一応の鍵がつけてあったが、なんの苦もなく扉は開いた。
「なんだ、本ばっかりじゃないか」
「ほんとだ。何の本だろう。信…平…? 汚れててわからないや」
手近にあった本を手にとったミツは積もったホコリに顔をしかめて言った。
「こっちには『ハリー・ポッター』があるよ。でも、相当古い本だ」
アルが見つけたのは、子供時代に世界中の誰もが読むファンタジーの名著だったがこれも紙が黄ばんで古びている。
「ふーん、なんだか魔法とかに関する本ばかりみたいだ。誰のものだったのかな」
カズは本棚に並べられた書籍が『龍』や『魔法』、『風水』などに整理されているのを見ながら、手にとってページをめくってみたりしている。
「カズ、アル、ちょっと来て。これ、なんだろう?」
ミツが指さしたものは、古びて薄汚れた布に包まれた、細長い木箱のようなものだった。
「開けてみよう」
三人は木箱を囲むように座り込み、包んでいる布を丁寧に取り去った。
蓋を開けようとした瞬間、
キィーン!
微かな、それでいて高く鋭い音が響きわたり、少年たちの目の前は真っ暗になった。
「二人とも大丈夫か?」
やっとのことでカズが口を開いた。
「うん、大丈夫……見て!」
三人の足元の床が青白くぼんやりと光っている。水の波紋が広がるように光は大きく強くなってゆく。しかし、眩しさは感じさせない不思議な光であり、やがてその中に様々な風景が浮かび始めた。
「これ…なんだろ」
「幽霊とはちょっと違うだろうな」
「あっ! 火山が噴火してる!」
ミツが指差した。
【二】
光の中の風景は鮮明な画像となり、映画を見ているかのようだ。噴火した山から吐き出される煙と、一瞬にして全ての物を呑み込む火砕流はまるで怪物のようにすら見える。
そして次に見えてきたのは巨大な『水』の魔物が町に襲いかかり、木々も家も人をも、あっという間に押し流してゆく様だった。
「なんでこんなものが見えるんだろう?」
「少なくとも、僕らは同じものを見てる」
その時、三人は同時に『声』を聞いた。
〝子供たちよ。やっと、この地に揃ったか…いや、まだ足らぬか〟
異様な『声』に、弾かれたように三人は立ち上がった。
「だれ?」アルは辺りを見回した。だが、誰もいない。
〝恐れずともよい。我はこの地に住まうもの〟
『声』は頭の中から響いてくる。
〝ぬしたちが見たものは、この『地』の記憶、『水』の記憶〟
「記憶?」
カズはまた変わった光の中の風景に、一人の少年を見出した。
白い衿の服を身に着け、胸には十字架を掲げた美しい顔立ちの少年は、時折、やや疲れた表情を浮かべながらも、粗末な着物を着て、跪き、十字架を握りしめながら少年に向かって祈りを捧げる人々の間を悠揚と進んでいく。
やがて立ち止まると、人々に向かい、決意を込めた凛とした声で語りかけはじめた。
-
「あるいは火と燃え、光と輝き、自由を希求した我々の、あまねく世界を治める父デウスの御子である我々が勝利すると信じて戦ってきた。
しかし事ここに至って、戦果は我々に利するところあたわず。
先に逝きし我らが父、母、嫁、夫、息子、娘達は全能デウス様の御元で、天国の門を叩いていることだろう。
何事にも比して、暮らすべき地は、もはやこの地上には存在しない。
願わくば終世をこの山、海、川、田地田畑と共に全うすることを神に日々祈ってはいたが、もうそれも明日からは叶わぬ。
さぁ! 我に続け!
最後の一戦を華々しく、雄々しく、挑もうではないか!」
【三】
少年たちは、ただただ押し黙って映し出される映像を見守った。
それはこれまで語られずにいた歴史の一部分であり、紛れもない真実ではないのか。何故自分たちにそれが理解るのか。知るはずのない人が、場所が、時間がわかるのか。
また新たな場面が浮かびあがってきた。
広い畳敷きの座敷に、五名の武家が額をつき合わせるようにして何事かを話し合っている。
「会津中将、保科正之殿のおなりー」
次の間を隔てた廊下から、来訪者を告げる声がひびく。武家たちの顔に緊張が走った。少時の間をおき、保科正之が姿を現した。
寛文八年(1668年)春。江戸城内において秘密裡に行われた協議の場であった。
『島原の乱』(寛永十四年・1637年)後、島原藩主・松倉勝家はその責めにより切腹の刑に処せられ、代わって遠江・浜松の高力忠房が島原へと入部したが、二代・隆長の代に改易となりその座は宙に浮かんだ。
一刻の猶予も許されぬ中、時の老中である稲葉正則、久世広之、板倉重紀、土屋数直の四名とことの重大さゆえに大老・酒井忠清も協議に加わっていた。この場に現れた保科正之は徳川二代将軍・秀忠公の庶子で別格中の別格の大大名であった。
保科は列席者たちを一瞥し、座に就くや
「島原がことは将軍家の一大事」
一同がうなずく中、保科は続けた。
「あの山は眠れる『龍』じゃ。誰が藩主になろうとも、天災人災は必ず起きる」
老中連は皆、唖然たる表情をした。
「山とは、普賢岳のことを言っておらるるのか?」
「左様。島原のあの山には『龍』が封じ込められておる。誰が治めようとも、いずれあの山と領民は暴れ出す」
一同は保科の発言の奇怪さに重い空気を漂わせていた。
「『龍』が封じ込められ居るとは、異なことを申される。誰が何のためにその様な」
「太古の昔、九州の地には『龍』を『神』と頂く王朝があったのじゃ。しかし、大和との戦に敗れ、その命脈は途絶えた」
「大和朝廷に封じられた、と」と酒井大老が始めて口を開いた。
「されど、なぜ今このときに」
「『龍』を封じた大和朝廷が昔日の力を失い、天下は徳川家のものとなりすでに久しい。封じる力が衰えればまた暴れだすは必定」
老中たちの顔には、一様に不可解と恐怖がない交ぜになった表情が浮かぶ。
「かの山を鎮めるがために、いかに計らえと申されるか」
「これは戦じゃ。かの山を鎮めるためならば、将軍家自ら犠牲になるしかあるまい」
一同はごくり、と唾を飲み込んだ。
「いかにも、保科殿の申されるとおりじゃ。されば、どなたを?」
酒井大老は暗い目つきで保科を見つめる。
「権現公のみぎりから、戦の先陣は松平十四家が勤めるのが御定法。さすれば、深溝松平家の他にあるまい」
この決断は、現福知山藩主・松平忠房を保科自ら説得するということでもある。忠房は温厚篤実で領民の信も篤いとの声高く、神仏に対する心も深いとの評判が将軍の耳にも届くほどの人物であった。
この保科裁定に一同は安堵し、島原の藩主が決定した。
明けて寛文九年、別名『臥龍城』と称された福知山城を発し、松平忠房は島原に入部した。
入部の日の払暁、家臣大岡直義が島原領内、猛島神社内で切腹した。『荒ぶる龍』が封じ込められた普賢岳に対しての『人身御供』であった。
【四】
少年たちの見つめる映像は、やがて宇宙から眺める『地球』へと変っていった。
その『地球』に張り巡らされた幾筋もの輝ける黄金の光。
「これは、地球だね」
「テレビでみるよりもずっときれいだ。ほんとに青いんだ」
アルは自分の足元に見える自分たちの住む惑星の美しさに息を呑んだ。
「この、金色の線はなんだろう」
無意識のうちに、地球儀に触れようとするかのように三人が手を伸ばした瞬間、体がふわりと宙に浮き、『地球』へと下降していくような感覚に包まれた。
〝太古の昔から、人の世の営みが始まる前から、我等はあった。大地の下を流れる天界をも支える『気』の流れ、その『気』の道『龍脈』と留まるところ『龍穴』を治め守ってきた〟
「じゃあ、これが『龍脈』なんだな」
カズは体を傾け、もっと近寄ろうとした。
『龍脈』が交わるところや到達点にあたる場所に『龍穴』はあるらしく、時々強い光を発している。
〝我等は天界を、天帝・黄龍を守護するために四方の護りへついた。北の『玄武』は地を、東の『青龍』は水を、西の『白虎』は風を、南の『朱雀』は火を司った〟
ひときわ強い光を放つ山脈から、巨大な『龍脈』が東西南北へと走り、さらに枝分かれしながら諸方へと散ってゆく。
〝かの山、崑崙から走り出る『龍脈』とともに我はこの地へ〟
支那の西方、黄河の源となる崑崙山脈から東へ向かう『龍脈』は長江を下り、東シナ海を渡り、まっすぐに島原半島を目指し普賢岳へと流れ込む。
では、この『声』は普賢岳に眠る『龍』なのか?
〝永い時を経るうちに、人は神を忘れ、神も人を忘れゆく。故に『気』も風に散りゆく〟
まばゆいばかりに地表をおおっていた『龍脈』の多くはその光を失い、涸れてしまった。
「人間が自分で世界を悪い方向に進ませているの? 神様は人間を忘れてしまうの?」ミツは堪らずに『声』に問いかけた。
〝神は『気』によりて働く。人に『気』があれば神が宿り、神が宿れば『気』もあり。神が去れば『気』は絶え、『気』が無くんば神は去る〟
「人間と神様はつながってるの? 神様の世界も人間の世界も同じなの?」
〝人の善き『気』が溢れる時は我等も穏やかなり。悪しき『気』で満つる時は災いとなす。天界が乱れし時は人の世も乱れ、人の世の争いは天界にも嵐を呼ぶ〟
ずっと昔の『戦争』でこの国に落とされた二つの大きな『禍』が、不気味な雲の形となり映しだされる。遥か天上では血の様に紅く染まった空を、黒い炎が焦がしている。遠く近く映し出される光景は、どちらの世界も地獄絵図さながらであった。
【五】
少年たちの眼下には緑深い島原の山々が、涸れることなく溢れ出る湧水に満たされた大地が拡がっている。
〝我はこの地で一時の眠りにつき、我の内に『水』を治めてきた。この地には時として我を知り、我を聞くものが現れる。わずかに残る『龍脈』の故か〟
金色の帯が普賢岳の麓から南の海へと向かう。
蒼く広い海に浮かぶ美しい島。上空から、地上へと下降するその先には『首里城』だ。朱に彩られた壮麗華厳な城が目に飛び込んでくる。古代琉球王朝の王城・『首里城』は、南北に長い沖縄本島の背骨のように走る丘陵の南の端、北からの『龍脈』が那覇市を抜けて東シナ海に注ぐ流れの上にある。
首里城正殿前には大龍柱と呼ばれる一対の柱が通る者を見下ろしている。
右に口を開いた阿形の龍、左に口を閉じた吽形の龍。
『阿』は口を開いて最初にだす音、『吽』は口を閉じて最後にだす音を指し、『万物の根源』と『一切の帰着する知徳』を意味するという。
〝かの地も、我の治めし『水』を持つ泉がある〟
いくつもある首里城の門の一つ、『瑞泉門』へと上る石段の途中、『龍樋』と呼ばれる石彫りの龍の口から、清冽な水が溢れ出ている。『瑞泉』とは、『美味し水、立派なめでたい泉』のことだ。
〝この地の『水』と、かの地の『水』に育まれし子らがやがて目覚める〟
『声』がわずかに遠く聞こえる。首里城も遠くなり始め、三人の体も上昇し続けている。
〝子らが目覚めれば我等も覚醒する〟
「子らって、僕らのこと? 他にいるの? どこに?」
カズは遠くなり始めた『声』にあわてて質問する。
〝ぬしたちは、かの地で出会う〟
「どうして僕らにこんなものが見えるの? 僕らは何なの?」
アルも必死に叫ぶ。
〝ぬしたちは我の末裔、我等の命脈。だが目覚めるまでには、まだ時がある。目覚めれば世を変えねばならぬ〟
『声』はほとんど聞こえなくなっていた。穏やかな光も、いまや目が眩むほど強くなっている。
カズ、アル、ミツは確かに見た。巨大な『龍』が地球を取り囲むようにうず巻いている姿を。溢れんばかりの光に包まれて、三人は不思議な世界から現在へと戻っていった。
三人は同時に目を開けた。
はじめに居たところから一センチたりとも動いていない。
しばし、顔を見つめあったまま、身動きできずにいる。
「今の、何だったのかな? 三人で同じ夢をみたってことじゃないよね」
アルが呟いた。カズ、ミツもうなずきあう。
「なんだか、いろんなものを見たような気がするけど、ぼんやりとしか思い出せないや。カズ、なにか思い出せる?」
「んー、なんかずっと声が聞こえてたよな。で、水がいっぱい流れてて、赤い建物みたいなのが見えた気がする」
しばらく、思い出そうと試みる。ふと足元をみると、開けようとしていた木箱は元通りに布に包まれている。
「これ、開けようとしてなかったっけ?」
言いかけたところで、外から三人を呼ぶ声がきこえてきた。
「やべっ、また怒鳴られるよ」
ミツが立ち上がり、アルも立ち上がった。
「行こう、カズ」
カズが元あったところに木箱を戻すと、三人は階段を駆け下りていった。
残ったのは、はじめと同じ静寂と薄暗がりのみ。
木箱から、コトン!と音が聞こえ、何かが動いた気配だけが伝わり、やがて消えていった。


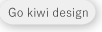 クリック!
クリック!



 トップ
トップ