第十一段
龍刺青編
【 一 】
明治十四年四月中旬、信平は南高来郡長・大岡正制に呼ばれ郡役所に出向いた。
郡役所は島原城の東堀端にあり、徒歩で行ける距離であった。
着くと大岡は丁寧に信平を出迎えた。
「猪原さん、学校建設でお力をお貸しください」と大岡は切り出した。
「どのような……」
「現在のような私塾乱立では国家の教育理念が行き届かないという、お上のお達しがありました。そこで公立学校の建設を急げ、とのことです」
「なるほど」
「土地は旧藩主さまなどの協力を仰ぎ確保しましたが、資金が目標額には届いておりません。そこで猪原さんには建設資材を予算内で集めていただきたい。損な、割りに合わない仕事と知りつつ、お願いします」と大岡は頭を下げた。
信平は他の業者は恐れをなして逃げたことを推察した。
しばし沈黙したが、信平の胸には西郷の魂が脈々と流れていた。
「分かりました。やってみましょう」
「かたじけない、つらい仕事を押し付けてしまって」と大岡は再度、頭を下げた。
明治十四年二月に「改正教育令」が発令され、島原町と島原村を五部に分け、一部につき一校の小学校を設けた。
信平達の住む大手部は、島原町の宮ノ丁・片町・中町他15地区の総人口4840人で一つの小学校を設けた。
5月4日には「小学校校則綱領」が通達され、分けて初等、中等、高等の三等にするとある。
信平の資材収集の仕事は急を要した。
降伏、敬愛、辰十郎を始め、他の雇い人までも九州一円に出張させ、木材、石材、金具などの建設資材を調達させた。
大岡の果断な判断と信平の長崎・佐賀・日向・鹿児島での過去における濃密な人間関係が効を奏し、何とか他の地域が始動する直前に、しかも格安の価格で調達できたのである。
【 二 】
すでに秋になっていた。
集く虫の声が激しい夜、信平と小夜は、久しぶりに居間で寛いでいた。
お茶を飲みながら話はじめた。
「どうにか間に合って、ようございましたネ」
「そうだな、みながよう働いてくれた」
「そうでございますネ。辰十郎さんも立派にお働きでございます」
「あれもなかなか 役立つようになってきた」
と満足気に信平がお茶を飲み干した時、玄関に誰かが訪れた声がした。
「ごめん ください ませ」
女性の声である。小夜が応接に出た。
「突然の訪問をお許しくださいませ」
「あなたは?」
「長崎から参りました、道永 栄と申します。不躾とは存じますが、一目なりとも『青龍の掛軸』を拝見させていただきたく、参りました」
小夜に案内された道永栄と名乗る女性は信平の前に平伏した後顔を上げ、信平と相対峙した。つぶらな瞳を持ち、黒々とした髪を簡単に束ねてはいるが、人並み以上の美しい女性であった。
「で、お栄…さんは何故、この掛軸をご存知なのですか?」と信平は聞いた。
「はい、青龍が増田四郎さまを鎮撫されたと聞きました故」
「えっ、それを何方に?」
「叔父からです。私も叔父も天草の大矢野島の生まれです」
「とすると、天草四郎と同じ……」
「はい、そうでございます」
「で、叔父御はどうして、鎮撫の件を?」
「たまたま、当日湯島近くに漁に出ていたそうです。雨がひどくなり引き返そうとした矢先に、原城の真上で物凄い音がした、青い大きな龍が空を舞うのを見て、そのあと若い青年の笑い声を聞いた、と……」
「そうですか……」
「その時、四郎さんが昇天されたのだ、と咄嗟に分かったと申しておりました」
「で、私だと分かったのは?」
「はい、その後、島原の術師・猪原信平様が鎮撫された、と人伝に聞いたのだそうです」
このころ、信平が術師であることは、人から人へ噂となって近隣に伝わっていたのである。
「……どうぞ、掛軸の方へ」
「ありがとうございます」と、お栄は『青龍の掛軸』の前に正座し、しばし瞑目した。
室内を《静寂》が支配した。
お栄が戻ってきた。
「これで心おきなく、旅立てます」
「ほぅ、どちらへ?」
「オロシャでございます」
「あの蝦夷の先のオロシャですか?」
「はい。ウラジオストークというところへ行きます」と、きっぱりと云った。
お栄は、その後も信平から目をそらすことなく、続けた。
「私は、父が早くに亡くなりまして、叔父に育てられました。叔父は常日頃、大矢野島の四郎さんを大変尊敬しておりました。私は、幼い頃から四郎さんの話を聞いて育ったのでございます。それは『自分一身を捨て、他の人の為に尽くす』という四郎さんの生き様です。今回のオロシャ行きも私自身が決断しました。自分の外地での仕事が、微力ながらもお国の役に立つと考えましてございます」
信平は、目の前にいるまだ二十歳少し過ぎたばかりの娘の、ただならぬ決意を聞いた思いがした。
その日の夜半、お栄は信平の元を去った。
信平は、開け放した座敷に時折流れる秋風の心地良さと同じものを「お栄」に感じていた。その「風」のせいなのか、『青龍の掛軸』がコトリ……と揺れた。
【 三 】
道永 栄は安政七年(1860年)に生まれた。この年二十二歳。
十二歳の時、遠縁を頼って茂木にわたり、旅館で女中奉公をする。
その後、料亭「ボルガ」の女将 諸岡まつの世話で、稲佐の「ロシア将校集会所」で家政婦として働く。
ウラジオストックを母港とするロシア極東艦隊は、嘉永六年(1853年)から日露戦争までの半世紀の間、長崎で長期越冬していた。常にロシアは不凍港を求めて南下の期を窺っていたのである。
お栄は『青龍』に見える一週間前、主人・諸岡まつに呼ばれ、ロシア行きを申し渡されていた。
「ウラジオでは、長崎の集会所のことが大評判でねえ。是非、支店を出してくれって、ロシア海軍のお偉方から頼まれたのヨ。お栄さん、ここは一番、私を助けてちょうだい。あんたしかいないのよ、安心して任せられるのは」と強く説得された。
翌年の春、お栄は、ロシア艦船バルトーク号の船長付きボーイとしてウラジオストックに渡った。再び帰国するのは十年後の明治二十四年である。
ウラジオでの十年間のお栄の活動に関して詳細を記したものは何もない。が、「日露外交秘史、諜報機関伝聞の件」という文献にわずかにその痕跡が残されていた。そこには「道永栄」のロシアでの活動が記してあった。
【 四 】
明治二十年(1887年)年某月、ロシアの青年アレクサンドル・ウリアノフがお栄の店にやって来た。
「許可が下りて、やっと来れました」
「首を永くして、お待ちしてました」お栄は既にロシア語が堪能になっていた。
「でも一泊しか出来ません」
「分かっております」
「お栄さん、僕は……」
「もう、なにも」とお栄は人差し指で青年の口を封じ、自ら青年の胸に身体を預けていった。
翌朝、まだ暗さの残る朝もやの中、青年は馬に乗り、お栄の元を去っていった。
昨夜、二人は互いに手紙を交わしていた。お栄が渡した手紙は、帝国海軍大佐・東郷平八郎からのものであり、青年からは、東郷へあてた手紙である。手紙は東郷からの青年の行動に対するお礼。青年からは資金援助に対するお礼の内容であった。
ウリアノフは一週間後、シェリッセブルグ要塞監獄で絞首刑になっている。
この若き将校は昨年6月、ロシア皇帝アレクサンドル三世の暗殺計画の首謀者であった。逮捕され、絞首刑に処せられる前、両親を始め、つかの間ではあるが暇乞いの時間を与えられたのである。
ウリアノフの弟は、のちにロシア革命の父と云われたウラジミール・レーニンである。その時、レーニンはまだ十六歳の少年であった。
第一次ロシア革命は明治三十八年(1905年)に起きるが、その蠕動は18年前のこの事件まで遡る。明治政府は当時からロシアの南下作戦を感じ取り、内政撹乱を期待して、革命勢力に対し資金援助をしていた。
レーニンは兄の刑死に強い衝撃を受け、革命運動へ強く傾斜していく。
お栄は流氷が溶け始めたある日、ウラジオ港を見渡せる小高い丘の上に立ち、はるか数千キロ彼方の天草や長崎に想いを馳せていた。鉛色の海と空が、見る人のこころを陰鬱とさせる南シベリアの港・ウラジオストック。短い夏の間の漁業とロシア極東艦隊が落とすお金で生活し、冬はひっそりと暮らす街。
お栄は温暖な天草や賑やかな長崎への思いで胸が熱くなり、流れる涙を拭きもせず、嗚咽を洩した。
とその時、お栄の頭上かなたの空で耳をつんざくような雷鳴が轟いた。お栄は思わず耳を両手で塞ぎこみ、身を縮めた。次に何処からともなく、野太い声がした。
「使命を果たせ!」 一言いうと元の静寂に戻った。
「龍の声?……いや、あれは確かに龍の声なんだ」とお栄は確信した。
【 五 】
時を前後して、明治十六年(1883年)秋、炎熱地獄のような夏が終わり、朝夕がめっきり涼しくなった九月中旬のある日、一人の眼光鋭い男が信平のもとを訪れた。
「東郷平八郎と申します」
四十がらみの立派な口ひげを生やした堂々たる男であった。
「猪原 信平です」
「突然の訪問、恐縮です」
「で、ご用件は?」
「『青龍の掛軸』を拝見したく、また、西郷どんのことをお聞きしたくて参りました」
「えっ、東郷さんと西郷さんのご関係は?」
「同郷でございます」
「そうでございましたか。どうぞ奥へ」と、信平は座敷に誘った。
座敷にて東郷はしばし『青龍の掛軸』に見入り、合掌して何事かつぶやいていた。その後、信平のもとに来て、小夜が入れた茶を喫した。
信平は西南の役での西郷について、思い出す限りのことを話した。
東郷は、身を乗り出して話を聞いていたが、ややあって自らのことを話しはじめた。
「私は西南の戦の折は、英吉利におりました」
「留学されていたのですか」
「はい、当初大久保さんに留学を願い出たのですが、断られました。そこで西郷どんに談判して、やっと留学許可が下りたのです」
「そうでしたか」
「……残念です」と東郷は眼を落とした。
「西郷さん……ですか」
「はい、とても残念に思っております」
「それほどまでに西郷さんのことを……」
「もし、日本に残っていたなら、必ず西郷どんの下に馳せ参じていたでしょう」
膝の上に置いた東郷の両手は震えていた。
事実、東郷の実兄である小倉荘九郎は、薩摩軍三番大隊九番小隊長として従軍し、城山攻防戦で自決しているのであった。
【 六 】
東郷の弁によれば、現在、西郷の予言通り朝鮮から大陸にかけて、ロシアの南下の気配も含めて、日本は厳しい局面に立たされている、とのことである。今、自分は海軍中佐という立場にあり、この日本の現状を何としても改善せねばならない、という。
信平は東郷の中に西郷の面影を見て取った。己が一身を賭して何事かを守り通す、武人の姿を見たのである。のちの日露戦争における日本海海戦で大勝利をもたらす、連合艦隊司令長官・東郷平八郎、三十代の時である。
「信平殿、たってのお願いがございます」
「どのような?」
「実は大陸への戦略上、佐世保に鎮守府を造る計画です」と東郷は話し始めた。大規模な海軍基地を佐世保に定め、その現地測量の責任者として彼は佐世保に来ていたのである。
が、東郷は佐世保在住の古老の話がどうしても気になるという。それは、佐世保近郊の海上で、毎年一、二艘の船が遭難するというものであった。時期はまちまちだが、場所はきまって佐世保湾外の松浦島周辺であると云う。
土地の人は「祟りである」と恐れている。
「そこで、信平殿に是非、ご同道ねがい、祟りの真偽を明らかにしていただきたいのです」と東郷は深々と頭を下げた。
「あい分かりました」
やや沈思したのち、信平は承諾した。東郷は安堵して辞した。
【 七 】
翌朝、信平は辰十郎と降伏を引きつれ、一路佐世保を目指し、走りに走った。
夜の帳も降りきった頃、三人は目的の佐世保湾外の「松浦島」に上陸した。
月も隠れて闇に近い夜であった。信平は二人に指示して竹を四方に立て縄を張り、結界を作らせた。
その中で信平は呪文を大音声で唱え始めた。他の二人は数珠を一心にかき鳴らしている。
小一時間も経ったであろうか、突然、間近の海が一瞬盛り上がった。
突風が三人を襲う。三人とも総毛立っていた。そして、もう一度海が盛り上がる。
盛りあがったまま海水が真っ二つに割れ、建造物らしきものが姿を表わした。
信平はますます大声で呪文を唱え続けた。
船である。巨大な木造船だ。
海から蟠り、大量の海水を海に落とし込む。
轟音をあげながらその全容を露にした。
海面から十メートルも浮かびあがり、舳先にはぐるりと篝火をめぐらせている。
と、その中央に三人の武将装束の亡霊が現れた。
「推参なり! 我らの海を汚すものよ!」と中の武将が云い放った。
次に、三人は弓を引き、矢をつがえた。
「放て!」 鋭い矢が信平の側に刺さった。信平は動ぜず、なおも呪文を唱える。
「何ゆえに、衆に害なす!」と信平は心の声を亡霊に放った。
亡霊たちはみな、顔が長い毛で覆われていて、赤ら顔で口が耳元まで裂け上がっている。
人間と見紛う、伝説の化け物「海に住む猩猩」であった。
猩猩三匹が口を揃えて云った。
-
海士の刈る
藻に住まう虫のごとき我ら。
音こそ泣かめ、世をば怨みじ。
今宵はことに波静か、
よき隙ありと、夕月隈隠れ、
宵よりやがていり潮の、
安らかな夜を何故とて、
怪しき呪文で壊しぞなす?
「安穏たる海を取り戻すため、祈りに来た」
-
またもや執権の手先か!
蒙古襲来の折、関東の執権、
我ら松浦党を塵芥のごとく、海の捨石とぞなす。
我ら一族郎党
悉く平戸彼杵一円の海に没する。
冷たき海底の辛さを、知るや400年。
恨み申す、執権。
執権!……恨み申す。
「成仏せんことを、祈りにきた!」と叫ぶ信平。
波も騒ぎ出し、船の篝火は船体に燃え移り、猛火となった。
-
見よや因果のめぐり来る。
火車にお前達も呼び込んで、
同じ地獄を味あわせん。
思うも怨めし、いにしえの。
思うもうらめし、いにしえの。
益々勢いを増した火炎が信平に襲いかかり、徐々に信平の身体が海に引きずり込まれてゆく。
「さがっておれ!」
うしろに控える二人は鞭で打たれたように反応し、20メートルばかり飛びのいた。
呪文を唱える信平が苦悶の表情に変わったその時、突然大気も割れんばかりの大爆発音があたりに鳴り響いた。
猩猩の物の怪たちの舟が、「どうっ」と左右に大きく揺れた。あたり一面に豪雨が降り注ぐ。
火の勢いが減じはじめてきた。
「り……、龍だっ!」、船上の猩猩が叫んだ。
-
「我は この海の守り神。そなた達の恨みは 我が胸に納めた。こころ安らかに 行くがよい」(龍の声)
瞬く間に猛火は消え、豪雨も止んだ。いつの間にか龍の姿も消えている。もとの静寂が信平たちを包んだ。
-
龍神に導かれし我らに、
もはや怨みは消え失せた……。
大和の簒奪者などでなく、
我らの神に導かれたのだ。
海底にて安んじて眠りにつかん。
【 八 】
明治二十四年(1891年)、ロシアでの使命を終えた道永栄は9年振りに長崎に帰ってきた。その9年の間に、お栄の才気と美貌振りは遠くロシアの首都、ペテルブルグまで鳴り響いていた。諸岡マツは、帰崎したお栄にロシア兵慰安所の最大拠点の料亭「ボルガ」の全てを任せた。
その年の4月初め、海軍福岡軍令部より二人の士官がお栄のもとを訪れた。
「来る今月末二十七日にロシア皇太子ニコライ二世が艦隊を率いて長崎を訪問する、宜しく接待せよ。また、ニコライの領土的野心ありや、を探れ」という達しを携えてきたのである。
果たして、二十七日、ニコライがやってきた。
二十二歳の若い皇太子は好奇心旺盛で、上野彦馬に写真を撮らせたり、街角で出会った少女にかんざしを買ってやったりもした。
7泊8日の長崎滞在中、夜は必ずお栄に会いにきた。
お栄も持ち前の美貌と流暢なロシア語でおおいにロシア皇太子をもてなした。
【 九 】
その滞在2日目の夜、突然ニコライは護身用である自分の拳銃をお栄に差し出した。
「えっ、なぜ? 私に……?」
「貴女の国の言葉では 愛ね。愛があるとこれはいらない」
「殿下……」お栄は自分の心の奥底に封印しているものを融される思いがして、立ちすくんだ。
ニコライは長崎滞在の最後の夜。お栄の部屋でくつろいでいた。
「お栄さん、明日、私は京都に行きます」
「おなごり惜しい、です」
「私も同じです」
「殿下、また長崎にいらしてください」
「きっと、来ます。……必ず」
お栄は一瞬、目をニコライからそらした。
「どうしましたか?」
「いえ、なにも……」とニコライを我が胸に抱きしめた。
お栄の涙が、はらはらとニコライの背中に落ちた。
「悲しい」
「……何故」
「生きるのは悲しい」
お栄の胸元あたりから、湯上りの甘い、陶然とさせる香りがしてきた。ニコライは両腕でお栄を強く抱きしめた。お栄もそれに応えた。衣擦れの音がした。行灯の灯が揺れて消えた。
しばし、時が経ち、お栄が静かに語りかけた。
「殿下、二人で同じ刺青をいれましょう、永遠の契りの為に」
ニコライは突然の申し出に戸惑ったが、思い定めるように、「はい……しましょう」とお栄を見詰めた。
翌日、彫り師を二人呼び、腕に入れたのは「青龍」の絵柄だった。
「殿下と私を守るのは、龍なのです」
「龍ですか?」
「はい」
お栄は、叔父から聞いた天草四郎の魂が龍から救済されるシーンと、青龍の掛軸を脳裏に浮かべていた。
その後の資料では、お栄のことを対ロシアのスパイであると断じているものもある。
ニコライは滋賀県大津市で暴漢に襲われるが、なぜか軽傷に終わっている。
ロシア第一次革命と日露戦争と東郷が指揮する日本海海戦の大勝利は十年後となる。
お栄の活躍は二の腕にある「青龍」の刺青とともに、歴史から消え去っていった。


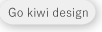 クリック!
クリック!



 トップ
トップ