第十二段
佳人の黎明編
【 一 】
1868年(明治元年)3月12日、西郷隆盛は江戸高輪の薩摩藩下屋敷内の一室に副官渡辺清を呼んだ。
「清どん、おはんは明日の勝さんとの話し合いの時、隣室で一部始終を聞いてくれもはんか?」
「はっ、承知しました」と渡辺清は平伏した。
この渡辺清は肥前大村藩士で、一早く勤皇倒幕の声を挙げた藩の一員として官軍に加わっていた。西郷はこの誠実で剣の腕もたつ渡辺をことのほか気に入り、戊辰の役以来副官として側に置いた。
西郷、勝の会談は十三、十四両日の予定であった。
初日は挨拶を交わす程度で直ぐに終了した。
いよいよ最終の十四日、新政府軍は既に翌十五日を期して江戸総攻撃を決定していた。もう勝には後がない。緊張して部屋に入った勝は西郷と対座し、しばし西郷を見詰めた。西郷はいつもと変わらず落ち着いた様子であった。勝が「西郷さん、これが」と降伏条件三か条をしたためた書状を胸から取り出そうとしたその時、
「わかりもうした」と西郷はいともあっさりと云った。
「分かった、ということは総攻撃を中止するということですね」と勝は念を押した。
「諸々は後で話せばよろしかろ」
勝は拍子抜けしたようだったが、じわりと西郷の豪胆さに打たれ始めていた。
「西郷さん!」と勝は西郷の両手を握り締めた。ここにおいて史上特記すべき江戸無血開城が決定した。
江戸百万の命が救われた一瞬であった。隣室で聞いていた渡辺は涙を流していた。
「もう 時代は完全に変わったのだ」と、幕府も朝廷もない、新しい体制に代わったのだという思いであった。
その後勝は親しい者たちにこう云っている。
「おれは、きょうまで西郷ほどの人物を二人と見たことはない。どうしても西郷は大きい。厚かましくも維新の元勲などとすましてるヤツと、とても比べようがない。西郷との談判はそりゃ きつかったよ。『わかりもうした、後のことは私が一身にかけてお引きうけもうす。』この御仁の一言で、江戸100万の人の命が救われた」と。
【 二 】
1888年(明治20年)信平は五十才を迎えた。小夜三十才。家業の金物店は順調に発展していた。
半島内の学校建設がここ五年間連続して続いていた。島原大手部を手掛けたのが「鉄は猪原」の評判を呼んだのだ。
世は正に信平が長崎の鉄橋を見たとき感じた通り「鉄の時代」になっていた。
信平と小夜は2年前に内輪だけで「祝言」を挙げていた。小夜は名実共に「金物店」夫人となって奥向きのことに的確な采配を振るっていた。
そんな春のある昼下がり、一人の麗人が訪ねて来た。島原ではあまり見かけない洋装の麗人であった。
「小鹿島筆子と申します。猪原信平さまはご在宅でいらっしゃいますか」
とはっきりとした口調であった。
「はい、しばらくお待ちを」と一番年若の番頭が、奥へ走った。
小夜が店に出てきて訪問者を奥に案内した。
信平は奥の座敷にいた。
「猪原 信平と申します」
「小鹿島筆子と申します。この度の突然の伺い、何卒お許しください」
「お気にめさるな。して私にご用の向きは如何なことですか?」
「はい、是非 青龍の掛軸を拝見させていただきたく まかりこしました」
「結構ですが、差し支えなければ訳をお話頂きたい」
「はい。私は旧大村藩士 渡辺清の娘でございます」
「えっ、渡辺清殿といえば、あの西郷さんの?」
「はい、ご維新まで西郷様の副官を務めていました」
「そうでしたか、それではうむもありません。どうぞ」と、信平は次の座敷の「青龍の掛軸」まで筆子を案内した。
筆子は掛軸の前に正座し、しばし瞑目した。明治三大貴婦人と謳われた筆子の周辺には、侵し難い雰囲気が漂っていた。
暫くして筆子は戻ってきた。
「素晴らしいものを拝見させて頂き、ありがとうございました」
「恐縮です」
「今回まかり越しましたのは父の命でございました」
「ほう、渡辺殿の命とな……」
「はい、父はあの西郷さんをお守りした青龍を、自分の代わりに見て来てほしいと」
「そうですか。して渡辺様は今は?」
「新潟県令を拝命いたしまして、彼の地におります。今回、大村にあります縁者の墓参に私に行けと……そしてその足で島原の猪原様宅に伺い、青龍の掛軸と対面せよと」
信平は十年前の西南の役の西郷との数々の係わり合いを思い出し、目頭を熱くするものに耐え、しばし沈黙した。
筆子は続けた。「父は私に申しました。これからは女も世に出よ。女しか出来ないこともある。だが三つのことを守れ、一つは死ぬ時は死ぬ、死を恐れるな、今は学問をしろ。二つ目は平時は地に潜み、いざとなったら龍になれ、三つめは、何とかなるもんだと思え、と」
信平は「それを、お嬢様に……」と感心するかのように頷き、小夜を見た。
【 三 】
「私は福祉を生涯の仕事にしようと思っています」
「福祉……とは、どのようなことですか?」
「私が先般フランスに留学しておりました折、彼の地での盲人や聾唖者に対する優れた教育を目の当たりに致しました。翻って日本は文明開化はいたしましたが、障害を持つ人達に対しての施策はまだまだでございます」
「フランスではどのような機関が、その福祉を行っているのですか?」
「やはりキリスト教会の活動が大きいと思います」
小夜の眼が輝いた。
「ところが日本ではご維新後もキリスト教はご法度で、私がまだ子供のころ大村の海岸線を何百人ものキリスト教徒の方々が縄で繋がれて行くのを見て悲しい心になりました」
「その中に私の母もおりました……」と小夜がポツリと云った。
「えっ?奥様は……」
「はい、代々キリスト教徒でございます」
「ではあのとき、お母様はどちらに?」
「備前、福山です。配流先で亡くなりました……」
「おいたわしい……もうそのようなことが、絶対あってはならないと思います」
「信仰が本当の意味で自由な日がくればいいのですが……」
その後、筆子は信平宅を辞した。
筆子はその当時、満2歳になる知的障害の長女を抱えていた。
小鹿島筆子。
鹿鳴館の華と謳われ、明治十三年、時の皇后の命によりフランスへ留学、二年を経て帰朝、明治十七年、官吏 小鹿島果と結婚する。順風満帆の前半生であった。
その当時のことをドイツ人医師ベルツが「ベルツ日記」の中で記している。
「日本の一女性の出現により、すっかり魅了されたが、それは小鹿島夫人で、自分が今まで出会った最も魅力ある女性の一人だった。夫人は達者な英語、フランス語、オランダ語を話せる人だった」とその才色兼備ぶりを表している。
しかし、明治十八年に長女 幸子の出生が筆子の人生の、試練の序章となる。長女幸子は生まれて半年で知的障害を宣告された。筆子はすがる思いで幸子と共にキリスト教の洗礼を受ける。
そんな失意の時期に、信平の元を訪れ、「青龍」を見たのである。
しかし、その後も悲劇は筆子に襲い続ける。幸子が四歳の時、次女恵子が生まれるが、生後時をえず死亡。翌年三女康子が誕生したが、やはり病弱で結核性脳膜炎を起こして知能と身体に障害を残した。当時、そのような子を持つ母は、恥とされ、蔑まれた。まして栄光の中にいた筆子には、耐え難い試練のように感じられた。
しかし、不幸はこれで終わらなかった。傷心の筆子に追い討ちをかけるように、夫の果が病に伏し、看病の甲斐なく帰らぬ人となった。明治三十年、筆子三十一歳の時である。
その年、筆子より一通の手紙が信平の元に届いた。
【 四 】
本文には次のようにあった。
「私は主が、艱難辛苦の旅を行われたことよりもまだまだ易しいことだと思うように努めました。また、娘幸子をお預けしていました、滝野川学園の経営に少しでもお役に立ちたいと思い定めました。三女康子も亡くなりました今、知的障害を持つ幸子一人になりました。悲しみに沈み込むより、命に代えてもこの子を守り抜かねばと神に誓いました。父が云い、また貴方様のところで拝見しました「龍」の心を持って、今後は福祉活動で生き抜く所存でございます。自分が弱くて、障害を持つ子らを救える筈はございません。まだまだ世の中は障害者を理解するには至ってはおりませんが、かつてフランスで学んだ人道主義の理念であります『人は人であることで神聖である』を心に深く刻み込んで日々を奉仕したく存じます。信平さま、小夜さま、青龍と共に遠く島原の地から筆子のこと見守って下さいませ」
信平は読み終わると信平は小夜に渡した。小夜は読むうち涙を流していた。
「何故、このような試練を与えられるのでしょうか?」と小夜は信平に訴えた。
「誰かが受けねばならぬ。強い心の人に敢えて試練は来る。お前の母も、そうだ」
「母も龍を見たそうです……」
「そうか」
「筆子さまも、きっと……」と頷く小夜であった。
障害者を排除・差別する歴史は東西とも古代から存在した。近代の「排除・差別」の思想的根拠は「社会ダーウィニズム」として次のように理論化できる。
「ダーウインの生存競争と自然淘汰の理論をそのまま社会に適用し、生物界における優勝劣敗の法則を社会に当てはめたものである」
この理論は戦争肯定論にも利用されている。
その後、筆子は滝野川学園にすべてを打ち込み、やがて園長 石井亮一の高潔な人格に深く感銘を受け、周囲の強い反対を押し切って、明治三十六年(1903)に亮一と再婚した。今日伝わる『石井筆子』の名は再婚名である。
筆子の甥にあたる関重弘は、このように述懐している。
「降るほどある縁談を断って、苦労の多い生活を選んで幸せかなのか疑問だった。しかしある日、伯父・亮一がさる財閥から多額な寄付をもらえるといって出かけたが、手ぶらで帰宅したことがあった。不浄のお金はもらえないから断って来た、と伯母に語ったのだった。それを聞くや、よくお断わりになりましたと云い、伯母は嬉しそうだった。伯母は幸せなんだなと思った」
夫・亮一と筆子は日本初の障害者施設「滝野川学園」の運営に奮闘した。
しかし筆子は、大正九年、学園が火災にみまわれたとき、子供を捜す中、階段から滑り落ちて片足を傷め、不自由な身となる。
更に、夫・亮一の死、自身の過労で脳溢血に倒れ、車椅子の身となった。
それでも、夫・亮一の死後、六年間、懸命に学園運営に尽力した。
【 五 】
そして、昭和十九年一月二十四日、激しい戦火のもとで数人の保母に看取られてこの世を去った。
享年82歳。
不思議なことに、すでに息のない筆子の閉じられた両目から止めどなく涙が流れ出てきて、拭いても拭いても溢れてきたという。
空襲で命を落とした学園児達を思う涙か、世の中の不理解や経済的困窮の中、気丈にも学園を守り通した筆子の、「もう泣いても いいのね……」という声が聞こえてくるような最期であった。
龍も慟哭したのか、その日は豪雨であったという。
現在、滝野川学園に、筆子が持って来たピアノが残っている。数年前、傷んだ箇所を修復し、立派に弾けるようになった。
中央にガラス版が埋め込まれていて、天使の姿が彫りこんである。これをいつからか、「天使のピアノ」と呼ぶようになった。現在、筆子の志に賛同する音楽家達が、学園でしばしば演奏会を開いている。
ピアニスト西山淑子は金子みすずの詩に曲を付け、学園の子供たちと歌った。
「みんなをすきに」 詩 金子みすず
私は好きになりたいな
何んでもかんでもみいんな
ねぎもトマトもお魚も
のこらず好きになりたいな
うちのおかずはみいんな
かあさまがお作りになったもの
私は好きになりたいな
だれでもかれでもみいんな
世界のものはみいんな
神様がお作りになったもの
梅雨が明けると島原は一気に気温が上がる。三十度を越える時もしばしばある。各家は冬の障子を外し、軒掛け簾を張り、座敷には蚊帳の用意をする。宇土熊野両神社から湧き出る水を途中で灌漑用に使いながら、街中の家々は庭の池に引き込み冷気を貰ったあとまた外に逃がす。
島原の生活はすべて「湧き水」と共にあった。この地の風土は「水」を抜きにしては語れないのである。
そんな、夏の始めのある日、「奥さま~っ!」と血相を変えて、手代の安吉が奥へ飛び込んで来た。
【 六 】
「一体、どうしたのです?」
「敬愛さんが!」
「何があったの?」
「知らない少年が来て、敬愛さんと何か話しておられて……話し終わるや否や、敬愛さんが、一目散に駆けて行きました」
小夜は廊下に立ち尽くしたまま、敬愛が信平の元に来た経緯を改めて思い浮かべていた。敬愛は島原より半島の南にある布津村の旧家の出身で、代々禁制の日蓮宗「不授不施派」を信仰していた。信平が半島にて布教活動をするという本部の知らせに接し、父は敬愛を信平の元へ行かせた。
昼下がり、敬愛が店の商品陳列を整理していると、「敬愛さん、いますか?」と一人の少年が訪ねてきた。何か思いつめている感じである。
「私だが……?」
「あんたが敬愛さんか?」
「そうだ。で、君は?」
「布津の山田の息子、一雄」
「山田といえば小作の、あの奈緒のところの?」
「うん」
「で、俺に用とは?」
「奈緒ねぇちゃんが……、ルソンに連れていかれる……!」
「えっ、奈緒が、ルソンに!」
「ねぇちゃんば、助けて!」
「……よし、行こう!一雄、案内してくれ!」
二人は布津に向けて走りだした。
島原往還を南に向かって、白池、今村刑場横を通って一路布津に向かった。
道々一雄が云うには、去年の飢饉が引き金になって生活が一気に苦しくなり、父親は借金がかさんできて、にっちもさっちもいかなくなったという。そんなある日、高利貸しが「娘をからゆきさんにすればよか。借金なぁ、すぐ返せる」と父親に持ちかけた。
父親は悩んだが思い切って云うと、奈緒は「よかよ、うちは」とあっさりと承諾した。母親は一晩中泣き明かしたという。それでも一雄は諦めきれず「あの敬愛さんなら、支度金九十円をなんとかしてくれる」と、いよいよ奈緒の出発前日に島原に走った。
お金もさることながら、一雄は日頃奈緒が何かと云えば「敬愛さんはね」とか「敬愛さんなら」と云うのを聞いていた。十五歳の少年ながら姉の敬愛に対する気持ちが分かっていたのだ。
「ねぇちゃん、敬愛さんは島原におるとじゃろ? 会いに行かんと?」と聞くと、
奈緒はうつむき加減に云った。
【 七 】
「出来んとよ……」
「なんでね?」
「身分違いやもん」
「学校の先生は四民平等と云うとったばい」
「うちは古か人間けん、出来んとよ……」
という奈緒に一雄はじれったさを感じていた。
今回の事も、自分は勿論「からゆき」なんか絶対いやなのに、父親の頼みには断りきれない姉であった。いつも自分の思いは脇に置いて生きてゆく姉であった。
奈緒は地主である敬愛の家、島崎家へ奉公に出ていた。賄の手伝いで、敬愛の母の指示の元、日々の食事を作っていた。奈緒は島崎家に慣れるうち、自分と年の近い敬愛と次第に打ち解けていった。
それゆえ十年前、敬愛が父の命で信平の元へ行ったとき奈緒は体の芯にぽっかりと埋めようのない穴が空いたような気がした。我知らず、奈緒の心には「敬愛」に対する思いが、伏流水のように静かに流れていたのだ。
この時代、明治中期に、所謂「からゆきさん」は東南アジアを中心に約五千人いたといわれる。この内の半数以上は島原半島と天草出身者であった。とくに島原半島は普賢岳のふもとのシラス台地で農耕に適さず、そのうえ台風も多く、農民はとことん貧しかった。
-
姉しゃんなぁ どけいたろか
姉しゃんなぁ どけいたろか
青煙突のバッタンフル
唐はどこんねき
唐がどこんねき
海の果ばよ しょうかいな
-
山ん家 はかん火事げなばい
山ん家 はかん火事げなばい
サンパン舟はよろん人
姉しゃんなぁ にぎん飯で
姉しゃんなぁ にぎん飯で
船ん底ば しょうかいな
【 八 】
村はずれにある粗末な藁葺家が奈緒の住む家だった。
「一雄、奈緒を連れて来い!」
「うん!」と一雄は一目散に家に向かった。
敬愛は少し離れた木陰から様子を見ていた。
ややあって、家の裏手から二人は出てきた。敬愛は自分を捜している一雄に無言で手を振った。
奈緒が来た。十年振りの再会に眼を輝かせていた。
「敬愛さん……!」
「うむ」
奈緒の目が潤んだ。
「一雄、先に島原に戻れ、奥様に杉谷の権現様に居ると伝えろ」
「分かった!」と一雄は走りだした。
「奈緒、行くぞ」
「はい、でもお父さんが……」
「なんとかなる!」
「……」
敬愛は奈緒の手を取って、島原を目指した。夕刻まではなんとしても島原に着かねばならない。なんとしても。
二人は、追っ手を避けるため山道に向かった。布教で師匠に付いて、幾度と無く半島内を歩いているので、敬愛にとっては造作もないことだった。
夕刻、権現神社に着いた。小夜はまだ来ていない。
神社奥の池から清冽な水が湧き出し、境内に沿った川を滔々と流れ、田畑を潤し、お城の掘りに流れ込んでいた。
二人は、流れに足を浸した。
「気持ちいい……」
「気持ち いいなぁ」
「はい、私、久しぶり……」
「なにが?」
「ほわっ としたの……」
「……奈緒、俺と信平さまにお世話になろう」
「それは、敬愛さんのいいつけですか?」
「いゃ、それは……」
「奈緒は敬愛さんの家で働かせてもらっていました」
「よく働く娘だったなぁ」
【 九 】
「だから、おいいつけなら、そうします」
川風が二人の髪をそよいでいった。誰かが拝殿の鈴を鳴らした。
「奈緒、いいつけだ」
「はい!」


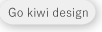 クリック!
クリック!



 トップ
トップ