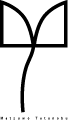2014年10月
リストランテ・アルレッキーノ

まぎれもなく、島原一押しのレストランだ。気品に溢れている。
地元の豊かにして安全な食材を、おいしく、なおかつハイコストパフォーマンスで提供してくれる。野菜が苦手な息子でさえおいしさを絶賛する。従業員のサーブも洗練されている。周囲は豊かな緑。
こんなレストランが存在すること自体、一種の奇跡だと思う。
ランチが11:30-14:30、
ティータイムが14:30-16:00、
ディナー(金・土・日、要予約)が17:30-20:00。
コースのみの提供。この場に沿う客層を選択的に入店願うにはやむを得ない選択だと思う。予約して出かけて行ったがいい。
閉店。
解明されていく脳
映画『LUCY/ルーシー』。10%程度しか機能していない人間の脳が、100%へ近づいて覚醒し超能力が使えるようになるヒロインの映画らしい。
「人間の脳は10%程度しか機能していない」説はウソ
やれやれ。「人間の脳は10%程度しか機能していない」説はウソ。以下、wikipedeiaから転記。-
「約300億個の神経細胞を含むがそれは脳をなす細胞の1割程度であり、残りの9割はグリア細胞と呼ばれるものである。グリア細胞は神経細胞に栄養を供給したり、髄鞘を作って伝導速度を上げたりと、さまざまな働きをする。「人間は脳の1割ほどしか有効に使っていない」という俗説があるが、これはグリア細胞の機能がよくわかっていなかった時代に、働いている細胞は神経細胞だけという思い込みから広まったものと言われる。最近では脳の大部分は有効的に活用されており、脳の一部分が破損など何らかの機能的障害となる要因が発生した場合にあまり使われていない部分は代替的または補助的に活用されている可能性があると考えられている。」
脳を100%フル稼働すると餓死する
けれど、脳の大部分が有効に活用されているということと、一気に100%フル稼働するということは別問題。もし人間の脳をフル稼働させると人間はどうなるのだろうか。答えは「餓死する」。脳が使うカロリーは大きい。人間の脳が常にフル稼働することになると、消化吸収器官がカロリー供給について行けず餓死するという。脳機能の解明に向けたビッグプロジェクト
では、脳はどのように働いているのか。これが十分に分かっていない。世界はこの解明に向けて動き出している。一般にはあまり知られていないようだが、2013年に脳機能の解明に向けたビッグプロジェクトがEUとアメリカでスタートしている。EUのものは「Human Brain Project(HBP)」。人間の脳の機能と仕組みを可能なかぎり忠実に解析し、2020年までに人間の脳をスーパーコンピューター・クラスターでシュミレートする。予算は10年間で総額約12億ユーロ。
アメリカのものは「Brain Activity Map Project (脳行動マップ・プロジェクト)」。統合失調症や自閉症など精神系にも関わる研究も対象で、この他アルツハイマー病やパーキンソン病などの病理解明も目標となっている。このプロジェクトには国防高等研究計画局も絡んでいる。予算はヒトゲノムプロジェクトに投入された予算を上回り、10年計画で総額は30億ドルを超えると思われる。
このような動きを受け、我が国も今年度「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」を推進し始めた。以下、サイトから転記。
-
「文部科学省では欧米の動向を踏まえ、我が国が強みを持つ霊長類(マーモセット)の遺伝子操作技術、光学系技術等のさらなる効率化・高度化を行うことにより、霊長類の高次脳機能を担う神経回路の全容をニューロンレベルで解明し、精神・神経疾患の克服につながるヒトの高次脳機能の解明のための研究開発・基盤整備を加速させるため、平成26年度より「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」を開始することとしました。」
Glass brain flythrough
実際の脳波信号の活動をリアルタイムに捉えた、解剖学的にリアルな3Dの脳。シータ波、アルファ波、ベータ波、ガンマ波と、脳領域間の情報伝達が光パルスとして可視化されている
アルミのリサイクルでつくるスツール
バーカバノンにぴったりとマッチするスツールのことをいつも頭の片隅で考えています。そんなこんなで脳味噌のアンテナを立てていたところ、面白いプロジェクトがかかってきました。
それはデザインプロジェクト「CAN CITY」。ブラジルで非公式労働者たちがアルミ缶などを回収し、リサイクルしてアルミスツールをつくっているとのこと。

3:43あたりに完成したスツールが出てきますが、この材質感がバーカバノンにマッチしそうで魅力的です。里山でチャレンジしてみたいのですが。アルミニウムが溶ける温度は660℃。鉄が溶ける温度は1534℃。容器は鉄製でOK。と調べていくうちに、必要な量が半端ではないことが分かり断念。
ちょっとグッとくる言葉
ずいぶん前に気がついたことだが、物事を成し遂げる人たちは、座ったままなにかが自分に起こるのをただ待っているということはない。彼らは外に出ていって、自らそのなにかに飛び込んでいくのだ。 レオナルド・ダ・ヴィンチ
いつも顔を太陽のほうに向けていなさい。そうすれば、影はあなたの後ろにできるのだから。 ウォルト・ホイットマン(アメリカの詩人)
だってさ。
言葉の力
ジャネの法則
歳を重ねるにつれ時の流れが早く感じる
ジャネの法則は、歳を重ねるにつれ時の流れが早く感じるというもの。心理学者ピエール・ジャネはこう言いいます。6歳の1年は、人生の6分の1。けれど60歳の1年は、人生の60分の1。だから年齢を重ねるほど短く感じられると。子供の頃は新鮮な驚きに満ち溢れていますが、人生で新しい局面に出会わなくなれば単調になり1年は早くなるわけです。
家と職場だけを行き来している人、振り返るとこの3か月で初顔あわせした人がいない人。そんな人生つまらないでしょう。
遊びをせんとや生れけむ、戯れせんとや生れけん。
地域移住
地域移住を希望している20歳代は4割
地域移住を希望している20歳代は4割近くになっている
ことをマスコミが盛んに取り上げ始めた。しばらく続くだろう。そう、若者よ、豊かさは地域にあり。来たれ。
内閣府が9月に発表した「農山漁村に関する世論調査」がこの発信源だ。
覚えておいでと思うが、5月に発表され話題となった消滅可能性都市とからんでいるだろう。消滅可能性都市とは「これから人口が減っていけば消えてしまう都市が表れる。それを見るには主に子どもを産む20~39 歳の女性の人口の動きを見ればいい」というものだった。発表したのは日本創生会議。実はこちらも内閣府の取組(こちらをご覧いただくと内閣府「地域の未来ワーキング・グループ」の第4回会議に日本創生会議あり)。
マッチポンプというやつだ。これを5月に出して、今度は9月に対策を出す。日本の官僚は考えているなと思う。諸外国の官僚に比べると優秀だ。
地方議員の粛清
掲示板での散人さんが7月に書かれたこの視点がキーだ。-
「地方議員の粛清が続くのは訳がある。それは平成の大合併から10年経過し、 本年度から交付金が縮小されるが、まだバカな議員たちは以前の夢(使いたい
放題の)覚めず、予算の合理化をしようとしない。 そんな輩への中央からの「お灸」をすえられているのだ。 バカ首長や議員の摘発はまだまだ続くだろう。」
消滅可能性都市のウソ
さらにこちらの木下斉氏のツイートを読むとよく理解できるかもしれない。要点は「消滅可能性都市のウソ。消えるのは、地方ではなく「地方自治体」である」ということ。皆さんの多くは、政府が人口減少に伴いコンパクトシティの方向に舵を切ったことはご存じだろう。結局はこの軸を中心に大きな潮流が渦巻いていると思う。
テオ・ヤンセン
テオ・ヤンセン展が長崎県美術館で開催されています。10月9日(木)-12月7日(日)
以前から好きな作家で、開催してくれた長崎県美術館に感謝。

13日は作家本人もいらっしゃいました。気さくな方で、サインをいただき、写真にも私と一緒に納まっていただきました。写真をよくご覧いただけばお分かりのとおり額に生傷。こちらで組み立てる際の災難でしょうか。

作品はその有機的な動きと形態もさることながら、実際に接すると写真のとおり半端ではない手作り感がその魅力の一つとなっていることが分かります。

こんな感じでスタッフの皆さんがソリャッと気合を入れてデモンストレーションで作品を動かしてくれます。容量感が半端ではありませんので、鑑賞者からため息が漏れます。写真もフラッシュなしで可です。
印象的だったのは、県美のスタッフの皆さんが活き活きとされていたこと。それは館内全体に満ち満ちた活気であり、訪れる私たちも楽しくなるものでした。展示作家によってこれほど美術館が変わるのかと感銘深く拝見してきました。
アルヴォ・ペルト
今回の世界文化賞が発表された。音楽分野で受賞したのはアルヴォ・ペルト。
ペルトの音楽↑を聴いて驚いた。こりゃイーノとハロルド・バッドによるアルバム『鏡面界』だ。私が最も敬愛するアルバムとして挙げている一枚。
台湾かき氷

「今日のお昼はスパゲティ」的記事は極力避けている。クダラナイからだ(ここまで書いたところで少なからぬブロガーを敵に回したことだろう)。
けれど本日はそんな食い物の話だ。
びっくりした。はじめての食感だった。長崎で食した。家人によると台湾かき氷は今夏話題になっていたらしい。「台湾かき氷 長崎」で検索すると店の名前も出てくる。
芹沢銈介美術館
長崎県で一番好きな建築をあげるならば親和銀行本店だ。設計者は崇高なる建築家 白井晟一。

静岡市内で最も感銘を受けたのは芹沢銈介美術館。ここも同氏の手による設計。白井氏のつくった知的にして上質な空間に包まれている至福。展示内容の芹沢氏ゆかりの品に惹かれなくとも、出かけるべし。どなたが訪れても建築の力とはかくたるものかと圧倒的力を持つ。静岡のおすすめポイント。ちなみに隣接して登呂遺跡がある。
今回、改めて白井氏について調べてみた。確かに不可解さのある人物である。


 ホームページは欲しいけれど、高いのは勘弁してほしい。
ホームページは欲しいけれど、高いのは勘弁してほしい。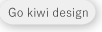 クリック!
クリック! トップ
トップ オススメ
オススメ 記事一覧
記事一覧 掲示板
掲示板 長崎マニアックガイド
長崎マニアックガイド 長崎の酒場
長崎の酒場 長崎を歩く
長崎を歩く 長崎キャンプ場
長崎キャンプ場 長崎インターネットラジオ
長崎インターネットラジオ 私の隠れ家
私の隠れ家 私の家づくり
私の家づくり デザイン
デザイン 絵
絵 音楽
音楽 小説
小説 メール
メール  リンク
リンク