Zone

7 聖塔ロゴス
アーケードが見える。雑踏が聞こえる。わずか三日ぶりというのに,数年間の長旅からの回帰のようだ。夜の帳に紛れ,白い息を吐きながら僕はじっと男を待った。店舗の灯が消え,ドアが開く。十分に距離を取って,僕は帰路についた頼りない足取りの男をつける。
漂う残り火の臭いが,退廃的に甘い。焦げ落ちた壁面。ひび割れ煤けたガラスのタイル。テロによるアーケードの破壊の様は,想像以上だった。財を一夜にして失った人々は忘却を呼ぼうと,手の届く快楽に唾液を滴らせていた。
量も被害の大きかったメインアーケード。そこでは冷えた路上で,薄汚れた仮面舞踏会が繰り広けられていた。廃嘘の中にあてどなく漂う彼等は,夢の足跡を捜していた。
周囲を見渡す。大丈夫だ。僕は声をかける。
「マスター」
僕を認めると,彼は一瞬怯えた目をした。
「沢田くん……。やあ」
彼は足をふらつかせる。わずかの間に,彼はずいぶんと療せた。「沢田くん,なにやった?マーゼンが君のこと,尋ねて来たよ。もう何度もさ」
「……妖精は?」
「みんないなくなった。ヨウちゃんは行方知れずだし,フジノさんは死んでしまったし……」
「死んだ?」
「ああ,ゾーン祭のテロでね。ペルモスのやつら……」独言のように彼は,呻いた。
「元気を出して,マスター」
「元気さ」
彼の声が,アーケードの裏道に虚ろに消えた。
「沢田くん」
「なんだい,マスター」
「なにか楽しいことないかなあ」
「また来るよ」
背を丸めて,あてどなく人気のない裏道を歩き続けた。時々ポケットに入れた手を揉む。
「おい!手を挙げて壁に寄れ!」突然前方に現れたモヒカンの男が,銃を向けて顎をしゃくった。「ドラッグ置いていきな,持ってるだろう?」
僕は思念する。〈退け……〉
男は床に転がり,銃が宙に舞う。慌てて男は,ナイフを手にする。ナイフは,次の瞬間紛々に砕け散った。ヒッと声を上げたまま,男は身を凍らせる。僕は男の目をじっと見た。漏れ来る舞踏会の音色,酔いどれの罵声,女の絶叫,歓声,げびた高笑い。胸の内から込みあげる虚しさ。男は,僕に狂人を見る目を投げながら逃げ去る。
気付くと,聴きなれたフレーズが,細く流れていた。「フール・オン・ザ・ヒル」,僕が「外」の世界で聴きなれていたビートルズのアルバム「マジカル・ミステリー・ツアー」の中の一曲だ。懐かしさに音源を求め,大通りに出る。
とあるブティック前のジュークボックスだった。人混みを抜け,老婆の肌のように細かい錆がふいたそのボディに触れる。
……He never listens to them
He knows that they're the fool's……
僕の前で,ジュークボックスはそう歌ってくれた。
とても侘びしかった。
気持ちは解るよ。僕はジュークボックスに語りかける。でもね,それだけじゃダメなんだよ……。
「私,近頃よく聴くの,その曲」
背後で声がした。
振返った僕に,おどけ顔の妖精がヤッホーと囁いた。相変らす軽いノリだ。まいる。
◇
深呼吸を繰り返すかのように一定間隔で,サンゴは夢見色の青緑がかった輝きを放っていた。マンホール。奥へ奥へと方向感覚がきかなくなるほど分岐しながら進んだところに,薄汚れた彼女達のアジトはあった。
これまでの顛末を話し終えると,僕は熱いコーヒーを飲んだ。どこからか,すきま風が吹き込んでいる。
「お仲間は何人?」彼女に尋ねる。
「隣の部屋が集会場なの。三十人ほどいるわ」
「今までここが,よくバレなかったね」
「住所登録しないことがコツよ」
「なるほど」僕はなんとなく嬉しい。
ジーンズにブルゾン。小さな咳をする彼女は,ファッショナブルな身なりを捨てていた。
「あなたと暮らしていた頃,電話はここからかかってきてたの」しばらくして彼女は,言葉を置いていくように話を始めた。
「マーゼンの動きがおかしくなっていたのは知ってたわ。もうかなり前にね。このレジスタンス運動はそうした頃始めたの。人間は迷いすぎるのよ。私達形成人は迷わない」
「迷路には住むけどね」
妖精は,フフフと下を向いて力無く笑った。「形成人はね,家族がないでしょう。あなたたちのように,家族を捨ててきた人達とは違うのよ。私達は形成され生まれ出たとき,この世に捨てられたようなもの。いくら私を形成してくれた人が愛してくれても,根無し草だわ。帰るところがあるから,旅は楽しいの。分かる? 私達には帰るところがないの」
長いコードに下がる電球から,ジジジという小さな音が聞こえた。
「アーケードだけが私の場所。でもそこに帰れるところはなかったの」彼女はもう一度そう言った。視線を外して,彼女は独り言のように話し続けた。
「一人暮らしは,なにもいいことがなかった。疲れても一人。咳をしても一人。帰ってきてドアを開けても,私を待っているのは陶磁器のように冷え切った部屋の空気だけ……。この運動に出会ったとき,やっと見つけたと思ったわ,仲間をね。でも,あなたとの暮らしは別。あなたと暮らし始めたとき,本当に楽しかったのよ,私。自堕落な生活の中で,私は豊かになっていくようだったの。分からないでしょうね,こんなこと言っても。楽しかったわ,本当に」
「僕も,あれから君を探し続けていたよ」
「私はわがままで,あなたに何ひとつしてあげられなくて……」
「愁傷なこと言わないでくれよ。レジスタンス活動に尽くしてたなんて,知らなかった」
「『外』に出たかったの。いつもそのことを考えてた。覚えている? 緑色のワニの話よ。でも形成人には許可されてないでしょう」
「出たかった?」
「ええ,青い空を見たかったの。でももう今は違うわ……。ここを変えるの。仲間達とね。不潔だけれど逃げたくないの。もう退けないところまで来たわ」
「できるかい?」
「やるわ。形成人も,人を愛することはできるし,憎むことだってできるわ」
「分るよ」
「あなた,別れた頃と少しちがう」
「イワサキさんや,ゾーンと出会ったからかな」僕は冷えたコーヒーを啜った。
「ゾーンの侵略にあって帰ってこれたなんてね」
「イワサキさん,無事だといい」
彼女は少し微笑んだようだった。
「イワサキさんは正直な人よ。正直な人だから,生き急いでいたわ」
「詳しいね」
「私を形成したのは,彼よ」
一瞬僕は息が詰った。彼女は重要なことを,唐突に言いすぎる。
「僕は自分に欠けたものを想い,君を形成した。よくそう言ってたわ。そして自分の欠落である私を抱いてたの。それは可哀想なほど不器用な愛し方だったわ。私は嫌だったの,彼が自分の教条と,私の間で悩むことが。息が詰まるように正直な人だった……。別れた理由を聞きたい?」
「悲しい言い方は,よしなよ」
「あのね。性善でも,性悪でもないの。私達は本当に性弱なだけなのよ」その時,僕は知りあって初めて彼女の涙を見た。「彼はもう死んじゃってる。分るの……」
彼女に渡したイワサキからの預かり物。それは聖塔ロゴスの住民登録室に至るマニュアル書だった。ヘルメットを被ることで,短命さを克服できるかもしれない。そんな噂が形成人には昔から伝わっていた。けれどそれをやった形成人はまだいない。聖塔ロゴスへの立ち入りが,形成人には禁じられていたからだ。「生きるんだよ」イワサキが,妖精にそう囁いているようだった。それを見て,妖精は声を出して泣いた。俯しながら震える背中は,普段気丈なだけに正視してはいけないもののように思えた。薄暗い部屋の中で,彼女はとても小さかった。
長いコードに下がる電球から,ジジジという小さな音が聞こえ続けている。時間は哀れなほど重く長かった。
彼女はポツリと呟いた。「ヘルメットを被るわ」
「僕も一緒にいくよ。一緒に被ろう」
「おせっかいね」
「違うよ。決めていたことさ。イワサキさんから,君へのプレゼントを預かった時からね。僕自身の問題なんだ」
僕はなにも知らない。だからこそ進みたい。この街を変えよう。そう,思った。
◇
午前二時。聖塔ロゴス前の広場は,巨大化をもくろむ都市の超然さを満々と湛えていた。強いライトを受け光沢を放つ白磁のタイルが,その桁外れの遠近感を消失させる。無菌室のような近寄りがたさ。パトロールがブーツの音を響かせる以外,人影は見当たらない。植え込みに身を潜める僕と妖精。小銃を持つ手に汗が滲む。パトロールの目を縫って,僕等は匍匐を繰り返す。
三十分ほどの息詰る時間を抜け,塔の左側面にある通用口に至る。間に合った。イワサキがくれたマニュアルによると,ここは時間外の出入りに使われており,三時から守衛は見回りに出かけるらしい。小銃を握りしめる。スチール製のドアを静かに開け,中をうかがう。息をついて,彼女に合図を送った。
気配なし。通路を縫う。排気管を這う。階段を上る。セキュリティの配線を切る。イワサキの書き残したマニュアルに従い,僕等は分刻みで事を進める。目指すは住民登録室。パトロールと出くわすことがない。防犯ブザーはならない。完壁なマニュアルだ。
そして,僕等は住民登録室に至った。
◇
暗闇にマシンのランプ群が,色鮮かに浮き上る。
横一列に並び,僕等を待つシート。
「本当にいいんだね?」
僕は彼女の瞳を真正面から見詰め,もう一度聞いた。
「……早くヘルメットを」
シートに深々と身を横える妖精。彼女の額には,うっすらと汗が光る。
「なにかあった時は,私の仲間達に伝えて。形成人には,住民登録なんて無理だったって」
「うまくいくさ」僕は微笑み,彼女にヘルメットをわたす。
「いいね?」
操作室に入ってタイマーをセットし,赤く輝くスイッチに指を添える。僕は祈った。……いくよ……心の中で呟き,スイッチを押す。
急いで元の部屋に戻ると,僕は妖精の隣のシートに滑り込み,ヘルメツトを被った。妖精は,ねえ,と言うと,腕をのばして僕の手を握りしめた。
肩の力を抜く。
マシンの壁面が微かに唸る。
頭の中でなにかが光った。続いて意議が地滑りを始める。ひどい気分だ。
突然,警報ブザーが鳴り響く! 妖精が叫ぶ。「バレちゃった。追手がやってくるわ!」
カットした配線が見付かったのだろうか。
「大丈夫。すぐにここだとは,奴等もわからない」
マシンが唸りを高める。
「ここから生きて返れたら,なにしたい? 」
「君の肩叩きでも」
「約束よ。ありがとう」
警報ブザーの中,僕は彼女の手のぬくもりを感じていた。
◇
脈動し始めたビーズ球ほどの意議。堅く透明な氷山をスルリと滑りぬけると,柔かい芳香を放つ湖に揺れながら沈んでいく僕と妖精。
湖の底は,複雑な基盤でびっしりと埋めつくされていた。
「ようこそ,C5。5201年間,お待ちいたしておりました」
マシンの声がこだました。
途端に,僕等は凄まじい力で,上方へと射ち上げられた。
妖精が叫び声を響かせる。
湖を抜け,次いで住民登録室の金属製の天井をすり抜けた。
複雑なプリズム光の満ちたロゴスの塔の内部。僕等はその只中を,天才のインスピレーションでもあるかのように過激な早さで上昇していく。
「飛んでるわ!」妖精が興奮した口調で叫ぶ。
周囲に見える螺旋階段。その中心にどこまでも伸びた空間。僕らの飛翔は限りなく続く。
妖精が飛んでいる。
彼女を見つめる。
彼女は畏怖と歓喜が複雑に交錯した顔をして,僕を握る手に力を込めた。
幾筋者光線が絡み合いながら,降り注いでくる。測り知れぬ遠方から放たれた甘美な舞。光と影が織りなす気まぐれな均衡は,僕の頭部から白い煙を吹き出させる。
「これが伝説の……」妖精はうわずりながら言った。
僕等は金色の光を,満身に浴びていた。
静かだった。
それは寝入りばなの夢の中で味わう安息のような静かさだった。
ずっと上方に巨大な扉が見えた。
扉はやがて僕等の来訪を歓迎するかのように,徐々に開き始める。
扉の向こう側からクリーム色の光が漏れ出す。そして音楽だ。囁くような音楽だ。妖精は僕の肩に抱きつくと,ねえ,と言って息を飲む。
苦しそうに,彼女は肩で息をしている。そしてじっと光を見つめている。
瞳に手を翳す。
瞳孔が光量に追いつかず,よく内部が見取れない。
溢れる光を浴びて,僕はとても懐かしい気持ちになった。
ついに,僕等は弾かれるように扉の内へと入った。
渦を巻く音楽に,光の洪水だ。
噴水のように,微妙に輝きの異なる光の放水が,あちらこちらから起こっていた。
私達とうとう聖地に来たんだわ。ねえ,聖地よ。ゾーンの聖なる高みよ。
僕等はさらに上昇を続ける。
幸せだわ。私の母胎なのよ,この部屋は。私を抱いてくれているわ。
彼女は,僕の胸に顔を埋め,涙を流しているらしかった。
その時の彼女には,刻み込まれたような強い存在感があった。確かな彼女が僕に見えた。「キテヨカッタワ」彼女が呟く。
確かな彼女。
確かな私。
僕達が欲しかったもの。
ペルモス教徒が羨望し,そしてマーゼンが追い続けたもの。
世界よ,かく在っておくれ!
「了解,マスターズナンバー」
声が響いた。
次の瞬間,銀粉が僕の身体から舞い上がる。回りに走る無数のスパーク。まるでさざ波に乱反射する朝日のようだ。彼女が何かを言おうと唇を動かしている。苦しそうな顔だ。音を越えた白色音に覆われ,聴き取れない。彼女は,首を横に振った。口元に耳を寄せる。彼女は,肩を震わせながら,僕にそっと口づけをした。
玄が切れたように,彼女の身体が大きく痙攣した。落ち始める身体。
馬鹿な! 妖精! 妖精! しっかりするんだ!
握りしめた彼女の手首が,冷たくなっていく。
僕の銀色の輪郭も振動を始める。
彼女のほのかな体臭が漂う。
とても幸福そうな顔をして,彼女は僕の顔を一瞬見つめた。
粒子は,きらめき,光が,満ちる。
僕は両腕に満身の力を込め,彼女の身体を抱き寄せる。
途端に,
僕は,
閃光となり,
弾け散った。
薄れていく流木のような意識が,目を開く。
ロゴスの塔を越え,はるか眼下にアーケードのイルミネーションが見えた。数千年間,ゾーンの歴史を覆ってきた霧が,今晴れていこうとしていた。
妖精……
僕はもう一度叫んだ。
妖精!
 ホームページは欲しいけれど、高いのは勘弁してほしい。
ホームページは欲しいけれど、高いのは勘弁してほしい。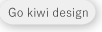 クリック!
クリック! トップ
トップ オススメ
オススメ 記事一覧
記事一覧 掲示板
掲示板 長崎マニアックガイド
長崎マニアックガイド 長崎の酒場
長崎の酒場 長崎を歩く
長崎を歩く 長崎キャンプ場
長崎キャンプ場 長崎インターネットラジオ
長崎インターネットラジオ 私の手作りキャンプ場
私の手作りキャンプ場 私の家づくり
私の家づくり デザイン
デザイン 絵
絵 音楽
音楽 小説
小説 メール
メール  リンク
リンク


