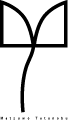1998年8月
くさや
くさやを,初めて食べました。
友人から電話がかかってきて,「まつをさん,くさやを貰ってきたので食べよう」とのこと。![]()
くさやは,臭いので有名。先日,行きつけの店のマスターが言うには「焼き始めると便所の臭いがする。火が回ると糞の臭いそのもの」という話を聞いたばかり。友人宅で七輪に火を起こしました。そして,くさやを焼く。とたんに友人はオエッという声をあげました。結局,私は大丈夫でした。美味くも不味くもない食い物というところです。臭いはたしかにします。くさや=糞=マルタイ屋台ラーメン(すみません,ローカルで),の図式が頭に浮かびました。写真は,友人が一口食べたところ。そう言えば私は,ドリアンも大丈夫。ある本にドリアンは「朝潮の靴下の臭い」と表現してありました。私としては,プロパンガスが漏れた臭いというところ。
現世と来世
お盆の日に書いた記事について,日本の宗教事情を研究しているあるお坊さんから以下のような解説を頂きましたので紹介します。
--------------------------------------------
後世は、現世の延長線上。したがって、後世とは、現世の未来のこと。来世は、現世とは全く切れています。つまり、無関係、ということ。
後世を構成するのは、現世の人間の記憶です。別の表現では、歴史です。中国人は(小室直樹によると)歴史による救済が目的だそうで、如何に歴史に名を残すか、それは とりもなおさず今生きている人間に、如何にして自分の名と業績を記憶させるか,そして、それを歴史に留める(ということは後世へも記録として残させる)か、これが眼目だそうです。
自分の肉体の死後、自分に関する記憶が、自分自身も含めて、現世から一切消失してしまうのは耐えられない! 漢民族の死後観は、現世を生きるための手段である肉体と魂が分離し、いわゆる死を経た後も、 肉体の根元(である 魄 )と 精神そのものである魂とは,つねに(分離したままではありながら)この世(=現世)に留まる。
後世 も 現世 も 同じ世。ただ、自分の 肉体と精神の状態が違う。 それが現世 と 後世 の差です。
世間という 器 を支えているものは 人間です。もっと言えば、人間の記憶です。この記憶がある限り(つまり 覚えていてくれる人がある限り )「生きている」のです。ここに、仏教的なニュアンスを含めて言えば…… 「かわいそうに、 織田信長は400年経っても まだ、 死なれない。死なせてくれない」。この「かわいそうに」というところが大切なのです。来世に行かないから、現世のままで評価 にさらされる。なぜなら、人格の連続性を保持したまま、行動の手段である肉体と精神を消失しているから。評価を逆転させる 行動( たとえば 裏話のリークなど )を取れないから。
平和5原則
皆さんは,平和5原則というのを憶えていらっしゃいますか?教科書にも載ってました,あれです。
①領土・主権の相互尊重 ②相互不可侵 ③内政不干渉 ④平等互恵 ⑤平和共存
1954年中国の周恩来とインドのネルーの共同声明として発表したものです。
「アメリカではこうなっとるから,日本もそうなるべし」論
おととい,久々に例の「アメリカではこうなっとるから,日本もそうなるべし」論を聞きました(笑)。「アメリカではこのような教育法をやって,日本より30年進んでいる。日本も追いつかねば」という論調でした。ところでアメリカの教育現場はどんな状況になっていましたっけ? 30年進んでいると言うことは,今日本でその教育法を取り入れた場合の,30年後の姿をアメリカに見ることが出来ると思いますが。
「人生なんて糞だ」と言った人
「人生なんて糞だ」と言った人がいました。たぶん[その人の]人生は糞だったのでしょう。
私たちが人生を語るとき,それは「自分の人生は」という条件がついてまわっているのです。「諸君,人生というのは……」というフレーズもそうです。ここが人文的世界の滑稽なところでもあり,面白いところでもあります。それでいいのです。語る人が上記の点を理解して発するのならば,それは勇気であり,それなくして私たちは触発されないのです。自己表現たる芸術が是とされるならば,人生観の吐露は否定されるべきではありません。過度の懐疑や斜視は生むものがなくなります。
それにしても,どうして評論家というのは,ああも小綺麗な格好をしているのでしょう。創作者の現場というのは,常に混沌としていることを考えると,いかに彼らは安全圏にいるかがわかります。
クリントン大統領の不倫
今は昔,宇野という総理がおりました。彼は「不適切な関係」を持っていたが故に,その職を追われました。このスキャンダルが出たとき,USAの某ジャーナリストは「わが国で,かようないかがわしい行為を政治家が行うことは,その政治生命を失うことだ」といった旨を述べ,日本社会を未発達なものとして批判しておりました(「そうか?」と当時思ったのでよく憶えているのです)。
さて今回フリントン,もといクリントン氏の一件が出ました。さあ向こうの番です。彼の地の民主社会のお手並み拝見といきましょう。
日本人の死生観
お盆にちなんだお話を書きます。
インド仏教では死者は49日後に転生する
インドでは死者は49日後に他に転生すると信じられております。ですから基本的に墓がありません。もう他のものに生まれ変わっているわけですから,墓は必要ないという捉え方です。
日本では49日は序盤戦で,それから何度も法事を行っていきます。このように日本の仏教はインド感覚のものとずれがあります。
中国の儒教では転生せず天に溜まる
儒教では,人が死ぬと,魄と魂に分かれると捉えられています。魄つまり肉体は地行き,魂は天に行くのです。そして魄と魂が合体すれば,復活があるとされ,そのため古代一族の長は,重大な決断を下さねばならぬ時,シャーマンとなって魄である先祖のシャレコウベをかぶり,魂を呼び寄せ,祖先の決断の言葉を聞いたと言われます。これが儒の初期の形です。そしてもう一つ大切なことがあります。儒教は輪廻思想を持ちません。祖先の魂はたとえば空の雲の上にずっと増え続けて行くわけです。ですから,子孫を絶やすことは一大事なわけです。なぜならば祖先と自分の魂が路頭に迷うからです。脈々と一族の流れは絶やしてはならず,魄を納める墓も重要と言うことになります。
日本仏教はインドと中国のミックス
日本の仏教は,このようなインドと中国の来世観がミックスされ,さらに道教や神道が入り組んでいるのです。現代日本の仏教者の本が,原始仏教について述べるとき歯切れが悪くなるのは,こうした背景があるのです。
日本の死者は成仏していないのか?
それどころかギボアイコ氏が「あなたの肩のところに,亡くなったお爺さんがいらっしゃいます」などと発言するテレビ番組が,かって高視聴率を取っていたと言うことは,日本人の多くは,お盆に限らず祖先の霊が自分の身近にいると信じているのかもしれません。というのも先ほどの発言は「あなたのお爺さんは成仏していませんよ」ということなのですから(この成仏という言葉も多くの日本的特色をしょっています),これを聞いて怒らないということは,もともとそういう世界観を持っているということなのでしょう。しかし,ミックスされた仏教などおかしいじゃないかという発想も短絡的です。本来,文化とはその地の人々が持つ共通したタブーなのであり,その地ごとに根付いて行かざるを得ないものなのです。それぞれの形があって文化なのです。
林羅山の選択
お盆になると,江戸儒学の祖,林羅山のことを思い出します。
彼は幼少のころ仏教寺院で学びました。そのうちに寺が,彼に仏門に入ることを勧めたのです。彼が親(養父母)にこのことを話しますと,涙ながらに止めるよう説得されます。家が絶えるではないかというわけです。以後,彼は仏教が世間を抜けた宗教であると考え,仏教から儒教へ転換するわけです。このことは仏教の根本を示した問題です。
映画「タイタニック」は強欲女の話
映画「タイタニック」を「21世紀の子ども達に残したい100の映画のひとつ」と評した意見がありました。それも「これはスペクタクル映画ではなく,人間の生き様の映画だ」というのです。困ったものです。以下は,もうすこし柔らかく書くべきなのでしょうが,あまりに憤慨しましたので,そのまま書きます。子ども達に残すというのならば黙っておれません。
女性主人公は強欲の塊
ローズ(女性主人公)の生き方が「21世紀の子ども達に残したい」生き方のひとつ? 彼女は,不満を持ちつつも大金持ちと婚約し,彼を毛嫌いしながらも手にしたダイヤは一生ガッチリせしまたままで,知り合った男とはすぐに交情し,そこまでジャックを愛したのなら一生思って生きると思いきや,ぬけぬけとまた他の男と結婚する。このローズは,猿です。目の前にある快楽は喰らい,不快には唾する。そんな人間の生き方を描いた映画が,「スペクタクル映画ではなく,人間の生き様の映画として,21世紀の子ども達に残したい100の映画のひとつ」と評する人は,物事の大筋が掴めない人でしょう。
ところでダイアナは聖女でしょうか?世論はそのように扱っています。私はタイタニックの映画を見たとき,ローズとダイアナがダブって見えてしまいましたが。
チキンラーメンで嘔吐感
事実を淡々と書きます。本日8月7日昼食に日清のチキンラーメンを食しました。賞味期限が1998.8.20でした。現在夕方6時ですが吐き気がして胃の薬を飲みました。
昔,食品には製造年月日がかかれ,そして賞味期間○○日と記されていたのです。これが法改正され,タイムリミットを記すようになりました。つまりいつ作られたのかわからなくなりました。
【問】この法改正は消費者のためになされたのでしょうか?
日本のホテル・旅館は高い
日本のホテル・旅館は高いですね。旅館なんぞは明細書を見せなさいと言いたくなります。この料理はいくらだったの? と。
旅や宿のガイド本も,いい加減にしてくれといいたくなるのがありますね。ガイド本の利用者側と,旅館側の,どちらの方に気配りしながら書いてるんだと。このHPに登場する俵山氏はかつて旅館業を営んでいましたが,ガイド本の取材が来るとなると無料宿泊・飲食の接待をしていました(全てのガイド本がそうか否かは別)。
ガイド本に責任なし だと
ガイド本を書いている方と,このことについて話したことがありますが,彼は「ガイド本でいい宿と記されていて,不愉快な対応しかしない宿だった場合(これは主観のレベルを超えた問題について),それは消費者側の自己責任だ,ガイド本に責任なし」という趣旨を言い放ちました。この点について法的にはどうなっているのか,極めて興味のあるところです。


 ホームページは欲しいけれど、高いのは勘弁してほしい。
ホームページは欲しいけれど、高いのは勘弁してほしい。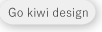 クリック!
クリック! トップ
トップ オススメ
オススメ 記事一覧
記事一覧 掲示板
掲示板 長崎マニアックガイド
長崎マニアックガイド 長崎の酒場
長崎の酒場 長崎を歩く
長崎を歩く 長崎キャンプ場
長崎キャンプ場 長崎インターネットラジオ
長崎インターネットラジオ 私の手作りキャンプ場
私の手作りキャンプ場 私の家づくり
私の家づくり デザイン
デザイン 絵
絵 音楽
音楽 小説
小説 メール
メール  リンク
リンク