雲が流れる。
時が流れる。
時々ススキがなびき、
地球が自転する音を立てる。

君に、とても魅力的な男の話を伝えよう。
けれど知っていたって、何かに役立つ類の話じゃない。彼は、僕の知る人間の中でも、ある意味じゃ最低の部類に入る。モラルは低く、計画性ときたら目を覆うほどだ。女性に滅法ルーズだし、金銭感覚に至っては破綻者だ。
でも彼の生き方を知れば、少しは気楽になれるだろう。結局僕らは生きてるだけなんだと。人生に意味はない。行動だけがそれを作る。定義を先だって求めるのは人の悪い癖なんだと。
彼は僕に「俺が死んだら、骨を拾って海にまいてくれよな」と時々言う。線香に蒸れたような顔をして、彼はそう言う。僕はいつも丁重にお断りしている。惚れた女性に葬式を出させるのが、男子の本懐ってものだ。
ある夜、飲みながら僕はこう言った。
「あんたを書いてあげよう。これで大地に爪痕が残せる」
「いいね」
「よし、出版代はそっち持ち、売り上げは僕がもらう。いい話だ」
この後、一時間程もめた。葬式は出さぬが、話は書こう。
彼の生きた軌跡だ。二つの脳味噌を背負って毎日右往左往する、そんな男の話を君にうまく伝えられたらと思う。
一九八七年。僕は夜明け前のツァラトウストラの心情にあった。
 夢を見た。赤い糸の夢だ。自分の左手小指に結ばれた糸をたどっていく。長い糸を手繰り寄せると、その先にあったのは自分の右手だった。この悲劇的結末に寝汗をかいて起き、職場に行くと転勤を命じられた。てやんでい、と飲みに行く。スナックの猿に似た女の子が「どこに転勤になったの?」と尋ねるので「島原、雲仙の袂さ」と答えると、「連れてって」とその子は目を輝かせ、「お勘定」と僕は席を立った。
夢を見た。赤い糸の夢だ。自分の左手小指に結ばれた糸をたどっていく。長い糸を手繰り寄せると、その先にあったのは自分の右手だった。この悲劇的結末に寝汗をかいて起き、職場に行くと転勤を命じられた。てやんでい、と飲みに行く。スナックの猿に似た女の子が「どこに転勤になったの?」と尋ねるので「島原、雲仙の袂さ」と答えると、「連れてって」とその子は目を輝かせ、「お勘定」と僕は席を立った。
すべてが一旦幕を閉じたがっていた。そこそこ楽しめはしたものの、このままでは何も生まれないとどこかで思っていた。このまま歓楽街の下卑た笑いの中にいても、このまま慣れすぎた職場にいても、このままアパートの冷えたノブを何度回しても、まるでコミカルなビデオを繰り返し見るかのような虚しさが降り積もるだけのようだった。よし行こう。
軽トラック一台で、布団と僅かばかりの衣類を移動させる。それで引っ越しは終わった。
 田舎だ。こりゃあ自然で遊ぶに限る。早速ゴルフ道具一式を購入し、グリーンに出る。ボールはあらぬ方向にばかり飛び、不愉快極まりない。ゴルフなんぞもう一生しないぞと決心しての帰り道、車窓から青い看板が目に入った。
田舎だ。こりゃあ自然で遊ぶに限る。早速ゴルフ道具一式を購入し、グリーンに出る。ボールはあらぬ方向にばかり飛び、不愉快極まりない。ゴルフなんぞもう一生しないぞと決心しての帰り道、車窓から青い看板が目に入った。
「ペンション星のきかんしゃ」
こうして僕らは巡り会った。

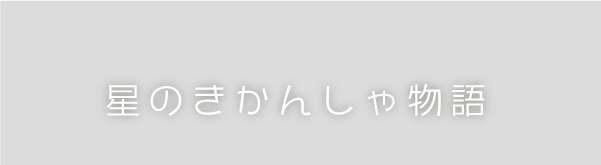




 トップ
トップ オススメ
オススメ 記事一覧
記事一覧 掲示板
掲示板 長崎マニアックガイド
長崎マニアックガイド 長崎の酒場
長崎の酒場 長崎を歩く
長崎を歩く 長崎キャンプ場
長崎キャンプ場 私の手作りキャンプ場
私の手作りキャンプ場 私の家づくり
私の家づくり 長崎インターネットラジオ
長崎インターネットラジオ デザイン
デザイン 絵
絵 音楽
音楽 小説
小説 メール
メール リンク
リンク