久しぶりに、マスターと飲む。場所は居酒屋「きりん」
「実はね」とマスターが笑いながら切り出す。今から何が話されるのか、僕には分かる。電話が一ヶ月近くもない時は、彼が女性にはまっているときか、新規事業にはまっているときだ。
「結婚するよ」
……始まった。カウンターの焼酎をとって呷る。「誰と?」
「いい女がいた」
 「名前は?」
「名前は?」「ヨウコ。福岡に住んでる」
僕はシメサバを注文する。
「何回会った?」
「一回だけどさ」
「ペット、買ってくるのじゃないんだから」
「とにかく美人でね、おまけにアウトドアが好きさ」
いけません。
「マスター、僕のこと、話題のネタに使ったろう?」
「いいや」
「何年のつき合いだと思ってるんだい。僕には分かるんだよ」
マスターが笑いながら醤油を注す。
「あんたが何といってきたのか、僕には分かる。僕がマスター、そっちはヨウコさんの役をやってよ」と言ってもう一杯。
「いいよ」とマスターは笑う。
「いやあ、アウトドアですか。実は僕も凝っていましてね」
「まあ!」
「よくいろんな所に出掛けます、僕も。自然が一番ですね」
「そうですね。私、山に登るんです、時々ですけど」
 「いいですものねえ。ザック担いで山の中に入って、自然の中に浸りきる。これが人生の悦楽です」
「いいですものねえ。ザック担いで山の中に入って、自然の中に浸りきる。これが人生の悦楽です」「山登りされるんですね」
「ええ、登り着いたときの汗が最高ですね(注‥彼は山登りなどしない。疲れることが大嫌いなのである。キャンプとは、車で出掛け酒を喰らうことと思っている)」
「どんな所行かれました?」
「多良岳とかですね。ナイフ一本持っていけば、いろんなことができます。食材は現地調達ですね。楽しいですよ(注‥彼がキャンプに持っていくグッズは、まるで夜逃げする男の所帯道具のように膨大なものだ。彼に「そんな道具じゃ山には登れない。山登りは人生といっしょだ。自分が背負える分しか持っていけないんだよ」と言ったことがある。それが彼には未だに理解できない)」
「素晴らしいですね」
「ザックはミレーを使っています。ご存じですか?」
「すごいですね。フランスの」
「そうそう、よくご存じですね。それからやっぱり高い山には、レキっていうドイツ製のステッキはかかせませんね(注‥これらのアイテムは僕が彼に紹介し購入したものだが、押し入れの奥に値札の付いたまま放置されている)」
「一人で出掛けるんですか?」
「いやあ、これがですねえ。まつをってのがいましてね。彼を山に一回誘ったら、これが病みつきになりましてね。連れてってくれってうるさいほどに、言うんですよ」
「その人、お友達ですか?」
「そうですねえ。いつも来てますねえ、家に。時々カヤックで、無人島に出掛けてキャンプをするんですよ」
「カヤックですか! おいくらぐらい、するものなんですか?」
「ああ六十万でしたね、海外から取り寄せたもので。日本製は船体が薄くてもろいんですよ(注‥もう飽きた、とこの前宣言されておられた)。そのかわり少し重いんですけどね。今度一緒に乗りませんか? カヤックの上げ下ろしは、まつをを呼べばすぐ来ますから」
「まあ、いいんですか!」
 ここまで話して、僕は一気に焼酎を開けた。
ここまで話して、僕は一気に焼酎を開けた。「どうだい、こんな会話したんだろう?」
「なんで分かる」
「長い付き合いだ」
そんなもんかねえと、彼は鯨を食う。
「本当のことを話すんだ。結婚したい人ならばね」
「いやあ、相手に逆らわないように話を合わせてると、こうなるんだよねえ」
「セールスしてるんじゃないんだよ、まったく。本当に結婚しようと思ってるの?」
「そうさ」
「一週間後に同じ質問するから」
「?」
「たぶん違った答が返ってくるさ」
「何でそんなこと言う」
「長い付き合いだ」

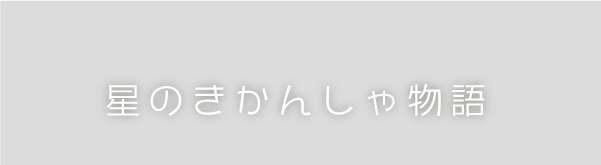




 トップ
トップ オススメ
オススメ 記事一覧
記事一覧 掲示板
掲示板 長崎マニアックガイド
長崎マニアックガイド 長崎の酒場
長崎の酒場 長崎を歩く
長崎を歩く 長崎キャンプ場
長崎キャンプ場 私の手作りキャンプ場
私の手作りキャンプ場 私の家づくり
私の家づくり 長崎インターネットラジオ
長崎インターネットラジオ デザイン
デザイン 絵
絵 音楽
音楽 小説
小説 メール
メール リンク
リンク