四方はどろどろの雨に包まれ、暗黒の世界に救急車やパトカーのサイレンが交錯した。死傷者で病院は溢れ、交通は寸断され、電話が不通となり、臨時ニュースを求めテレビをつけると再放送のドラマで役者が笑っていた。
もう市長は餅つきをしなくなった。夜にジャズ・コンサートがうたれることもなく、アーケードにはシャッターを閉ざした店舗が並んだ。大規模な移住が始まった。安全を求め、体育館、旅館、客船、仮設住宅、親戚宅、そして他の市町村へと人々は移動した。
真夜中疲れ果て体育館に雑魚寝する被災者に、照るライトを向けてマスメディアは叫んだ。
「みなさん、こんなに被災者の方々は疲れ果てていらっしゃいます!」
失せろ、無礼者!
それからしばらくして、マスターは僕たちの前から消えた。実に唐突な消え方だった。わずかばかりの家財道具と五千万円の借金を背負って、彼はある日音信不通となった。
それからも時折、僕は「星のきかんしゃ」を訪ねた。
荒廃した細い坂道をのぼっていくと、枯れた木々の間からとんがり屋根が見え、そして外壁が姿を現した。
もう屋根の青い色も、ベランダの輝く白もなかった。辺りには厚く火山灰が降り積もり、ただ灰色の世界が広がっていた。そして風が吹いていた。初めて出会ったときと同じように、相変わらず微風が吹いていた。風にのって時々一陣の灰が舞い、そして力無く散り落ちた。僕は、病院に見舞いつづけた祖母を思い出していた。死を目前にして白いシーツにくるまった祖母。ベッドの中で縮み枯れいこうとしていた身体。
胸まで伸びた草をかき分け、ペンションの入り口に近づく。窓から建物の中を覗き込む。
僕は何をしてるのだろうと思った。何を覗こうとしているのだろう。薄暗い室内も、うっすらと白い灰に被われていた。もう常連たちの笑い声もなく、暇そうに外を見やるマスターの姿もなかった。誰もいなかった。災害に疲れ果てた町が、僕の帰るところだった。
車に乗り込もうと車のドアを開ける。そのとき山が金属製の音を轟かせた。振り返っても別に変わらない。おかしいなと車に乗り込む。なにげなくバックミラーを覗く。僕は目を剥いた。悪夢のように濁った火砕流がこちらに迫っていた。ギアを入れて急発進する。火砕流は巨大な鎌首をもたげる。方々に立てられた災害用のサイレンが一斉に鳴り響いた。火砕流が天空にまで届く巨大な暗幕となって、陽の光を遮り始める。辺りの光景は、まるで上映を終えたスクリーンの褐色に染まり、その後みるみる夜を迎える。
十分ほど血相を変えて疾走した。浜辺の集落に着き車を止める。道行く人が落ち着いている。ここまで来れば大丈夫だ。僕は深い息をついた。しばらくすると灰を含んだ黒い雨が降り始め、重い音をボンネットに立てた。辺りを伺おうとしたが、窓は土まみれとなり車内は暗転していった。
男は息を殺して近付く。建物の周りを一周し、灯のないことを確認する。用意したバールで窓をこじ開け、室内へと身を滑り込ませると、横たわったまま動きを止めた。錐で闇を裂くほどに耳をそばだてる。誰もいなかった。すっくと立って、ブレイカーを上げる。冷蔵庫がグンという低い音を立てて息を吹き返す。もう一度外に出ると、男はウイスキーと胸一杯の薪を運び入れた。やがて暖炉に火が立ちあたりを照らす。男は咳を一つして、グラスを呷り始めた。
「昨夜深江で一件の家屋が焼失した」
 そう新聞は伝えていた。「星のきかんしゃ」が火事で燃え落ちた。原因は、かっての常連で自称家具作家の不法侵入に因るものだった。酔いつぶれた隙に、暖炉から火の手が廻ったのだった。
そう新聞は伝えていた。「星のきかんしゃ」が火事で燃え落ちた。原因は、かっての常連で自称家具作家の不法侵入に因るものだった。酔いつぶれた隙に、暖炉から火の手が廻ったのだった。ややあって現場に赴いた。それまで視界を遮っていた建物が消え、向こうの風景が見えた。残滓の中に陽光を受け、列柱が黒光りをして横たわっていた。それは不思議な穏やかさに包まれた光景だった。終わった。僕は改めて、一つの時代が終わったことを淡々と感じていた。

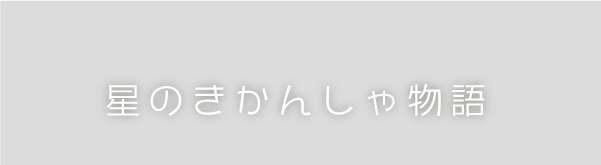




 トップ
トップ オススメ
オススメ 記事一覧
記事一覧 掲示板
掲示板 長崎マニアックガイド
長崎マニアックガイド 長崎の酒場
長崎の酒場 長崎を歩く
長崎を歩く 長崎キャンプ場
長崎キャンプ場 私の手作りキャンプ場
私の手作りキャンプ場 私の家づくり
私の家づくり 長崎インターネットラジオ
長崎インターネットラジオ デザイン
デザイン 絵
絵 音楽
音楽 小説
小説 メール
メール リンク
リンク