「星のきかんしゃ」は、人里離れた丘陵地帯にあった。
よく覚えている。
渡る風、そよぐ緑。
 陳腐な表現だ。けれど僕の中では、今でも「星のきかんしゃ」には、心地よい風が吹いている。懐かしくてたまらない。あの頃の想い出は、ラズベリーのように甘酸っぱい香りを漂わせている。細い緩やかな坂道をのぼっていくと、緑の梢の間から青いとんがり屋根が見え、そして陽光に照らし出された白い外壁が姿を現した。木枠を十字に組んだ広いバルコニーには雑木が陰を落とし、日溜まりの中には色鮮やかなプランターがあった。
陳腐な表現だ。けれど僕の中では、今でも「星のきかんしゃ」には、心地よい風が吹いている。懐かしくてたまらない。あの頃の想い出は、ラズベリーのように甘酸っぱい香りを漂わせている。細い緩やかな坂道をのぼっていくと、緑の梢の間から青いとんがり屋根が見え、そして陽光に照らし出された白い外壁が姿を現した。木枠を十字に組んだ広いバルコニーには雑木が陰を落とし、日溜まりの中には色鮮やかなプランターがあった。コーヒーを注文し、窓際の席に腰を下ろす。広く取られた窓からは、眼下に青い海を満々とたたえた海岸線が望めた。砂浜は緩やかなカーブを描いて右手へと伸び、そして人家が点々と見て取れた。静かだった。ここまでは国道を走る車の音も届かず、とまどいがちな葉擦れの音だけが辺りにはあった。なるほどと僕は思った。
 次の日、勤務が終わるとタクシーでペンションに乗り付けた。期待どおり、そこから眺める夕刻の海は、最上のステーキにかかるソースのような彩りに包まれていた。昨日と同じ席に陣取る。そしてワインといくつかのつまみをオーダーし、移ろう光景をゆっくりと楽しむ。日が暮れた頃、マスターが僕に声をかけた。「外でおでんパーティーをやってる、来ないか」と。常連と呼ばれるようになるまでに、それほど時間はかからなかった。
次の日、勤務が終わるとタクシーでペンションに乗り付けた。期待どおり、そこから眺める夕刻の海は、最上のステーキにかかるソースのような彩りに包まれていた。昨日と同じ席に陣取る。そしてワインといくつかのつまみをオーダーし、移ろう光景をゆっくりと楽しむ。日が暮れた頃、マスターが僕に声をかけた。「外でおでんパーティーをやってる、来ないか」と。常連と呼ばれるようになるまでに、それほど時間はかからなかった。ペンションのオーナーは、俵山一臣氏という。僕はマスターと呼ぶ。彼は両方の眉毛が繋がったフライパンのような顔をしている。背は低い。出会った頃は中肉中背でいささかボヘミアン、現在の歩く成人病とでも称すべき肉体と精神はまだ見あたらなかった。
「まつをさん。俺がここに来たとき、何もなかったんだ」
「資金も?」
「うん。土地を買い、プレハブを一棟立て、庭に掘った穴に糞していたよ」
「楽しかったかい?」
「もちろん。その頃はまだ書籍の販売員をしていてね。夜帰って、ペンションの図面を引くのが楽しみだった。そこから始まったんだ」
なんという無垢な青年だったのだ、とジンとくる。「めげそうに、ならなかったかい?」
「いや人生っていうのはね……」
いかん、彼に人生論をぶつきっかけを与えてしまった。彼は口角泡を飛ばし語るのが好きだ。本人に面と向かっては言えぬが、よくも他人に話すなと思うほどつまらぬ人生観だ。彼はそうすることで、自分自身を説き伏せているかのようで、聞く人の涙を誘う。そして「語り」は、時々「騙り」に変わる。
「その頃、不自由じゃなかったかい?」と聞く。
「女にもてなかったね。誰も寄りつかなかった」
「誰も?」
「そう。だからありったけのコネを使って金をかき集め、とりあえずペンションの元を建てた。そうしたらボチボチ運が向いてきた」

女好きである。
「マスターの夢は、女性にもてることだったの?」
「それもあるね」
よく学校の教員は「人生夢が大切だ」と檄を飛ばす。「夢も質によるだろう」と思う。
「まつをさん、俺は悟ったよ。心なんて見えない。もういい。今度から彼女はスタイルで選ぶことにする」悟ったと語るのもまた彼の性癖である。悟っていればこの物語もない。彼の人格は安物のズタ袋のように見事に破れていて、書きごたえ十分である。だからこそ彼の周りに人があつまる。ペンションに客が何時間いようが気にしない。いつの間にか客を残して寝る。勘定はどんぶりも甚だしい。常連が奇抜な企画を立てれば、そりゃ面白いと膝を叩く。お下劣でメルヘン好き。でも考えてみれば、そんなもんじゃないかと思う。色即是空を説く坊主には、やたら道楽者が多い。マスターも年を経てお下劣さに堂が入り、メルヘン傾向にはピンク色の紗がかかってきた。人間が年をとるってことは、現象として興味深い。そして彼は実に面白い。なにか芸をやるという訳ではないけれど。猿じゃないんだから。

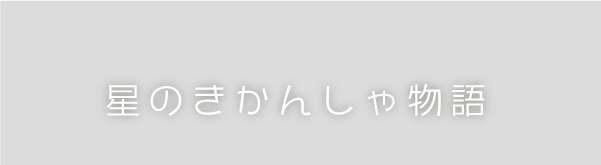




 トップ
トップ オススメ
オススメ 記事一覧
記事一覧 掲示板
掲示板 長崎マニアックガイド
長崎マニアックガイド 長崎の酒場
長崎の酒場 長崎を歩く
長崎を歩く 長崎キャンプ場
長崎キャンプ場 私の手作りキャンプ場
私の手作りキャンプ場 私の家づくり
私の家づくり 長崎インターネットラジオ
長崎インターネットラジオ デザイン
デザイン 絵
絵 音楽
音楽 小説
小説 メール
メール リンク
リンク