あの日、空は見事なまでに晴れていた。
広大な雲仙の裾野が広がり、僕らは日常を満喫していた。
そしてその稜線から、二筋の白い噴煙が立ち登った。
平成二年十一月十七日、災害の始まりの日だった。
 双眼鏡で雲仙の噴火口を覗く。倍率は十一倍。火口付近の樹木の枝一本ずつが見て取れるほどの鮮明さだ。火口の上空を飛ぶヘリコプターがよく見えた。そして、もうもうと煙が上がっていた。時折鳥が視界を横切る。爬虫類が根性を振り絞り、鳥類に進化した気持ちがなんとなく理解できた。
双眼鏡で雲仙の噴火口を覗く。倍率は十一倍。火口付近の樹木の枝一本ずつが見て取れるほどの鮮明さだ。火口の上空を飛ぶヘリコプターがよく見えた。そして、もうもうと煙が上がっていた。時折鳥が視界を横切る。爬虫類が根性を振り絞り、鳥類に進化した気持ちがなんとなく理解できた。不思議なことに、島原ではいつもの日々が過ぎていった。
アーケードは買物に忙しい人々でごったがえし、歓楽街には酔っぱらい達がうろついた。たとえば昼間に産業祭が開かれ市長は餅つきをし、夜にはジャズ・コンサートがうたれアンコールの声が響いていた。人間は日常性に執着する。あくまでも昨日と今日の間になだらかな継続を求めるのだ。
 「星のきかんしゃ」に登っていくと、マスターは輪をかけてのほほんと構えていた。
「星のきかんしゃ」に登っていくと、マスターは輪をかけてのほほんと構えていた。「阿呆らしい。ここからは、噴煙の上がる山は見えないよ。災害はこの丘の向こうの話」そう彼は言い放った。予想通りである。基本的にテレビを見ない。ニュースも読まない。さらに世間からも遠いし、くよくよしない。彼は過去を罵倒するが、後悔と反省はしない。ある種の見事さがそこにはある。
事態が急変したのは、溶岩ドームが現れてからだった。
その出現が報じられると、砂糖に集る蟻ん子のようにマスメディアが訪れた。「星のきかんしゃ」ではこれと同時に創業以来の、大繁盛が始まった。災害特需である。「星のきかんしゃ」だけが、例外だったわけではない。メディアが注文する上弁当を作るために、被災者用の並弁当の入手が困難なほど、彼らは集まった。
興奮したワイドショーの司会者がスタジオから、山を背に立つレポーターに向かって次のように言い放った。
「で! 島原に人は住んでるんですか?」
てやんでい!
島原の爺さんがしゃべると下にテロップが入り、僕達は自身の置かれた立場を少しずつ理解していった。
僕はマスターを生活者として描こうとしている。彼は被災者となったが、したたかに生き抜いた。そんな事実を書こうと。これは身近に多くの被災した方たちと接した者にとって、決断を必要とすることだ。けれど同時に、昨今の小市民ヒューマニズムが、いかに薄っぺらい価値観に裏打ちされているかも思い知らされた。被災者はかわいそうである。それはそうだ。突然降ってわいた災難に襲われたのである。自己責任を問われる問題ではない。銀行の行く末を見誤って、預金が返されなくなった預金者とは違う。三年後に互いを罵倒する相手と永遠の愛を誓う、新郎新婦とは違うのだ。
 しかし僕はメディアが主になって増幅されていった価値観が、いかに画一化された単細胞なものであったのかを、この目で見た。うんざりである。みんなそろそろ気付こうよ。環境破壊の悲惨さを説いた後に、山奥に新築なった高級リゾートホテルの宿泊券をプレゼントする、そんな輩の口から吐き出される言葉は、阿呆の戯言なのである。
しかし僕はメディアが主になって増幅されていった価値観が、いかに画一化された単細胞なものであったのかを、この目で見た。うんざりである。みんなそろそろ気付こうよ。環境破壊の悲惨さを説いた後に、山奥に新築なった高級リゾートホテルの宿泊券をプレゼントする、そんな輩の口から吐き出される言葉は、阿呆の戯言なのである。被災者は生活者である。すべての人は、生活者なのである。当たり前なのだけれど、メディアでは欠落して語られない視点だと思う。マスターはしたたかに生き抜いた。マスメディアから銭を啜り、火砕流から逃げまどい、隙あらば大酒を食らったのだ。
災害騒動で転がり込んだ資金をもとに、彼は岩風呂を増築した。風呂はそれほど時を経ずして完成の運びとなり、僕らは昼間から湯を楽しんだ。湯気の立ちこめる中、身体を休めていると、時々遠くでゴロゴロという音がした。溶岩ドームが崩落する音だ。その頃には、「星のきかんしゃ」の手前の丘ごしに、溶岩ドームが黒く鋭角な頭をそそり立たせていた。僕らは湯船の中、ゆったりと身体をのばしながら、うっすらとした死の匂いを嗅いだ。
何者かがどこかで雪玉を廻していた。自分の伺い知れないところで、何者かが人生の雪玉を転がしているのだ。そう思うことがある。ゆっくりと事態は転がりながら膨らんでいき、そして突然私たちの目の前に現れる。
「不可逆ですな」
事態は、そう僕達に告げたあと、「さあどうするね」と足組みをする。
火砕流が始まった。

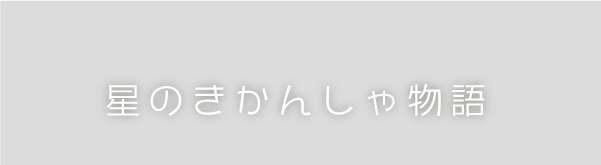




 トップ
トップ オススメ
オススメ 記事一覧
記事一覧 掲示板
掲示板 長崎マニアックガイド
長崎マニアックガイド 長崎の酒場
長崎の酒場 長崎を歩く
長崎を歩く 長崎キャンプ場
長崎キャンプ場 私の手作りキャンプ場
私の手作りキャンプ場 私の家づくり
私の家づくり 長崎インターネットラジオ
長崎インターネットラジオ デザイン
デザイン 絵
絵 音楽
音楽 小説
小説 メール
メール リンク
リンク