アウトドア雑誌を開いていると、マスターが僕にたずねた。
「まつをさん、カヤックはどうかな?これで釣りはできると思う?」
「大村湾は波が静かだからね」
「ふうん。カヤックに乗って、無人島にでも行きたいね」
「いいね。釣った魚でキャンプだ」
数週間後にアメリカからカヤックが着いた。二人乗りである。氏が購入したのだ。
「ちょっと高かった。ハンマーで叩いても割れないんだ。これで岩場も大丈夫。行こう」
 大村湾には海上空港の近くに、市所有の無人島がある。ここを目指す。テント、スリーピングバッグ、マット、ランタン、バーナー、ガス、鍋、食器、調味料、飲料水、酒、そして釣りの道具。これらを全長四メートルのカヤックに積む。波打ち際で前部にマスターが座る。オールをセットし後ろから助走をつけて乗り込むと、カヤックは見事に水面を滑り出した。塩の匂いがした。海は腕時計の鏡面のように穏やかに輝いていた。視界は水面とともにあって、オールを漕ぐ度に、身体の深部に溜まった鬱屈が海水に溶け出すかのようだった。
大村湾には海上空港の近くに、市所有の無人島がある。ここを目指す。テント、スリーピングバッグ、マット、ランタン、バーナー、ガス、鍋、食器、調味料、飲料水、酒、そして釣りの道具。これらを全長四メートルのカヤックに積む。波打ち際で前部にマスターが座る。オールをセットし後ろから助走をつけて乗り込むと、カヤックは見事に水面を滑り出した。塩の匂いがした。海は腕時計の鏡面のように穏やかに輝いていた。視界は水面とともにあって、オールを漕ぐ度に、身体の深部に溜まった鬱屈が海水に溶け出すかのようだった。シャンパンを開けてシェラカップに注ぎ、進水祝いの乾杯を掲げる。
「生きてるって感じだね」と彼が呟く。
「そうだね、俵山さん」
「マスターって呼んでくれ。昔どおりマスターでいいよ」
シャンパンを一杯、海に捧げる。
携帯電話が鳴った。知人からのものだった。
「今日は来れないよ。今、海の上」
島には六畳ほどの平坦なサイトがあって、ここに陣取ることにした。マスターはいそいそと釣り糸を投げる。僕はテントやかまど作りに取り掛かる。昔からこの役割分担でやってきた。当方、釣りだけはご免被りたい。糸は絡むし、餌付けはチマチマしてるし、投げたら巻き挙げなきゃならない。面倒である。
 セットを終えて島を散策すると、島の東側に朽ちた桟橋をみつけた。そこから対岸の街の様子が望めた。今は無人となったこの島にもかつては往来があったのだろう。サングラスを外して街の様子を眺める。耳元で寄せる波の音がしていた。映画の広角ショットをみているかのようだった。スーツを脱いで遠くから見る街はなにか滑稽で、どこまでも人がすることに過ぎないんだなと思えた。粒のような人が歩き、車が走り、ビルと広告が重なり、そして青い山々が彼方へと消えていた。
セットを終えて島を散策すると、島の東側に朽ちた桟橋をみつけた。そこから対岸の街の様子が望めた。今は無人となったこの島にもかつては往来があったのだろう。サングラスを外して街の様子を眺める。耳元で寄せる波の音がしていた。映画の広角ショットをみているかのようだった。スーツを脱いで遠くから見る街はなにか滑稽で、どこまでも人がすることに過ぎないんだなと思えた。粒のような人が歩き、車が走り、ビルと広告が重なり、そして青い山々が彼方へと消えていた。生きているだけなんだ。それだけなんだ。
そう思った。
夜、マスターの釣ったクサビを流木で焼いて酒を呷った。
時折、海上空港に着陸する飛行機が、最上のイルミネーションとなって頭上を過ぎていっていた。

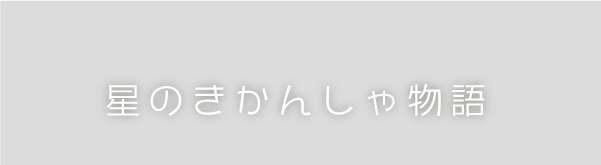




 トップ
トップ オススメ
オススメ 記事一覧
記事一覧 掲示板
掲示板 長崎マニアックガイド
長崎マニアックガイド 長崎の酒場
長崎の酒場 長崎を歩く
長崎を歩く 長崎キャンプ場
長崎キャンプ場 私の手作りキャンプ場
私の手作りキャンプ場 私の家づくり
私の家づくり 長崎インターネットラジオ
長崎インターネットラジオ デザイン
デザイン 絵
絵 音楽
音楽 小説
小説 メール
メール リンク
リンク