ある日訪ねると、彼がいた。
「やや、まつをさん、こちら中村さん。電通のプロデューサー」
どうも、と長身の中村雅俊似の男が、首を傾けながらこちらを向いた。
詐欺師様の登場である。
詐欺師は「や、どうも」と目線をこちらに送った。
マスターの話では、数日前からペンションに泊まっているらしい。長崎旅博覧会のプランニングのため長崎で打ち合わせがあり、その後の休暇をここで過ごしているという。
 あほか。
あほか。マスターが、どこぞの少女漫画の主人公のように、瞳を輝かせながら言う。
「中村さんはね、クリエイティブに属しててね……」
中村は「そ」といって立ち上がる。「長崎の施設は、どれもキャパがねえ……」そう言って彼は、手についたピーナッツの薄皮を神経質そうに払った。
マスターの説明を、かいつまんで書く。中村氏は電通のクリエイティブで、長崎旅博覧会のために来ていて、中村雅俊の親戚で、慶応の法を卒業していて、普段は東京に住んでいて、妹はフランスでモデルをやっていて、実家は資産家。
あほか。
常連たちはグラスをあげながら、彼の話す言葉に相槌を打つ。
「何日、泊まってるの?」と僕。
「もう三日ほどお世話になってます」と中村。
三日間無賃宿泊だ。
「でもね、中村さんはいい人でね、皿洗いまでやってくれるんだよ」とマスター。
あ・ほ・か。
けれど、今考えても見事な応答だった。なんというか、プロはリズムが違う。実に流暢なのだ。僕のそれとなく入れる探りに即答し、いつの間にか複雑怪奇な虚偽の塔を築き上げていく。微少な個体である珊瑚が、波にたゆたいながら次第に巨大で奇怪な形を作っていくような名人芸だ。
彼は心臓を煩っていた。天罰である。けれどこれも嘘だったのかもしれない。
そしてあれよあれよという間に、彼の滞在は十日となった。マスターを小部屋に誘う。

「マスター。ありゃ、いけない」
「なにが?」
「彼は、中村じゃないよ、たぶん」
「?」
「中村という名前から、職業から、モデルの妹から、みんな嘘だ。あいつは嘘つき。わかる?」
「あのねまつをさん、今度、中村さんの企画でね、このペンションの下の土地買って、でかいテニスコートを作る。いいよお、こりゃいい。このペンションも当たる。やっぱり企画のプロは違う」瞳、キラキラ。いけません。
ただマスターは、中村氏が僅かな音で目を覚ますことを、とても不思議がっていた。「あの人はいつ寝てるんだろう。やっぱり繊細な人は違うね」と。
放っておいたら、マスターの中村への入れ込みは、ずいぶんと加熱していった。テニスコート用土地取得の話は、まず多くの常連をなびかせ、銀行役員を巻き込み、土地取得交渉に町議を動かさんとしていた。実務的な段階である。おいおい。そしてその結果、中村の無賃宿泊は数週間に及んだ。
あ・ほ・か。
事態はいよいよ進展し、視察旅行の運びとなる。御一行様は、マスター、甲斐さん、そして詐欺師中村様。行き先は阿蘇で大きなテニスコートを持つペンションである。 その夜の御一行の華麗さは、今でも語りぐさである。肴を並べ、高級ワインを開け、カラオケは阿蘇の深夜に響きわたり、お三方の大研修会は行われた。会が盛会を極めたことは、申すまでもない。高級テニスコートは、もはや彼らの頭の中では、完成に至ったのである。めでたし。マスターのことを、もはやマスターと呼んでいただきたくない。青年実業家、俵山信一氏と呼んでいただきたい。畏れおおくも、氏は億の資金を動かされるアミューズメント業界のプリンスである。飲めや、飲め。歌えや、歌え。ぱるるるる。御一行は、近未来に燦然と輝く己が姿を、目を細め眩しげに見ていた。
翌日、「ここは私が」と自ら宿泊代を申し出た中村の支払いによって、御一行は心地よく阿蘇を後にした。プロデューサー中村の財力の一端を垣間見たと、俵山氏は熱く私に宣われた。
その後、中村は東京の実父に一億円ほど用立ててもらうため、ペンションを去った。一週間後には帰ってきますからと、言い残して。
 ペンションには、いつになく重い空気が流れていた。
ペンションには、いつになく重い空気が流れていた。訪ねると、マスターと町議がいた。
「まつをさん。町議さんは、中村が怪しいって言っててね」
やっと私の賛同者が現れた瞬間である。
町議曰く、「どうもおかしい。電通の人間が、どうしてそんなに時間がある」
そうでしょ、そうでしょ。ちょっと離れて見ている者にとって、一連の出来事は悪い冗談だ。
「そっかなあ?」とマスター。
「今、彼はどこにいるの?」
「さあ?でも明日、ここに帰ってくる」
「明日?」
「そう、明日」
「それまでに、調べよう」
「はあ?」
「彼の身元が分かるもの、たとえば住所は?」
「東京の新宿。それ以上は知らない」
「電話番号は?」
「自宅をいつも開けてばかりで、自宅の番号は意味がないって言ってたよ。そのかわり連絡を取りたいならって、もらっていた番号が幾つかある」
「それそれ」
こうしてパンドラの箱は解き放たれた。まず東京へ。電話が繋がったのは、どこかのクラブだった。「中村? 誰それ?」と電話口に出た女は言った。来た来た来た。次に長崎の友人なる人物宅へ。電話に出た男は中村のことを聞くなり、どこにアイツはいるのかと怒鳴った。事情を説明する。「ダマされないように。ヤツは詐欺師だ。私は親まで巻き込んでやられた」と。
決・定。
マスターは爆発なされた。町議は唸られた。呼び出しで訪れた甲斐さんも、キレた。
「ちょっと待てよ。彼の正体を割り出す方法がもう一つある。中村はキャッシュカードで、阿蘇の宿泊代を支払ったって言ってたろう。カードの番号を調べればいい」
 そうだそうだとマスターが、電話を阿蘇のペンションに電話する。電話口に出た先方はこう宣うた。
そうだそうだとマスターが、電話を阿蘇のペンションに電話する。電話口に出た先方はこう宣うた。「あんたら、指名手配しとる」
哀れ御一行は、正真正銘、指名手配されていたのである。つまり、こうだ。カードで払いますと中村が申し出た。マスターと甲斐さんは外に出た。一人になった中村は支払いをせず、時間を置いて外に出た。御一行は車で立ち去られた。ややあって店の主人は、無銭宿泊だと気付く。御一行が宿泊された部屋に行く。そこには甲斐さんの名前が入ったタオルがあった。御一行は指名手配された。代表者名は、タオルを置き忘れた甲斐氏。以上。
これを聴いた甲斐さんの激怒の仕方を、君に上手く伝えることは至難の業だ。その様は、なんというか身体中にヒビが入るような、そんな激怒の仕方だった。
マスターと甲斐さんは、吠え合って中村を罵る。アノ野郎! そもそもあの目が悪党の目だ、身のこなしが詐欺師だ、どう考えても話が出来過ぎてる、なにが中村雅俊の従兄弟だ、バッカタレめが!等々。
そして、そんな興奮状況のただ中に、件の電話のベルはなったのである。
全員が目を剥いたまま見つめ合い、言葉を失った。
「ヤツだ! 中村だ!」
マスターが言った。
「どうしよう?」
「俵山さん。冷静に、にこやかに。彼をここに明日来させるんだ」町議が言った。
「そうそう冷静に。捕まえるぞ、捕まえるぞ」
「まず笑えよ。平常心」
あー、簡単に言うと、マスターが最も出来ない事を、僕達は注文していたことにすぐ気付くことになる。土台無理なのである。彼は怒りたいときに怒り、笑いたいときに笑い、寝たいときに寝て、百パーセント天然酵母状態で三十数年間生きてきたのである。そういう人なのだ。深呼吸し受話器を取ったマスターは、
「やあ中村さん」と言って、引きつったヒヒヒという奇怪な声を出した。
以来、中村は二度と僕達の前に現れなかった。

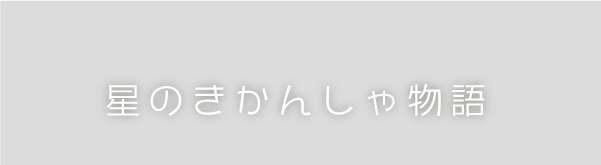




 トップ
トップ オススメ
オススメ 記事一覧
記事一覧 掲示板
掲示板 長崎マニアックガイド
長崎マニアックガイド 長崎の酒場
長崎の酒場 長崎を歩く
長崎を歩く 長崎キャンプ場
長崎キャンプ場 私の手作りキャンプ場
私の手作りキャンプ場 私の家づくり
私の家づくり 長崎インターネットラジオ
長崎インターネットラジオ デザイン
デザイン 絵
絵 音楽
音楽 小説
小説 メール
メール リンク
リンク