また転勤となった。
ワッセワッセと引っ越しをして、ふと見渡すと、歩いて五分のところに、マスターの新居があった。
ここにいたのだ。
「庭で飲もう」と彼が誘う。
外にはちょっとしたテラスがあって、白いテーブルとイスが置かれていた。ワインクーラーから白を取り出し、グラスに注ぐ。サイドボードに並ぶ作家名の入った陶器のコレクションから一枚取り出し、刺身を盛る。春の風が吹いていた。
「俵山さん、仕事はどうなの?」と僕がたずねる。
「店舗が三軒ばかりあってね」と彼は答えた。
僕は、彼が一発逆転ホーマーを放ったことを理解した。
かって僕に語った夢の生活を、災害からわずか二年で彼は手にしていたのだった。
被災者の影はもうなかった。彼は完全な意味で成功者だった。
次の週末、彼女と会った。
コンニチハ、と彼女はこちらをまっすぐに見ていった。
マスターは幾分照れながら、僕の反応を気にしていた。
透き通るように白い肌をしたその女性は、木漏れ日の中、孵化したての昆虫の羽根のような印象を与えた。
 陶芸を楽しみに出掛ける。マスターは胸に金のチェーンでサングラスを下げ、静かに車のハンドルを握っていた。「マスターには慣れましたか?」と僕が聞き、「彼女はよくしてくれてるよ」とマスターが応えた。春だった。
陶芸を楽しみに出掛ける。マスターは胸に金のチェーンでサングラスを下げ、静かに車のハンドルを握っていた。「マスターには慣れましたか?」と僕が聞き、「彼女はよくしてくれてるよ」とマスターが応えた。春だった。午後には暖かい日射しの中、テラスのテーブルにはコーディネイトされた花と料理が盛られた。春の微風を受けながら僕達はグラスを傾け、生きていることの素晴らしさを満喫した。今にして思えば、僕が知る限り、マスターの最も落ち着いた日々だったろう。彼女とマスターには一種の気品があり、愛車グロリアもゆったりと走った。二人とも過去を背負っていたけれど、それは今の在りように深みを与えるためのものであったかのように思えた。

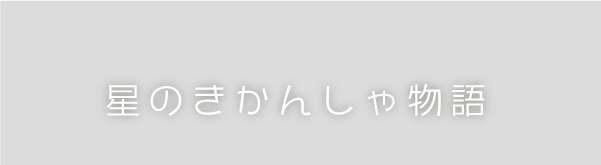




 トップ
トップ オススメ
オススメ 記事一覧
記事一覧 掲示板
掲示板 長崎マニアックガイド
長崎マニアックガイド 長崎の酒場
長崎の酒場 長崎を歩く
長崎を歩く 長崎キャンプ場
長崎キャンプ場 私の手作りキャンプ場
私の手作りキャンプ場 私の家づくり
私の家づくり 長崎インターネットラジオ
長崎インターネットラジオ デザイン
デザイン 絵
絵 音楽
音楽 小説
小説 メール
メール リンク
リンク