ペンションは実に込み入った造りをしていて、一旦中に入ると迷路のようだった。どこかである人が、建物は作り手の精神構造が現れるといっていた。なるほど。けれども、僕はマスターの思慮の深さが、あの建物を現出させたとは思わない。あれは彼の行き当たりばったり、思慮不足の賜だと思う。一番近くにいた私がいうのだから確かだ。めちゃくちゃ、計画性がないのである。
 彼は三ヶ月に一度のペースで改築をしていた。それは、まるでビーバーがあちこちから運んだ小枝を山積みにして池の中に巣を作るような、なんというか「これはワテのサガなんどす。すんまへん」といった生態とも呼ぶべきものだった。アプリオリなる因果律に追い立てられし者の悲しみ。カントだったら、そんな風にでも言うんだろうなあ、きっと。人間にはいくつかのベクトルが埋め込まれている。彼の場合、その一つが家を造ることなのだろう。
彼は三ヶ月に一度のペースで改築をしていた。それは、まるでビーバーがあちこちから運んだ小枝を山積みにして池の中に巣を作るような、なんというか「これはワテのサガなんどす。すんまへん」といった生態とも呼ぶべきものだった。アプリオリなる因果律に追い立てられし者の悲しみ。カントだったら、そんな風にでも言うんだろうなあ、きっと。人間にはいくつかのベクトルが埋め込まれている。彼の場合、その一つが家を造ることなのだろう。けれど、もう一つ知っておいてもらいたいことがある。彼はその家に住むことに関心がない。どうでもいいと思っている。しばらくは事務所のソファーの上に寝泊まりし、それで十分満ち足りていた。分からない人だ。彼と過去付き合った女性は、そんな混乱を起こして彼の元から去ったんだろう。南無。無常である。
ペンションの入り口も、五年間に三度移動した。
客室は徐々に増えていって、最後には七つぐらいあったんじゃないかと思う。「思う」というところが凄い。常連だった僕でさえ、よく思い出せない程の構造で、全室仕様も異なっていた。迷路だ、本当に。改めてある種の感慨に耽ってしまう。そういえば屋根裏部屋という隠し部屋もあった。あそこで何してたんだ、おい。
 玄関を開けると、すぐダイニングだった。床と壁が白木で、東側と南側に大きく窓が取られ、一番奥には煉瓦を積んだ暖炉があった。入ると木の匂いがツンとして、陽の光が緩やかに空間を満たしていた。白木のテーブルとイス、コットンのランチョンマット、素焼きの陶器、そして水を与えられず苦行僧のように立ちつくす観葉植物。そんなものが点々と置かれていた。
玄関を開けると、すぐダイニングだった。床と壁が白木で、東側と南側に大きく窓が取られ、一番奥には煉瓦を積んだ暖炉があった。入ると木の匂いがツンとして、陽の光が緩やかに空間を満たしていた。白木のテーブルとイス、コットンのランチョンマット、素焼きの陶器、そして水を与えられず苦行僧のように立ちつくす観葉植物。そんなものが点々と置かれていた。右側奥に大きな原木から作られたカウンターが設えられ、止まり木についた者の背中側は「星の間」になっていた。この部屋は天井の一部がガラス張りで、夜に寝転がると満天の星が望めた。
ベランダは二つあった。上のベランダは真っ白に塗られた三十畳ほどの広さで、天体望遠鏡が置かれていた。「いやあ星をみるとロマンチックで、心が吸い込まれていきますよ」とかなんとか彼はウンチクをたれていたが、実は望遠鏡の使い方など知らなかった。買ってはみたものの、使用法が面倒で、近寄ったことがない。一種の詐欺である。買った瞬間から飽きるという類のものは、彼の場合多い。そういう人なのだ。夜になり、客から望遠鏡の取り扱いを頼まれると、急に台所仕事が立て込むことになっていた。「ご自由にお使い下さい」と満面の笑みをたたえて、彼は台所に消えていっていた。
長崎県深江町。ここに「星のきかんしゃ」はあった。

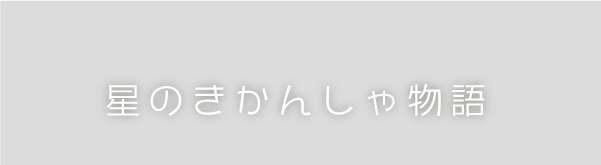




 トップ
トップ オススメ
オススメ 記事一覧
記事一覧 掲示板
掲示板 長崎マニアックガイド
長崎マニアックガイド 長崎の酒場
長崎の酒場 長崎を歩く
長崎を歩く 長崎キャンプ場
長崎キャンプ場 私の手作りキャンプ場
私の手作りキャンプ場 私の家づくり
私の家づくり 長崎インターネットラジオ
長崎インターネットラジオ デザイン
デザイン 絵
絵 音楽
音楽 小説
小説 メール
メール リンク
リンク