 それにしても不思議な経営状態だった。いつも俵山氏は退屈そうな顔で僕を迎えてくれ、ウイークデーにはあまり宿泊客の姿を見かけなかった。近頃になって、彼に尋ねたことがある。「盆と正月に稼いでたんだよ」と事もなげに彼は答える。そうかなあ、と僕の頭が訝る。なにかいかがわしいことでもしてたんじゃないか、おい。
それにしても不思議な経営状態だった。いつも俵山氏は退屈そうな顔で僕を迎えてくれ、ウイークデーにはあまり宿泊客の姿を見かけなかった。近頃になって、彼に尋ねたことがある。「盆と正月に稼いでたんだよ」と事もなげに彼は答える。そうかなあ、と僕の頭が訝る。なにかいかがわしいことでもしてたんじゃないか、おい。そういうわけで、客は週末にちらほらと来た。鴨葱って言葉がある。あれだな、「星のきかんしゃ」の新手の客は。丘の上で下界を眺め暮らすマスターにとって、客とは新しいネタを持ってやってくる鴨だ。これで今夜も面白い酒が飲める。
いろんな客が来た。大体がクセの強い人種だ。あんなところに来ると、人は下界を脱いで地を曝すのに違いない。訳の分からない人も大勢いた。自称家具作家は、世を忍ぶ仮の姿と称し年二百日ほど土木作業員をやっていたし、八戸から軽のアルトでやってきた流れ者はイカを出され「こんなもの向こうじゃ猫跨ぎといって人の喰うもんじゃない」とさんざん腐した後に、バカバカ平らげた。正月過ぎに来た一人旅の女は、到着するなり目にも鮮やかな着物に着替え、ろくに人と話さず三日間過ごして帰っていった。そして酔っぱらってやってきて、酔っぱらったまま帰っていく奴は星の数ほどいた。
甲斐さんは常連客の筆頭である。夜ペンションに訪ねると、彼はいつもカウンターで足を組み、斜に構えて煙草を吸っていた。「よーう」彼はジーンズと白のTシャツが実によく似合う人だった。「……というわけで」というセリフを、辺り一面に漂わせている人っている。甲斐さんは、ベンツのある家で生まれ、数年後には福祉施設にいた。「そんな人生って分かるかい」彼はそう言って煙草の灰を落としたことがある。
そんな日々は、人生の中で最も会話に浮き立つような喜びを味わっていた日々だった。あの頃出会った人たちとまた一堂に会してみたい。それはかなわぬ夢とは知りつつそう思う。常連はみんなすこぶる話術に長けていて、鼻にかける肩書きなど持ちあわせてもいなかった。
 「遊びは気ままを旨とすべし。約束なんぞ、人生上の負債が一つ増えたようで息苦しい」
「遊びは気ままを旨とすべし。約束なんぞ、人生上の負債が一つ増えたようで息苦しい」「隣のゴルフ場、今はあいてるよ。隠れん坊をやろうか」
「今から? もう十二時をまわってるのに?」
「ほら、月があんなに輝いてるわ。ベストコンディションよ」
「いいね、広々として」
「やろう、やろう」
グラスファイバー状の細い雲が散っていた。僕達は暗い林を抜け、隣接するゴルフ場に出る。月光は青く、浮き上がるホールは巨大なクラゲの体内のように暗く柔らかだった。鬼を決める。みんな憑かれたようにもう一杯ずつ飲む。闇が暗い木々の間からじっと僕達を盗み見ていた。一カ所に揃えて靴を脱ぐ。そして二人一組で駆け出す。方々に笑い声が蒔かれ、森の静寂へと消えていった。草いきれが僕らを追う。かろうじて足の裏に感じる芝の触覚だけが、これは現実なんだと僕に囁く。息を切らし穏やかなスロープを越えて、樫の木の影に座る。「というわけで……」
「なにが、というわけ?」
ゲゲゲゲゲ。突然、マスターの下卑た笑い声が、近くを走り去っていった。
よく晴れて客のいない夏日は、マスターと二人で二階のベランダに出た。抜ける青さの下でサングラスをかけ、倒した白いビーチチェアに寝そべりビールを呷る。「それにしてもいい女ってのは、なかなかお目にかからないね」とマスターが言い、「そのとおり」と僕が応える。明確な欲望目標と少ない思弁。日がな一日ぼうっとホイジンガを読んで過ごす。夏の正しい過ごし方だ。
 振り返ってみると、「あの女は俺と結婚するために生まれてきた」とマスターが熱っぽく宣言するのを、僕は三十回以上聞いた。人間何事も慣れる。こう考えるといい。結婚界の星飛雄馬。ご苦労なことに毎週瞳に炎を揺らし、三十分で終わっていくのだ。女性を前にすると、マスターは単なる野良犬になる。そのとき彼女が「お手」と言えば、彼は荒い息を吐きながら喜んでお手をするだろう。
振り返ってみると、「あの女は俺と結婚するために生まれてきた」とマスターが熱っぽく宣言するのを、僕は三十回以上聞いた。人間何事も慣れる。こう考えるといい。結婚界の星飛雄馬。ご苦労なことに毎週瞳に炎を揺らし、三十分で終わっていくのだ。女性を前にすると、マスターは単なる野良犬になる。そのとき彼女が「お手」と言えば、彼は荒い息を吐きながら喜んでお手をするだろう。クリスマスパーティーは最大のイベントだ。企画はマスターと僕と甲斐さん。日暮れになると、県内外から常連さんがワッセワッセとやって来た。ガラス製の大ボールにウイスキーを一本分ぶちまけ、かち割り氷を入れてミネラルウォーターを注ぎ、大量の水割りを作る。それぞれのテーブルに洋風、和風、中華風と各種の料理が盛られ、全員は立ったり座ったり好き勝手にパーティを楽しんだ。バンドがぎゅうぎゅう詰めになった部
 屋をかき分けてアンプをセットし、大音響でレゲェをやる。全員叫んで会話を交わし、ピザや鮨を口に運び飲んだ。阿呆が一人来ていた。どこかの企業のボンボンである。ディップで髪をオールバックにし、赤い蝶ネクタイを付けトラッドでビシリときめていた。パーティが始まると、女の子達に「支店長」と記された自分の名刺を配り、手当たり次第くどき始めた。ある子がその名刺をみんな集めて、トラッド君に渡し言い放った。「帰れば」それから数年後、風の便りにその支店がたたまれたと聞いた。ちょっとした感慨があったなあ、あの時は。
屋をかき分けてアンプをセットし、大音響でレゲェをやる。全員叫んで会話を交わし、ピザや鮨を口に運び飲んだ。阿呆が一人来ていた。どこかの企業のボンボンである。ディップで髪をオールバックにし、赤い蝶ネクタイを付けトラッドでビシリときめていた。パーティが始まると、女の子達に「支店長」と記された自分の名刺を配り、手当たり次第くどき始めた。ある子がその名刺をみんな集めて、トラッド君に渡し言い放った。「帰れば」それから数年後、風の便りにその支店がたたまれたと聞いた。ちょっとした感慨があったなあ、あの時は。一夜開けると空爆の跡地のようだった。一階に降りると、おびただしい数の空瓶や、使い捨て紙皿や、割れたグラスや、ピーナッツの殻や残飯が、夢の墓場のように力無く散乱していた。料理場にあった冷蔵庫の扉は開け放たれ、「これ有料よ」と空しくマスターが叫んでいたワインセラーには一本の瓶も見あたらなかった。
僕らはそれぞれに忙しかったが、それでも私的な時間は気ままに使えた。
 しばらくしてパーティでせしめた大枚を握りしめ、島原の夜の街にマスターがやってきた。アーケードを歩きながら、彼は感動の声を挙げる。「どうしたんだい」と聴く僕に、「いやあ、街だねえ」と目を細めしみじみと呟いた。「俺は山の中に暮らしてるから」
しばらくしてパーティでせしめた大枚を握りしめ、島原の夜の街にマスターがやってきた。アーケードを歩きながら、彼は感動の声を挙げる。「どうしたんだい」と聴く僕に、「いやあ、街だねえ」と目を細めしみじみと呟いた。「俺は山の中に暮らしてるから」街のゴミゴミとした生活を抜けて、野に入る。都市はもはや僕達の目指すべきところではないと思っていた。けれど年中人里離れた丘に暮らし、日が暮れると近辺に灯を見かけぬマスターにとって、島原のような片田舎のアーケードでさえも煌々たる場所なのだろう。時たま訪ね来ることと、そこに暮らすことの格差をしみじみと感じる。例えば海も、時たま訪ね来る者にとっては愛でるべき広がりなのだろうけれども、そこに生活し続ける者にとっては戦いと共生の場だ。そこにリゾートという言葉の持つ無責任さが潜んでいる。そういうわけだ。
「まつをさんたちが帰ってさあ、宿泊客もいない夜なんて、長いよ。特に冬場はねえ。何回目が覚めても夜なんだ」
ソロで山深く分け入った時のことを思い出した。
ウイスキーを呷り肴を喰らう。早々に寝袋にくるまり、眠りにつく。そして丑三つ時に目が覚める。月のない山奥。漆黒の闇という表現そのものだ。瞼を閉じているのか開いているのか分からないような、そんな暗さだ。闇は僕の肉体に密着する壁のようにあって、じりじりと四方から僕を圧迫する。数キロ先から近づいてくる一陣の風が鮮明に耳にいる。沼の水面の微かな音がする。五感のすべてを立ち上がらせる闇の中で、マスターは幾晩となく過ごしているのだろう。

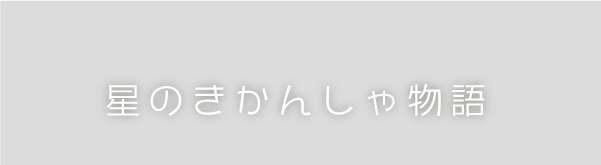




 トップ
トップ オススメ
オススメ 記事一覧
記事一覧 掲示板
掲示板 長崎マニアックガイド
長崎マニアックガイド 長崎の酒場
長崎の酒場 長崎を歩く
長崎を歩く 長崎キャンプ場
長崎キャンプ場 私の手作りキャンプ場
私の手作りキャンプ場 私の家づくり
私の家づくり 長崎インターネットラジオ
長崎インターネットラジオ デザイン
デザイン 絵
絵 音楽
音楽 小説
小説 メール
メール リンク
リンク