電話の向こうでマスターは、弱々しく僕に呼びかけた。
「何してる? まつをさん」
「どうした?」
「別れた」
「すぐ行くよ」
彼女が彼のもとを去っていった日だ。
長い夜だった。
彼は干上がった池のようにひび割れて、家にじっとしていた。
「まつをさん、仏教を教えてくれ」
そう彼は言った。
静かな夜だった。
彼に命の危機を感じた時間帯だ。
色即是空。けれど愛した者と別れる時に、狂おしい苦悩があってこそ人間だ。なぜ自分は彼女を愛したのだろう。なぜ自分は彼女と別れることになったのだろう。どうして自分はこんな人間なのだろう。どうして自分はここにいるんだろう。
 あの夜、マスターは自己存在の意味を求めていた。けれど、結局僕らは生きてるだけなんだ。そう教えてくれていたのは、マスターの生き方そのものだった。人生に意味はない、定義を求めるのは人の悪い癖なんだと。僕達はうまく立ち行かないとき、なぜと問う。因果律を求め、それが自分の人となりに帰結したとき、そして一人では抱えきれないほどの自己否定に繋がるとき、人は危機を迎える。凡人がとれる手は二つだ。ひとつは、今の自分を越えること、つまり全人格的な成長を短期間で遂げること。そしてもう一つは、忘れることだ。
あの夜、マスターは自己存在の意味を求めていた。けれど、結局僕らは生きてるだけなんだ。そう教えてくれていたのは、マスターの生き方そのものだった。人生に意味はない、定義を求めるのは人の悪い癖なんだと。僕達はうまく立ち行かないとき、なぜと問う。因果律を求め、それが自分の人となりに帰結したとき、そして一人では抱えきれないほどの自己否定に繋がるとき、人は危機を迎える。凡人がとれる手は二つだ。ひとつは、今の自分を越えること、つまり全人格的な成長を短期間で遂げること。そしてもう一つは、忘れることだ。彼は自分を見つめていた。俺はだめだと。
「マスター、考えが同じところを廻っているだろう? 同じことをずっと考えているだろう?ぐるぐると考えて、ぜんぜん答はみえないだろう? 同じところを歩いているから、足元がぬかるみ始めて、だんだん足が取られるようになっているだろう?」
「うん」
「やめな、マスター。もう考えていないんだよ」
彼の中で枯渇し、日々追い求めているたものは何だったのだろうかと、振り返る。愛する女性、家庭の団欒、趣味、感動、信頼、安心。自分が「くるまり」たがっていることに、彼は気づいていたのだろうか。
その夜、マスターは初めて自分の生い立ちを話した。
彼は双子の次男として生まれた。生まれてそれほど経たないときに養子に出され、事情を知らずに彼は育った。告知を受けたのは中学校の時だ。そこで一回壊れたと彼は言う。
「俺がよく実家に帰るのは、そのためだと思う。だけど俺は一人なんだ。天涯孤独って感じはどこかにあるよ」
そう彼は言った。
それから毎晩、僕は彼の家に通った。
ドアを開けるのが恐ろしい夜も、何度かあった。

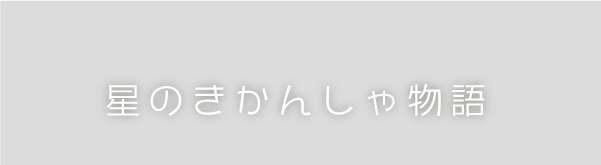




 トップ
トップ オススメ
オススメ 記事一覧
記事一覧 掲示板
掲示板 長崎マニアックガイド
長崎マニアックガイド 長崎の酒場
長崎の酒場 長崎を歩く
長崎を歩く 長崎キャンプ場
長崎キャンプ場 私の手作りキャンプ場
私の手作りキャンプ場 私の家づくり
私の家づくり 長崎インターネットラジオ
長崎インターネットラジオ デザイン
デザイン 絵
絵 音楽
音楽 小説
小説 メール
メール リンク
リンク